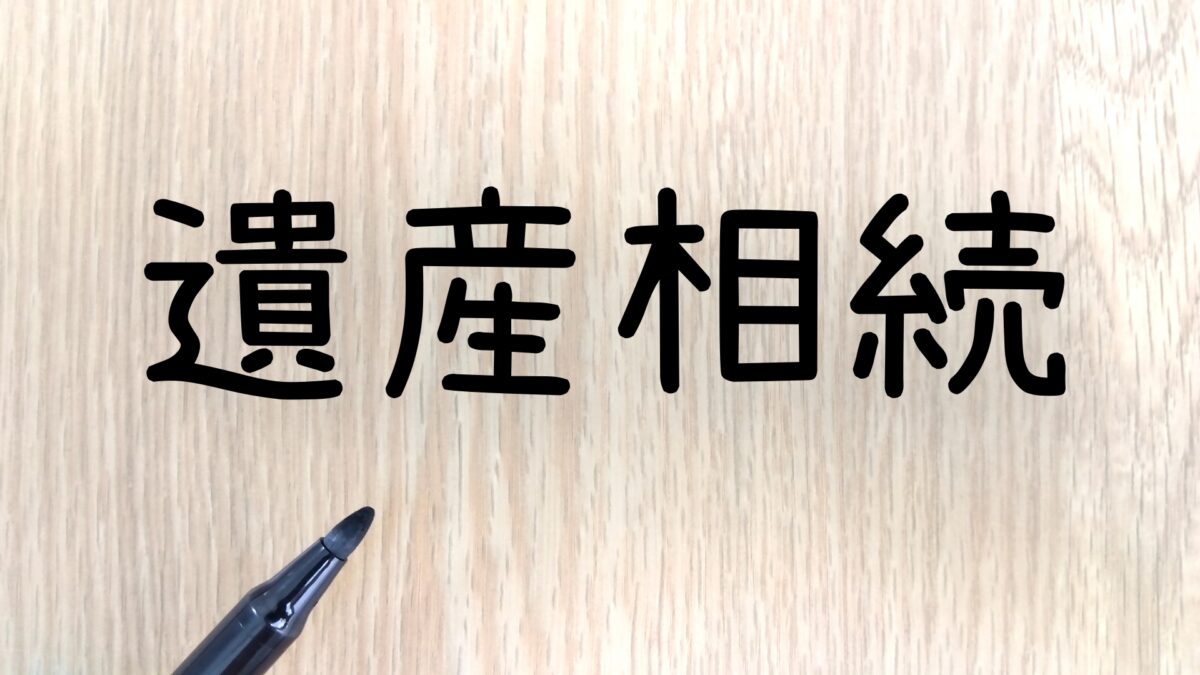もし親戚や親、旦那さんや奥さんが亡くなったら遺産はどうなるのでしょう。相続人は誰になるのでしょうか。今回は、そんな難しい話をどんな方でもわかりやすいように解説していきます。
遺産とは

遺産とは、亡くなった人が所有していたすべての財産のことを言い、「相続財産」とも呼ぶ事もあります。財産といっても金銭的な価値をもつプラスの財産(積極財産)のみではありません。借金などといった弁済しなくてはならないマイナスの財産(消極財産)も遺産に含まれます。
相続の対象となる財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。これらの中には、ネット銀行の預金やネット上の証券口座にある株式、仮想通貨(暗号資産)のように、デジタル化されているために被相続人でなければ存在を把握しにくい財産もあるので、実際の遺産確認の際には注意が必要です。
【プラスの財産】
| 現預金 |
| 外国通貨 |
| 自宅用の建物と土地、賃貸用の建物と土地、店舗 |
| 田畑、山林、空き地、立木など |
| 有価証券(株式、投資信託、公社債など) |
| 債権(売掛金、貸付金、立替金、被相続人が受取人の生命保険金請求権など) |
| 借家権・借地権 |
| 家庭用財産(車、家具、宝石、宝飾品、絵画、書画、骨とう品など) |
| ゴルフ会員権 |
| 船舶・飛行機など |
| 仮想通貨(暗号資産) |
| 知的財産権(特許権・著作権など) |
| 慰謝料請求権・損害賠償請求権 |
| 電話加入権 |
【マイナスの財産】
| 借金(ローン、クレジットカードの未決済分) |
| 買掛金 |
| 医療費や水道光熱費などの未払経費 |
| 未払税金 |
| 未払家賃・未払地代 |
| 未払いの慰謝料・損害賠償金 |
| 預り金(敷金、保証金など) |
| 保証債務 |
マイナスの財産については、これらを相続により引き継いだ場合、相続人が弁済する義務を負います。
相続人とは

相続人とは、被相続人がなくなった場合に財産を相続する人間を指します。
配偶者はどうなるのか
死亡した人の配偶者は相続人となります。もし配偶者がいなかった場合など、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
相続するにあたっての順位とは
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は相続人に含まれません。
第1順位:死亡した人の子ども
その子どもが既に死亡しているときは、その子どもや孫などが相続人となります。
第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
孫が代わりに相続する「代襲相続」とは
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て「孫」「ひ孫」「甥、姪」等が相続財産を受け継ぐことをいいます。
養子の立ち位置
相続人が養子でも、実の子どもとして取り扱われます。
つまり養子はすべて法定相続人の数に含まれます。
相続人が未成年だったらどうなるのか
未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。
しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合などは、親が未成年者の代理人になれないことがあります。このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印等を行うことになります。
ただし、未成年者であっても結婚している等、成人とみなされる場合もあります。
行方不明者がいる場合はどうなるのか
家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任を申し立てるか、失踪宣告の申し立てをする必要があります。
失踪宣告を受けた行方不明者は法律上、「死亡したもの」として扱われます。ですので、遺産分割協議の参加義務はもちろん、相続人から除外されることになります。ただし、その相続人に子がいる場合には代襲相続となります。
そのほか、相続に関する疑問を解決

相続に関して下記の疑問について説明します。
- この人に相続権はあるのか
- 相続権はあるけど相続したくないときはどうしたらいいのか
そのほか疑問点として多く挙げられるものを解説していきます。
相続権がありそうでない人たち
子どもの相続権は、被相続人との関係性でその有無が決まります。つまり、亡くなった方の前妻や前夫との子が実子であれば、現在の親権の所在にかかわらず、その子には相続権が付与されます。
しかし、あなたの配偶者が亡くなった場合のあなたの連れ子の相続権という意味では、被相続人との養子縁組の有無によって相続権の有無も決定され、被相続人の生前に養子縁組をしていた場合には相続人となりますが、そうでない場合にはその子に相続権はありません。
相続人のはずなのに貰えない?「相続欠格」とは
特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことです。遺贈を受けることも出来なくなりますが、欠格者の子は代襲相続が可能です。
相続人側が相続権を剝奪する「相続廃除」とは
相続人の廃除とは、相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはそのほかの著しい非行が相続人にあったときに、被相続人が家庭裁判所に請求して虐待などした相続人の地位を奪うことをいいます。 この申立は、被相続人が生前か遺言書でしかすることは出来ません。
相続放棄するとどうなるのか
相続での悩みとして、最も多いお悩みは『亡くなった親の借金を相続放棄したいこと』と言われています。
次いで、不仲だった家族、疎遠だった親族の相続に関わり合いたくないというお悩みから相続放棄を検討する方も多くいらっしゃいます。
相続放棄は、「相続放棄=その相続は存在しない」ということになります。
また、放棄した相続人に子がいても代襲相続はありません。マイナスの遺産のみ相続しないなど、そのようなことは出来かねます。
相続人でなくても財産を受け取れる人とその条件
被相続人が作成した遺言書により遺産の受取人として指定された人は相続人でなくても、遺産を受け取ることができます。
ただし、以下の2つ注意点があります。
- 遺言書の形式が民法に規定された方式に従っていること
- 法定相続人の遺留分を侵害できないこと
2つ目について、法定相続人の遺留分とは、一定の法定相続人について民法により保障された相続分のことをいいます。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合は、受遺者は法定相続人からの請求に応じ、遺留分を請求人に支払わなくてはなりません。
相続に関する手続きはどうやってするのか

相続をする際の手順について、順番にご説明します。
遺言書の調査
まずはじめに遺言書の確認をしましょう。自宅を探すのはもちろん、銀行や弁護士・司法書士・税理士に預けられている可能性もあります。なお、遺言書が公正証書遺言の場合、公証役場で存在の有無を照会することもできますので問い合わせてみましょう。
相続人の調査・確定
遺言書の調査と同時進行で法定相続人をくまなく調べる作業を行う必要があります。法定相続人とは、相続人になる可能性のある人の事です。
被相続人の前妻との間に子がいる、あるいは生前養子縁組をした子がいる可能性もあります。法定相続人は戸籍謄本を取得して確認できます。
まとめ:遺産の相続人は法律で決まっている

遺産相続は複雑な手続きに思えますが、しっかり確認出来ればそんなに複雑ではありません。相続にはプラスの遺産もマイナスの遺産も関わってきます。 また、相続人が亡くなっている場合などは代襲相続が適用されます。相続権を放棄したい場合は放棄することもできますので、もしわからない場合はすぐに専門家に相談し、正確な判断を仰ぎましょう。