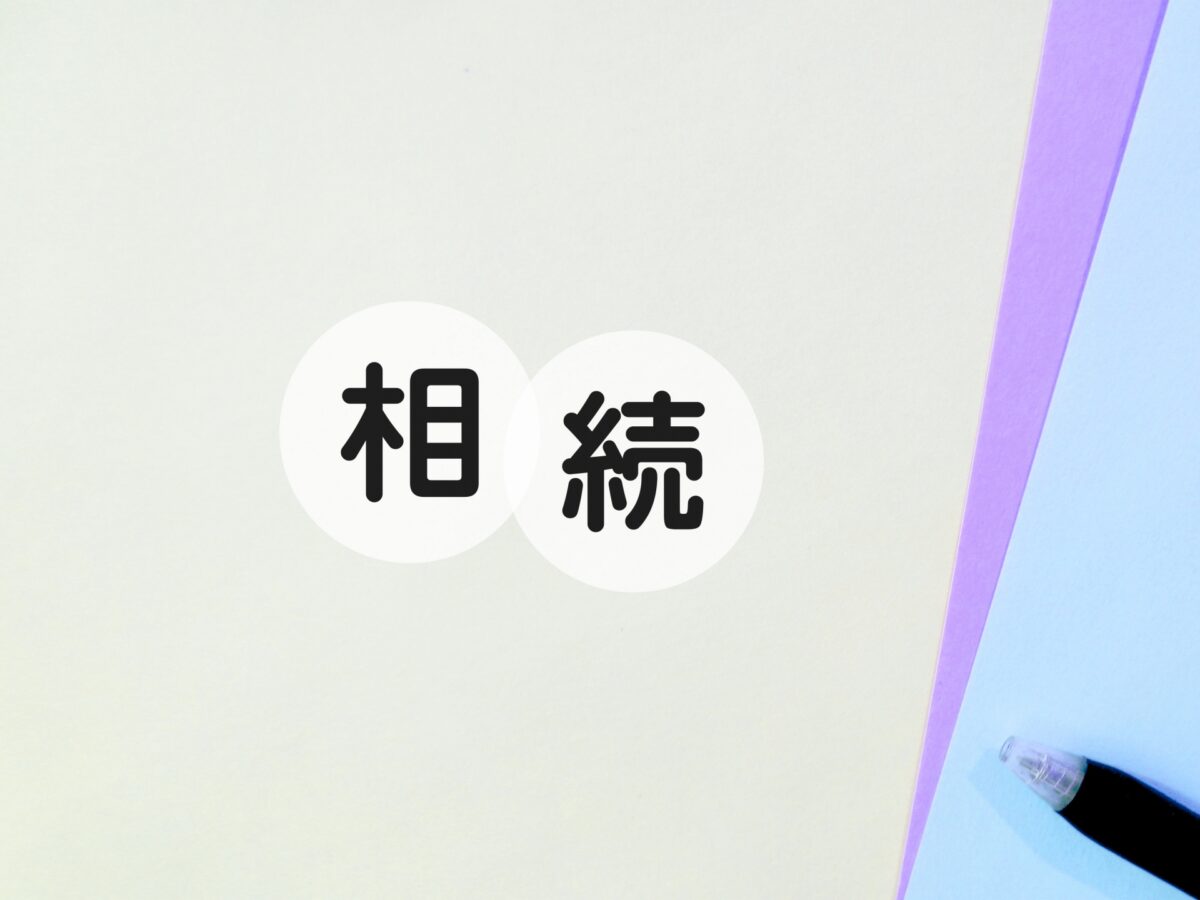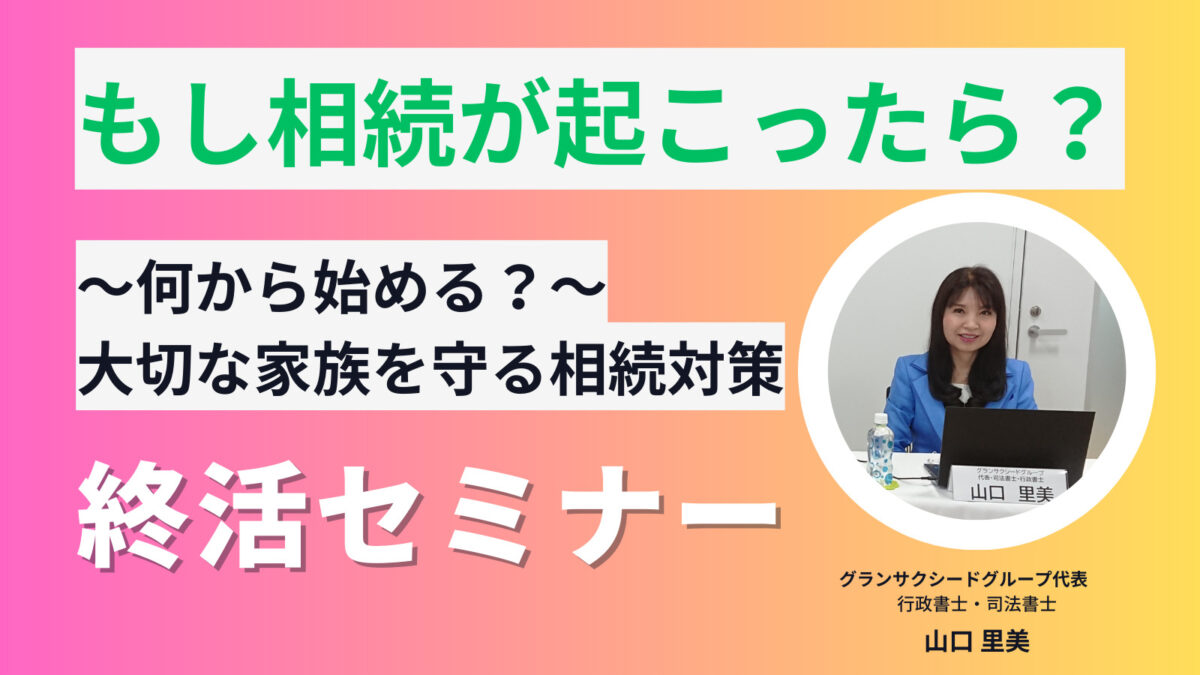自分に万が一のことがあったとしても、死亡保険に加入していれば安心です。残された家族に保険金が渡れば、経済的な不安を軽減できるでしょう。死亡保険加入時には、「子供を受取人にしたい」と考える方もいるのではないでしょうか?子供の年齢や知っておきたい注意点などを解説します。
死亡保険の受取人に指定できる人とは?
死亡保険の受取人は、事前に指定しておくのがおすすめです。受取人が指定されていない場合、自らの思いとはまったく別の人が保険金を受け取ってしまう可能性も。トラブルを防ぐためにも、誰を受取人にするべきか慎重に検討しておくべきでしょう。
とはいえ死亡保険の受取人は、「誰でも指定できる」というわけではありません。一般的には、「配偶者と2親等以内の親族」と定められています。2親等以内の親族に含まれるのは、具体的に以下のような人々です。
・被保険者の子供
・被保険者の両親
・被保険者の祖父母
・被保険者の孫
・被保険者の兄弟姉妹
これらの条件に当てはまらない場合でも、保険会社の規定で死亡保険の受取人に指定できる可能性があります。被保険者との関係性を証明するためにどのような書類を用意すれば良いのか、保険会社に問い合わせて準備しましょう。
子供の年齢と受取人指定

先ほどもお伝えしたとおり、死亡保険の受取人に子供を指定することに、特に問題はありません。すでに配偶者が亡くなっている場合や、離婚で自身が親権を獲得している場合には、子供を受取人に指定するよう検討してみてください。自分が亡くなったあとでも、子供の生活を支えてくれるでしょう。
死亡保険の受取人指定に、年齢制限はありません。たとえ子供が0歳でも、問題なく指定できるでしょう。受取人指定時に、子供の同意も必要ありませんから、親の判断で手続きできます。
ただし、保険金受取時に子供が未成年の場合、親権者や未成年後見人による手続きが必要になります。あくまでも代理での手続きとなり、親権者や後見人には、その事実を証明するための各種書類の提出が求められるでしょう。
未成年後見人による代理手続きを選択する場合、まずは未成年後見人を選定しなければいけません。遺言によって事前に指定しておく方法もありますが、誰を指定するべきか、悩む方も多いでしょう。後見人を指定していなかった場合、家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
家庭裁判所では、さまざまな事情を考慮しながら未成年後見人を選任してくれます。自分自身で選定する必要がない一方で、手続きには時間がかかるでしょう。死亡保険金を受け取れるまでに、やや時間がかかる点も頭に入れておいてください。
死亡保険金を子供に残す場合の注意点とは?
死亡保険金を未成年の子供に残す場合、注意しなければならないのが「子供自身がお金を管理するのは難しい」という点です。ある程度まとまった金額が支払われる死亡保険金。子供の将来のためのお金ですが、適切に管理できなければ意味がありません。
未成年の子供が死亡保険金として大金を受け取った場合、実質的な管理者は親権者や未成年後見人となるでしょう。子供が成長し、自分自身で判断できるようになるまで、適切に管理するよう求められます。しかし実際には、実質的な管理者がお金を使い込んでしまうケースもあります。「子供の将来のために」と残したはずの死亡保険金でも、実質的な管理者の手によって、好きに使われてしまうリスクがあるのです。
子供の未成年後見人は立候補も可能で、家庭裁判所によってもっともふさわしいと思われる人が選任されます。家庭裁判所の判断にゆだねられるため、子供自身が指定できるわけではありません。誰が未成年後見人に指定されるのか、また自分の死後、子供のお金を適切に管理してもらえるのか不安な方は、事前に未成年後見人を指定しておきましょう。
子供が受け取る死亡保険金を適切に管理してくれる、信頼できる人を指定してください。
保険金の受取人指定は途中で変更可能
未成年の子供を死亡保険金の受取人に指定することは可能です。しかし、子供が未成年のうちに保険金を受け取ることになれば、さまざまなトラブルが発生してしまう可能性もあるでしょう。こうしたトラブルを避けるため、検討したいのが「受取人の途中変更」についてです。
「万が一のとき、子供のためにお金を残したい」と思っても、未成年の子供が自分で判断しお金を使えるわけではありません。子供が未成年のうちは、自身の親や兄弟姉妹を受取人に指定しておくのもおすすめです。子供が成人を迎えて、自分自身で管理できるようになったら、あらためて受取人を子供の名前に変更しましょう。
親や兄弟姉妹を死亡保険金の受取人に指定する場合、その目的を事前に伝えておきましょう。また、子供が成人を迎えた段階で受取人を変更する旨も、理解してもらうことが大切です。周囲とのコミュニケーションを大切にしつつ、子供を守る体制を築き上げてください。
死亡保険金の受取人は相続対策にもつながる
配偶者がいる場合、成人した子供を生命保険の受取人にすることは、相続対策としても効果的です。配偶者を受取人にした場合、一次相続での税金負担は軽減されるでしょう。一方で、遺産を受け取った配偶者が亡くなって発生する二次相続では、子供の相続税負担が重くなってしまいがちです。
一次相続の段階で、子供が死亡保険金を受け取っていれば、二次相続の対象となる財産はその分少なくなるでしょう。死亡保険金を法定相続人が受け取る場合、非課税枠が用意されています。上手に活用すれば、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
子供の年齢が幼いときには、「子供自身の将来のために」という目的で、受取人を子供にする方が多いでしょう。子供の年齢が上がり、自分自身の終活を考える段階になったら、相続税対策としての受取人指定について検討してみてください。子供を指定して財産を残し、家族の負担を軽減しましょう。
死亡保険金の受取人は子供の年齢にも考慮して指定しよう

死亡保険に加入する際、誰を受取人に指定するべきか悩む方も多いのではないでしょうか。受取人に年齢制限はありませんので、子供を指定することも可能。一方で、未成年者が保険金を受け取る際には注意点もあります。子供にお金を残すため、事前準備をしっかりとしておきましょう。未成年後見人の指定や法的に有効な遺言書の準備など、やるべき行動は決して少なくありません。今回紹介した情報も踏まえて、より安心できる体制を整えるため、誰を受取人に指定するべきかあらためて検討してみてください。