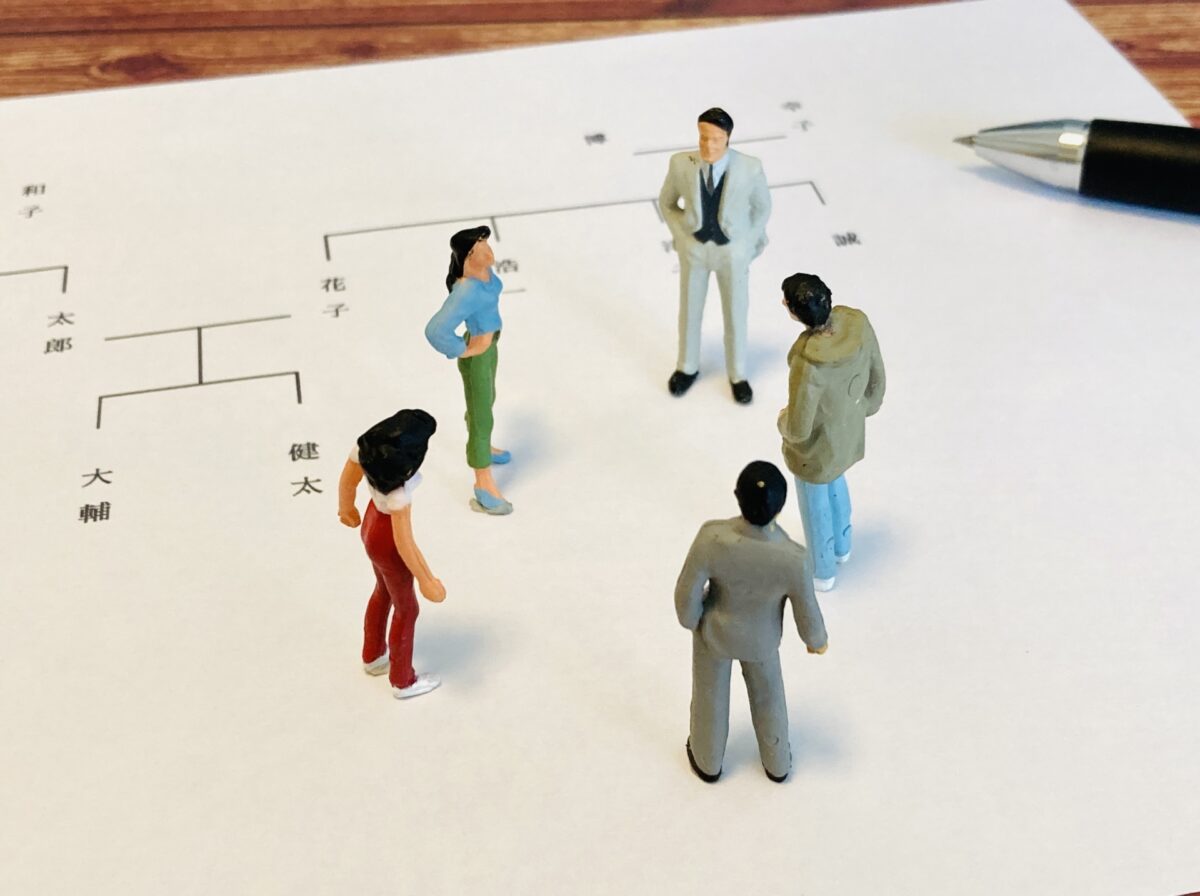自身の老後について考え始めたら、遺産や相続について正しい知識を身につけるところからスタートしましょう。相続とは、いつやってくるかわからないもの。きちんとした知識を持っていれば、いざそのときに慌てなくて済むでしょう。
遺産と言えば「親から受け継ぐもの」というイメージを抱いている人も多いかもしれませんが、状況によっては兄弟姉妹の遺産を受け取るケースもあります。兄弟姉妹の立場で、どうなった場合に遺産が受け取れるのか、わかりやすく解説します。
相続の基本!相続順位について学ぼう

被相続人が亡くなったとき、その財産は相続人へと受け継がれていきます。故人と血縁関係にある人が相続人なるイメージですが、現実には「血縁関係にある人すべて」が相続人になれるわけではありません。相続には「相続順位」が定められており、この順位がもっとも高い人が相続人になれるのです。
被相続人が亡くなった際に、無条件で相続人になれるのは「配偶者」です。故人に夫や妻、法律上の配偶者がいれば、どのような状況であっても相続人として認められます。相続順位が定められているのは、この配偶者以外の相続人についてです。
相続順位がもっとも高いのは、故人の子どもです。子どもが複数人いれば、全員が相続人になります。相続順位2位は、故人の両親。そして第3順位に当てはまるのが、故人の兄弟姉妹です。
相続順位1位から3位の人々は、常に相続人になれるわけではありません。相続順位が高い方から順番が回り、当てはまる人が見つかった段階で、それ以降の順位の人には相続権が発生しない仕組みになっています。
兄弟姉妹が亡くなった際に、故人が結婚していて子どもを設けている場合、配偶者とその子どもが財産を受け継ぐでしょう。故人の兄弟姉妹が相続人になるケースとして考えられるのは、「故人に子どもがおらず、両親もすでに亡くなっている場合」です。
ちなみに、故人には子どもがいたものの、すでにその子どもが亡くなっている場合、相続権は子どもの子ども、つまり孫へと受け継がれます。この場合も、故人の両親や兄弟姉妹が財産を相続することはできません。第2順位の父母が亡くなっている場合、祖父母に相続権が発生します。兄弟姉妹に相続権が発生するものの、すでに亡くなっている場合はその子どもたち、つまり故人にとっての甥や姪が相続権を持ちます。
兄弟姉妹が法定相続人になった場合の相続割合は?
兄弟姉妹の立場で相続人になると決定した場合、どのくらいの財産を受け継ぐのか気になる方もいるでしょう。兄弟姉妹が相続人となるケースは、以下の2パターンしかありません。
・故人の配偶者と共に、兄弟姉妹が相続人になる
・兄弟姉妹のみが相続人になる
下のケースは非常にシンプルで、相続人となる兄弟姉妹ですべての財産を受け継ぎます。兄弟姉妹が複数人いる場合には、財産をそれぞれで等分することになるでしょう。
一方で、故人に配偶者がいる場合、相続財産の4分の3を配偶者が受け継ぎます。兄弟姉妹の法定相続分は全体の4分の1で、相続人が複数人いる場合には、その4分の1をさらに等分に分けてください。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合に覚えておきたい3つのポイント

兄弟姉妹が法定相続人になるケースは、決して少なくありません。兄弟姉妹が亡くなった際には、法定相続人になる可能性があるという点を、頭に入れておきましょう。兄弟姉妹の立場で、頭に入れておきたいポイントを3つ紹介します。
★1.子どもや親が相続放棄する可能性がある
上で解説したとおり、亡くなった兄弟姉妹に配偶者や子どもがいれば、兄弟姉妹の立場で法定相続人になるケースは少ないでしょう。その時点で、「自分には関係ないこと」と捉えてしまう方も多いのではないでしょうか。ここに注意が必要です。
遺産相続とは、プラスの財産のみを受け継ぐ行為ではありません。もし故人が負債を抱えていたとしたら、そのマイナスの財産も相続財産としてみなされるでしょう。この場合、相続順位第1位である故人の子どもたちや、第2位の父母が、そろって相続放棄の手続きを取る可能性も。相続放棄の手続きを取った相続人は「最初からいないもの」として扱われ、相続順位は次に回されます。つまり、第3順位である兄弟姉妹が、相続人になる可能性もあるのです。
相続放棄の手続きには、期限が設定されています。「自分には関係ないだろう」と思い込み、手続きのチャンスを逃さないよう注意してください。
★2.故人の兄弟姉妹の代襲相続は一代のみ
代襲相続とは、相続権を持つ人がすでに亡くなっていた場合に、その相続権が下の世代(もしくは上の世代)にどんどん受け継がれていくことを言います。
故人の子どもが亡くなっていれば、その子どもが、その子どもも亡くなっていればまたその子どもに相続権が発生します。第2順位の両親についても同様で、両親が亡くなっていればそのまた両親、さらにその先の両親と、どんどん遡っていくのです。その範囲は定められておらず、該当する人が存在するなら、どこまででも辿っていけるという特徴があります。
ただし兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は一代のみと決められています。兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪が相続権を持ちますが、すでに甥や姪が亡くなっている場合、その子どもに相続権が渡ることはありません。
★3.兄弟姉妹に遺留分は認められない
もう一点忘れてはいけないのが、遺留分に関する注意点です。遺留分とは、法定相続人が相続できる最低限度の相続分のこと。たとえば故人が遺言書で「○○に全財産を譲る」と言った内容を残していても、法定相続人であれば、遺留分だけは確保できるという特徴があります。
兄弟姉妹の立場で法定相続人になる場合、遺留分は認められていません。故人の遺言は法定相続よりも優先されますから、「配偶者に全財産を譲る」といった内容が残されていれば、兄弟姉妹が遺産を受け取ることはできないのです。
トラブルになりやすいポイントですから、事前に頭に入れておきましょう。
兄弟姉妹が財産を相続する場合の特徴を知ってトラブルを防ごう
兄弟姉妹の立場で、被相続人の遺産を受け取れる可能性はあります。故人に子どもがおらず、すでに両親も亡くなっている場合、相続権が回ってくる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし実際に兄弟姉妹の立場で法定相続人になる場合、相続人の範囲が広がり、トラブルに悩まされるケースも少なくありません。相続に関する基礎知識をきちんと身につけ、トラブルを避けられるように準備しておきましょう。相続順位を知っておくだけでも、事前の心構えができるはずです。