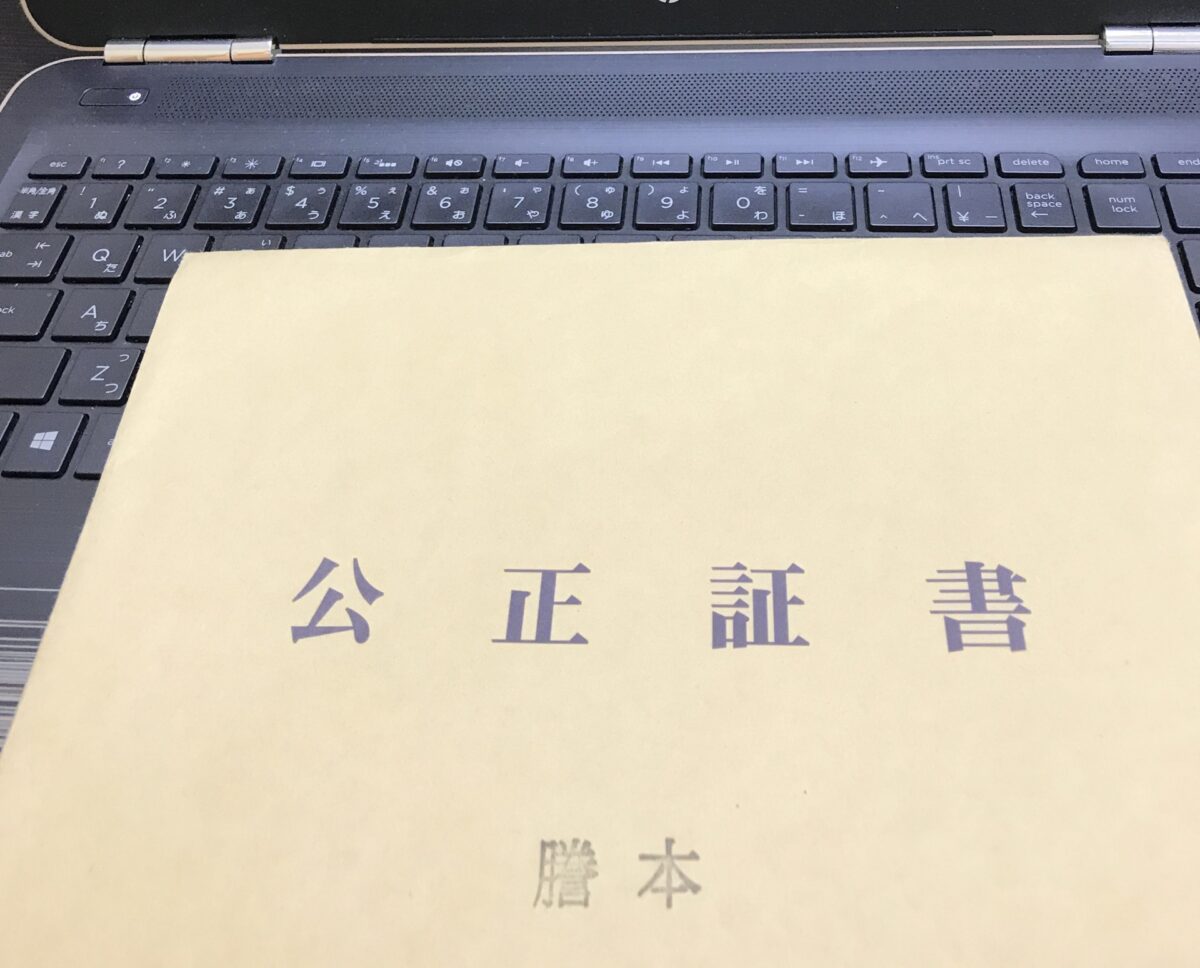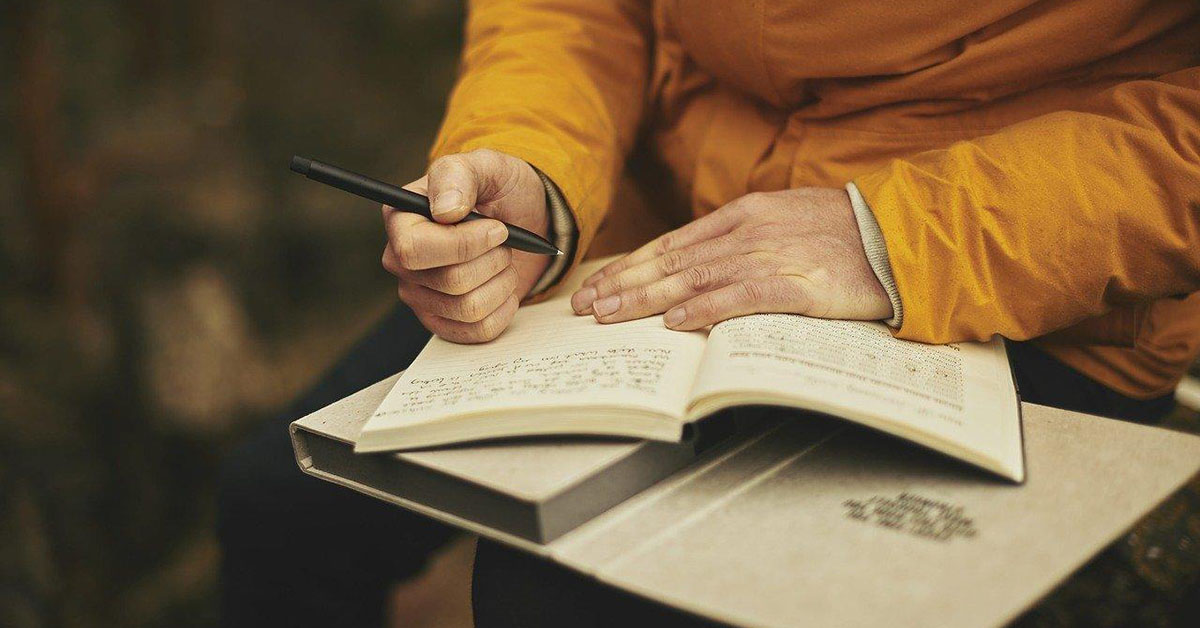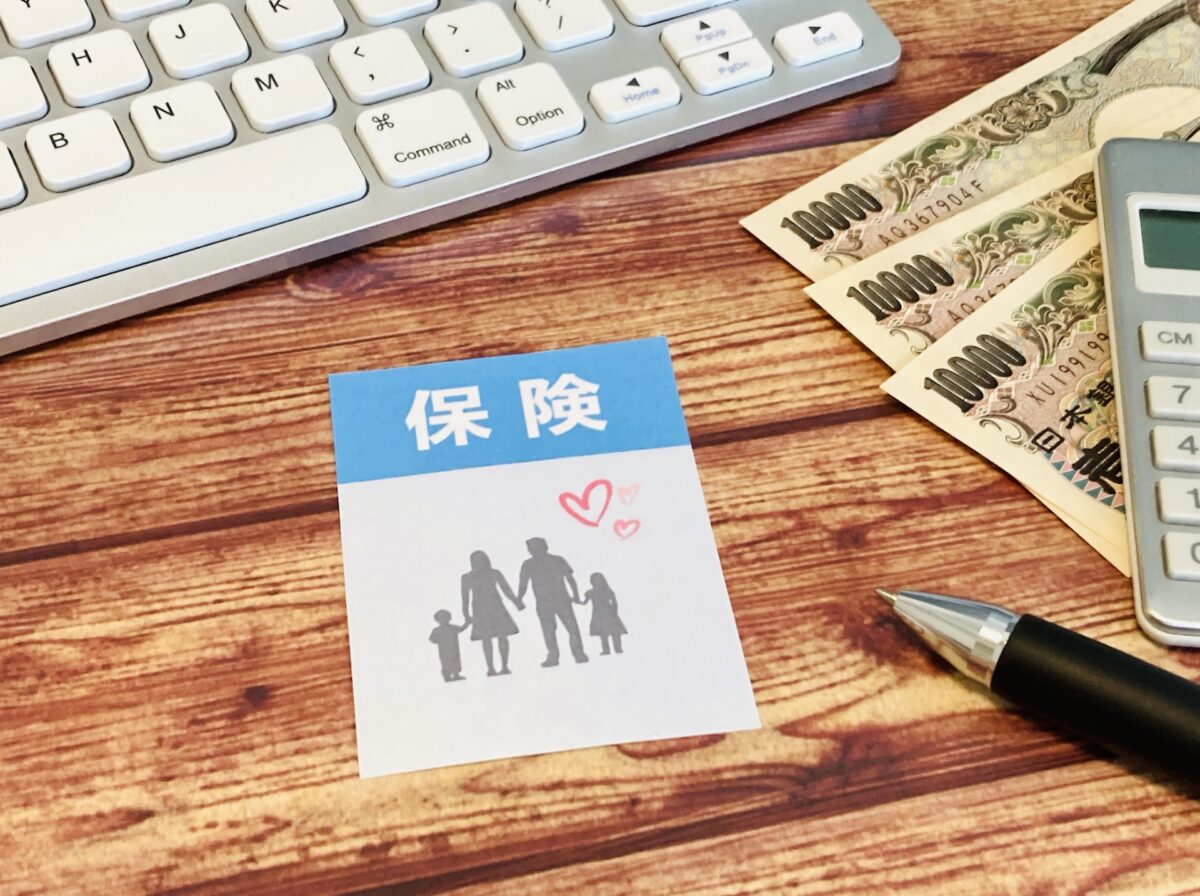ひと言で「遺産」と言ってもその実態はさまざまで、状況によっては「できれば受け取りたくない…」と考える方もいるでしょう。こんなとき、あらかじめ知っておきたいのが遺産を放棄するための手続きについてです。
このコラムでは、遺産を放棄するための手続き、「遺産放棄」について詳しく解説します。混同されやすい「相続放棄」との違いについても紹介するので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
遺産放棄(財産放棄)とは具体的にどういうこと?
遺産放棄(財産放棄)とは、相続権を持っているにもかかわらず、「遺産を相続しない」という立場を表明することを言います。被相続人が亡くなり相続がスタートすると、まずは遺言書の有無が確認されるでしょう。遺言がなければ、その遺産は遺産分割協議によって、どう分けられるのか決定されます。この遺産分割協議にて、「財産を相続しない」と表明すれば、それが遺産放棄(財産放棄)に当たります。
遺産放棄は、法律で明確に定められた手続きではありません。よって事前に特別な準備をする必要もなく、その他の相続人に自身の決意を伝えればOKです。遺産分割協議でその希望が受け入れられれば、無事に遺産を放棄できるでしょう。
また遺産放棄を宣言したからといって、相続人としての立場を失うわけではありません。他の相続人との話し合いにはなるものの、「この遺産は放棄したいが、こちらだけは相続したい」など、柔軟な対応も可能です。後になって新たな遺産が見つかったときにも、またあらためて、相続人としての立場で話し合いに参加できるでしょう。
相続放棄との違いは?
遺産を受け取らない道を考えたとき、もう一つ検討したい道が「相続放棄」です。遺産放棄とよく似た言葉ではありますが、両者の意味合いは大きく異なります。それぞれの意味を正しく把握して、自身の思いに沿った方を選択しましょう。
相続放棄とは、相続人としての権利、つまり相続権そのものを放棄するための法的手続きです。法的にも自身の立場を明確にするため、一定期間内に家庭裁判所にて、必要な手続きを済ませる必要があります。家庭裁判所にて相続放棄が認められれば、その人は「最初から相続人ではなかった」とみなされるでしょう。相続順位は次の人に回され、今後何があっても、相続人としての権利を主張することはできなくなります。
相続放棄の手続きができる期間は、「相続を知った日から3ヶ月間」です。この期間を過ぎると、相続放棄の手続きは選択できなくなりますから、十分に注意してください。
「相続放棄は面倒だから遺産放棄で十分!」は間違い
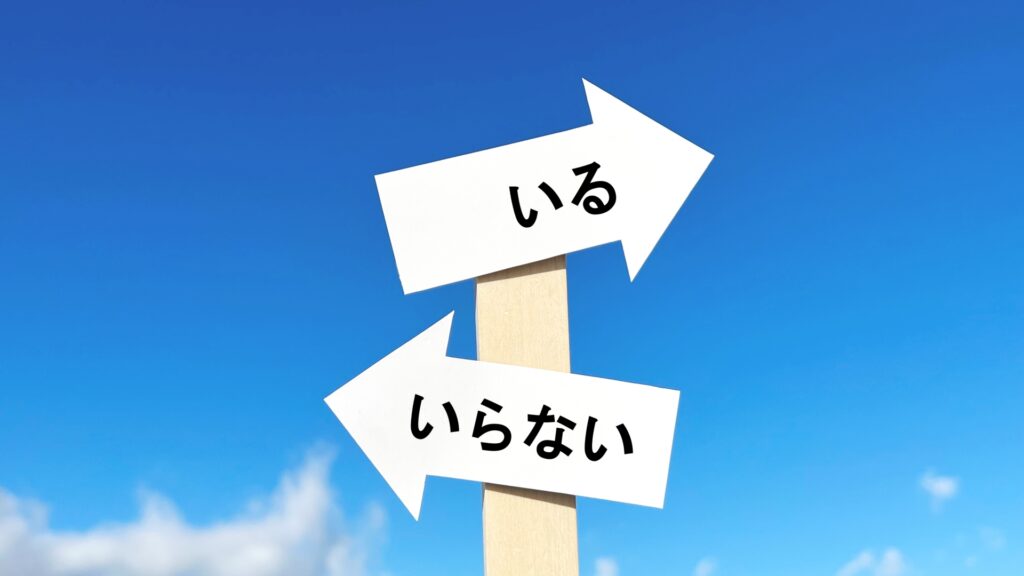
遺産放棄が他の相続人に自身の意思を伝えるだけでOKであるのに対して、相続放棄するためには、家庭裁判所への申し立てが必須です。「どちらにしても財産を受け取らないのだから、より簡単な遺産放棄で十分なのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、この考えは非常に危険です。
なぜなら、被相続人が残す「遺産」とは、常にプラスであるとは限らないからです。万が一、マイナスの財産が相続財産に含まれれば、遺産放棄の意思表明だけでは不十分です。債権者は、相続人に対しても借金を返済するよう求める権利が認められています。法律的にも「自分は相続人ではない」と明らかにしなければ、被相続人の代わりに、自身が借金を背負ってしまうでしょう。
いくら「自分は遺産を受け取っていないので」と説明しても、債権者には通用しません。法律をもとに動いている債権者の取り立ては、そのまま継続してしまいます。
プラスの財産とマイナスの財産の両方が残されている場合には、遺産放棄で十分なのか、それとも相続放棄の手続きを取らなければならないのか、特に慎重に判断する必要があります。遺産分割協議においても、「どうせ財産を相続しないから」と安易に考えるのは辞めましょう。どの遺産を誰がどのように引き継ぐのかを明らかにした上で、自身の立場を明確にするのがおすすめです。
遺産放棄を選んだ方が良いケースとは?
遺産放棄にも相続放棄にも、メリットとデメリットの両方があります。相続放棄のメリットは、相続人としての権利を放棄したという事実を、法的にも認められる点です。一方で、柔軟な対応が難しいというデメリットがあります。
以下のようなケースでは、相続放棄よりも遺産放棄を選んだ方が、メリットが大きくなると予想されます。ぜひじっくり検討してみてください。
★1.基本的には遺産を放棄しつつ、一部のみ受け取りたい場合
遺言書が残されていない場合の遺産相続では、法定相続分に沿って遺産を分配します。しかし、常に遺産を等分に分けられるとは限りません。特に、遺産に土地や建物といった不動産が含まれている場合、相続割合は非常に複雑になるでしょう。
たとえば、「不動産は要らないが、現金だけは受け取りたい」という場合、遺産放棄が有効です。不動産についてのみ遺産放棄をして、その他の財産については受け取りましょう。
遺産放棄の手続きを上手に活用すれば、親族間の余計なトラブルを防止できる可能性があります。
★2.将来的にさらに遺産が発見される可能性がある場合
被相続人が亡くなったあと、一定期間経ってから新たな遺産が発見されるケースもあります。この場合、最初の相続で相続放棄の手続きをすると、後で見つかった遺産についても相続する権利を失ってしまうでしょう。
「今現在明らかになっている遺産は受け取らない」と決めていても、将来的に状況が変化する可能性はゼロではありません。わざわざ相続放棄をするメリットがないのであれば、遺産放棄に留めておくのがおすすめです。将来遺産が発見された場合に、あらためて相続するのか、遺産放棄をするのか、それとも相続放棄をするのか、その時点の状況を考慮して決断できるでしょう。
★3.相続権を次の順位に回したくない場合
相続放棄をしても遺産放棄をしても、「自分が遺産を受け取らない」という結果に変わりはありません。しかし「誰が相続人になるのか?」という視点で考えると、2つの手続きには非常に大きな差があるのです。
遺産放棄を選択する場合、自分自身が相続人として、「遺産を受け取らない」と決断することに。相続権は、当然自分のもとに残ります。一方で相続放棄をすれば、相続権は次の順位へと移っていきます。相続順位が移り、相続人の範囲が広がれば、さらなるトラブルを引き起こしてしまうケースもあるでしょう。
こうしたトラブルを防ぎたい場合も、「相続人の立場のまま遺産だけを受け取らない」遺産放棄には、意味があります。
今回紹介した3つのケースは、どれも「相続財産に負債が含まれていない場合」を想定しています。まずは負債がないかどうかを確認し、その上で、遺産放棄するべきかどうか、検討してみてくださいね。
遺産放棄と相続放棄を知って適切な手続きを

自身の終活について考え始める時期は、身近な人からの相続について考え始めるべき時期でもあります。「遺産を受け取らない」という選択肢についても、ぜひ慎重に検討してみてください。
遺産放棄と相続放棄は、言葉は似ていますが、もたらす結果は大きく違ってきます。それぞれの基礎知識を身につけた上で、自分にとって必要な手続きを選択するのがおすすめです。