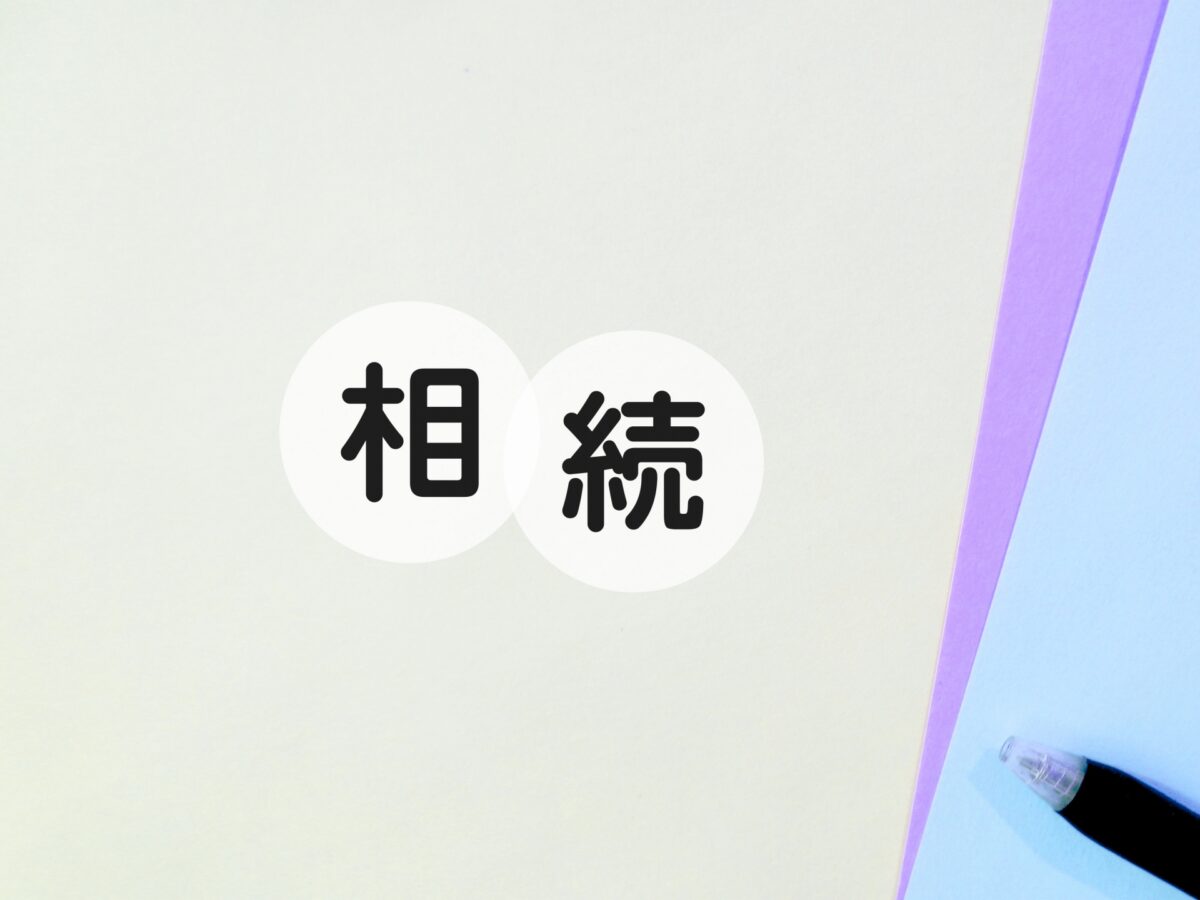家族が亡くなった際に受け取れる可能性がある「遺族年金」。残された家族にとっては、その後の生活の支えとなる、非常に重要な年金と言えるでしょう。
遺族年金は公的年金の一種ですが、「種類や受取人になるための条件がわかりにくい…」と感じる方も多いようです。遺族年金の種類別に、どのような条件に当てはまる人が受取人になれるのか、わかりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
そもそも遺族年金とは?種類を解説
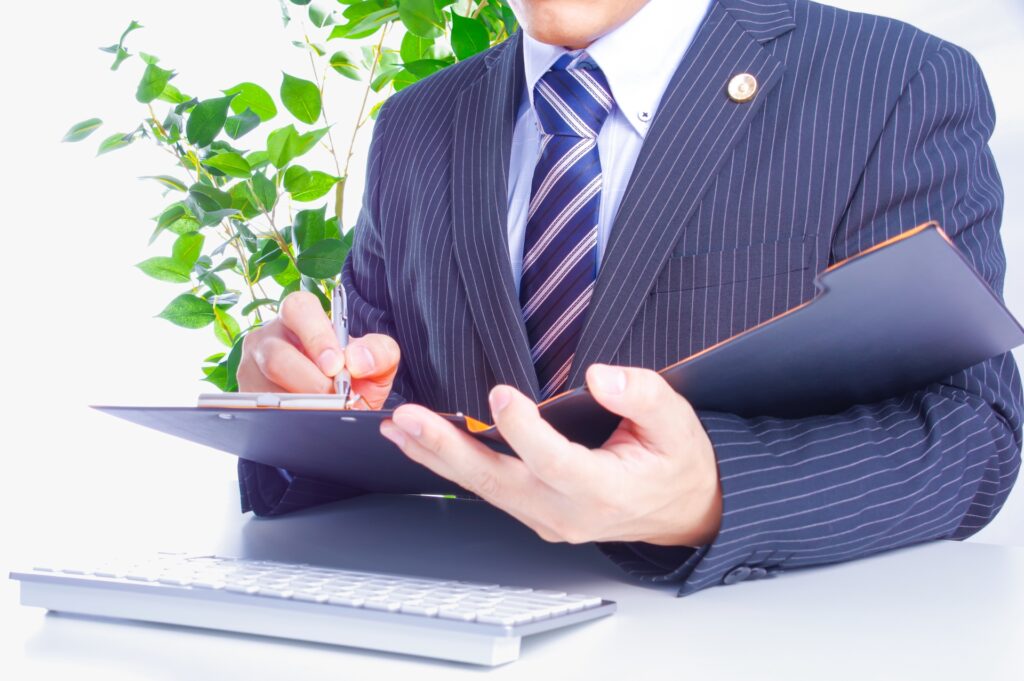
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった際に、その配偶者や子どもに支給される公的年金です。遺族年金には、以下の2つの種類があります。
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金
国民年金から支給されるのが「遺族基礎年金」で、厚生年金から支給されるのが「遺族厚生年金」です。それぞれの加入者が対象であるため、厚生年金に入っていない人は、遺族厚生年金を受け取ることはできません。
遺族基礎年金は、多くの人が加入している国民年金の制度のひとつ。対象になる方も多いことでしょう。一方で、厚生年金に加入しているのは会社員や公務員です。自営業の方や無職の方は対象外になるので、注意しましょう。
遺族基礎年金を受給できる人の条件は?
遺族基礎年金は、残念ながら「国民年金に入ってさえいれば、誰でも無条件で受給できる」というわけではありません。受給要件を満たすためには、以下の条件をクリアする必要があります。
【被保険者(死亡した人)における条件】
・国民年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料を滞納なく納めていること
・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上であること
【受給する家族の条件】
・受給要件を満たす被保険者の配偶者または子であること
・子の年齢が18歳未満、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級に該当すること
・遺族の前年の収入が850万円未満であること(もしくは所得が655万5,000円未満であること)
・生計が同一であること
条件からもわかるとおり、遺族基礎年金の目的は、「亡くなった人の収入で生計を立てていた子どもが18歳になるまでの期間、経済的な援助すること」です。
このため、受給要件を満たした被保険者の配偶者であっても、該当年齢の子どもがいなければ、遺族基礎年金は受給できません。
また配偶者が再婚した場合には、遺族基礎年金の支給はストップします。子ども自身が結婚した場合も支給はストップするので、注意しましょう。
★遺族基礎年金が対象外のときにチェックしたい年金は?
遺族基礎年金の受給要件を満たしていない場合でも、
・寡婦年金
・死亡一時金
これらのお金は支給対象になる可能性があります。寡婦年金とは、死亡した夫の収入で生計を維持していた妻が、60歳~65歳になるまでのあいだ支給される年金です。
また死亡一時金は、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま亡くなった場合に、その遺族に対して支払われるお金です。一時金の支給額は、過去の保険料納付期間に応じて決定されます。
寡婦年金も死亡一時金も、遺族基礎年金の対象者には支給されません。自身の立場を明らかにした上で、受給できる年金や一時金についてチェックしてみてください。
遺族基礎年金で受け取れる金額は?
遺族基礎年金で支給される金額は、定額です。令和4年度の支給額は777,800 円。ここに、受取人の子どもの数に応じて金額が上乗せされる仕組みです。
1人目および2人目の子の加算額は、1人あたり223,800円。3人目以降は1人につき74,600円がプラスされます。夫が亡くなり、18歳以下の子ども2人を育てる妻が遺族基礎年金を受給する場合、その年額は1,225,400円です。月々に換算すると約10万円前後を受け取れますから、家計の足しにできるでしょう。(※1)
受取人資格を満たしているかどうか、しっかりと確認してみてください。
遺族厚生年金を受給できる人の条件は?
遺族厚生年金にも、受給するための条件があります。被保険者と受給する家族、それぞれの条件についてチェックしていきましょう。
【被保険者(死亡した人)における条件】
・厚生年金保険に加入中に亡くなった(保険料納付済期間が全体の3分の2以上)
・厚生年金加入中に初診日がある病気やけがで、5年以内に死亡した(保険料納付済期間が全体の3分の2以上)
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給中に死亡した
・老齢厚生年金の受給権者であった(保険料納付済期間および合算対象期間が25年以上)
・老齢厚生年金の受給資格を満たしていた(保険料納付済期間および合算対象期間が25年以上)
※1
以上5つの、いずれかの条件を満たしている必要があります。
【受給する家族の条件】
・被保険者の妻である
・被保険者の18歳までの子、もしくは20歳未満の障害を持つ子である
・55歳以上の夫、父母、祖父母である
・亡くなった方によって、生計を維持していたこと
受給する家族の条件には優先順位があり、高い人から支給されます。もっとも優先順位が高いのは「子を持つ妻」や「子を持つ55歳以上の夫」です。子を持つ妻がいる場合、受給要件を満たす孫や父母がいても、孫や父母は遺族厚生年金を受給できません。
遺族厚生年金の支給額は、死亡した方の老齢厚生年金の金額をもとに決定されます。報酬比例部分の4分の3が支給金額になりますから、生前に多くの保険料を納めていた人ほど、家族が受け取る年金額も多くなるでしょう。
また遺族厚生年金には、
・夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、18歳までの子(もしくは20歳未満の障害を持つ子)がいない
・子どもの成長によって、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給できなくなった
このような立場の妻に対して、「中高齢寡婦加算」という制度があります。妻が40歳から65歳になるまでの間、年間に583,400円が遺族厚生年金に加算されて支給されます。
遺族厚生年金は遺族基礎年金とは違って、子どものいない妻でも受給が可能です。ただし、30歳未満の妻の場合、受給期間は5年間という制限があります。
30歳以上の妻の場合はその他の欠格事由が発生するまで受給対象になりますから、妻の年齢が非常に大きなポイントになると言えるでしょう。
少し条件が難しいのが、厚生年金に加入した妻が亡くなり、夫が受給対象になった場合です。妻が亡くなった際に、夫の年齢が55歳以上でなければ受給できませんので、注意してください。また夫が55歳のときに妻が亡くなった場合でも、支給がスタートするのは夫が60歳になってからです。
ただし夫が55歳以上であり、なおかつ18歳までの子(もしくは20歳未満の障害を持つ子)を持つ場合、60歳よりも年齢が下であっても支給がスタートします。自身の場合の条件について、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。
遺族年金を受給できるかどうかわからないときは?

遺族年金の受給者に関するルールは、確かに複雑で難しいもの。どうすれば良いのかわからなくなったときには、近くの年金事務所や年金相談センターを訪れてみてください。日本年金機構では、電話による相談窓口も開設しているため、こちらを利用するのも良いでしょう。
自分は無理だろうとあきらめていても、「調べてみたら実は受給対象だった」という事例もあります。必要な情報を整理した上で、一度相談してみるのがおすすめです。
※1 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
※2
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html