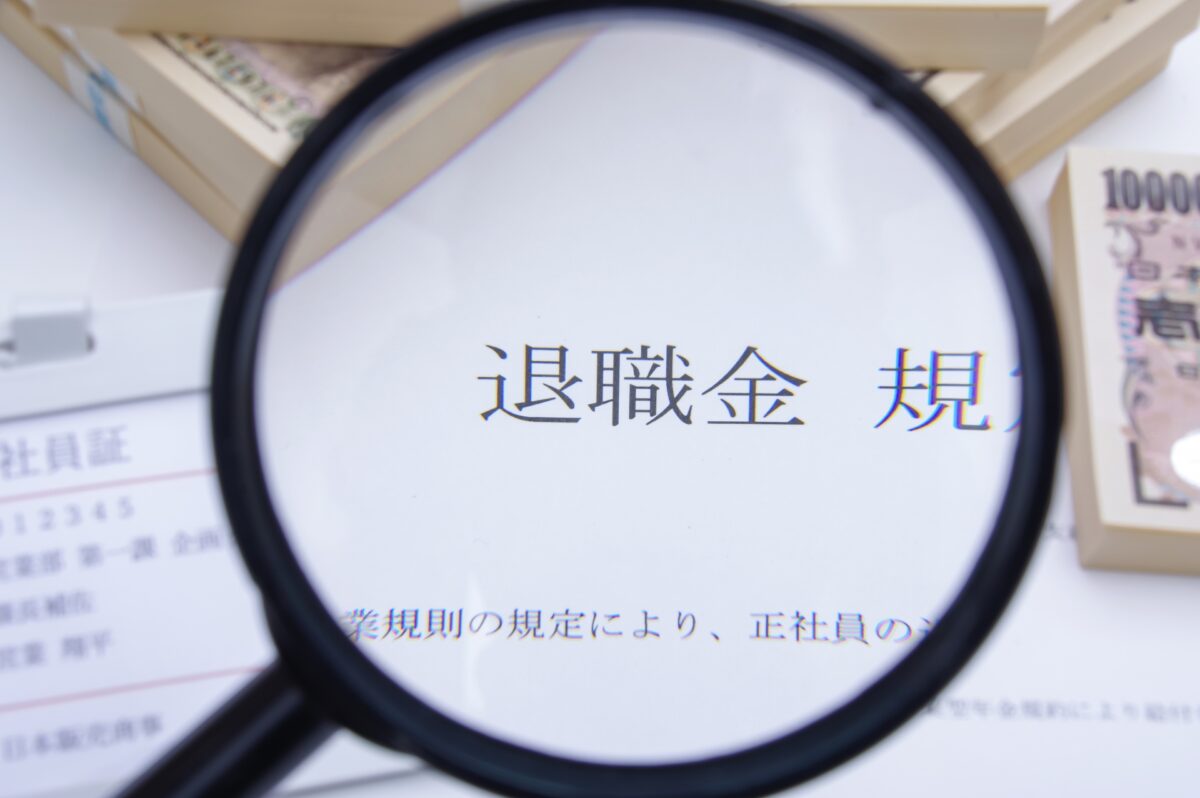小規模企業の個人事業主、会社役員の方にとって、メリットも大きい小規模企業共済。共済契約者死亡によって家族が共済金を受け取る場合、その財産が相続上、どのように扱われるのかについて、詳しく解説します。相続対策としても有効と言われる小規模企業共済の基本とともに、メリット・デメリットについても確認してみてください。
小規模企業共済とは?
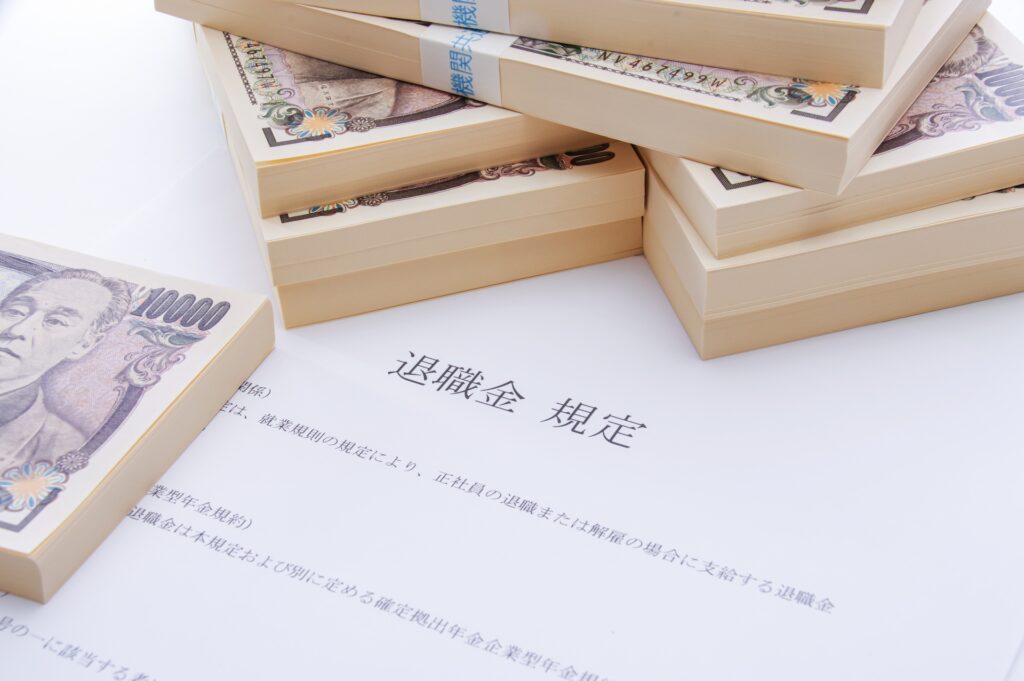
小規模企業共済は、「経営者の退職金」とも呼ばれる制度です。月々の給料からの積立によってまとまった金額を確保。事業を廃止した場合や退職後の生活を安定させるために使用できます。将来の備えとして役立つでしょう。
また共済契約者が死亡した場合、遺族に対して共済金が支払われます。契約者によって生計を維持されていた家族の、その先の生活を守ってくれるでしょう。小規模企業の個人事業主や会社役員にとって、安心できる制度と言えます。
小規模企業共済で受け取った財産の扱われ方は?
契約者が死亡した場合に遺族が受け取る共済金には、「相続財産に含まれない」という特徴があります。受取人固有の財産に当てはまるため、遺産分割の対象にはなりません。遺産分割協議は、小規模企業共済で受け取ったお金以外の財産について行われます。また小規模企業共済以外にも、生命保険金なども相続財産に含まれないため、何が遺産分割協議の対象になるのか、事前に把握しておくことが大切です。
たとえば小規模企業共済で300万円を受け取り、その他の財産が2,000万円あるケースを考えてみましょう。配偶者と子ども2人が相続人になり、配偶者が小規模企業共済の受取人になった場合、まずは配偶者が共済金である300万円を受け取ります。その後あらためて、相続財産である2,000万円分を子ども2人と分け合うことに。法定相続分に沿って分割するなら、相続財産の割り振りは配偶者が1,000万円、子どもが500万円ずつ受け取ります。小規模企業共済と合わせると、「配偶者が1,300万円、子どもたちはそれぞれ500万円ずつ」という割合に落ち着くでしょう。
相続財産に含まれない共済金は、仮に「○○に全財産を譲る」という名前の遺言書が残されていたとしても対象外です。法的に有効な遺言書が残されていた場合、遺留分をのぞき、相続財産については指定された人がすべてを受け継ぐことになるでしょう。しかしこの「相続財産」に、小規模企業共済金は入りません。遺言書の内容にかかわらず、共済金は、受給権を持つものの中でもっとも順位が高い人に支払われます。
また相続財産について相続放棄を選択した場合でも、共済金は受け取れます。事業を営む人が多額の借金を抱えて亡くなってしまった場合、相続放棄がやむを得ないケースもあるでしょう。このような場合でも、共済金は受取可能です。家族の今後の生活に役立ててください。
一方で、覚えておかなければならないのが、相続税上の扱いについてです。契約者死亡によって支給される共済金は、「みなし相続財産」として扱われます。先ほどもお伝えしたとおり、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算には含まれるのです。相続税が発生するのかどうか、また発生する場合いくらになるのかといった計算は、共済金を含めた金額で対応してください。計算が複雑でよくわからない場合には、無理をせず、専門家である税理士に相談するのがおすすめです。
契約者死亡による小規模企業共済金を受け取る人は?
契約者が死亡した場合に小規模企業共済金を受け取る人は、小規模企業共済法にて規定されています。民法上の相続の一般原則とは異なるため、注意してください。具体的な順位は以下のとおりです。
第1順位者 配偶者(※内縁関係者含む)
第2順位者 子
第3順位者 父母
第4順位者 祖父母
第5順位者 兄弟姉妹
第6順位者 そのほかの親族
これらの順位の中で、もっとも順位の高い人が共済金を受け取ります。
小規模企業共済金の特徴の一つは、第1順位者である「配偶者」に、内縁関係者が明確に含まれる点です。戸籍上の届け出はなくても、死亡当時に事実婚の状態にあった配偶者であれば、共済金を受け取れます。
第2順位から第6順位までの受取人には「共済契約者が亡くなった当時、共済契約者の収入によって生計を維持されていた人」という条件があります。生計を維持されていたと認められない場合、第7順位以下に落とされるため注意しましょう。具体的にどのような条件で「生計を維持されていた」と認められるのかは、問い合わせて確認するのがおすすめです。不安な点があれば、事前に専門家に相談しておくのも良いでしょう。
小規模企業共済のメリット・デメリット
契約者の死亡時にも共済金が支払われる小規模企業共済。そのメリット・デメリットは以下のとおりです。
【メリット】
・掛け金が所得控除できる
・掛け金は自分で調整できる
・掛け金が無駄にならない
小規模企業共済の掛け金は、所得控除の対象です。加入時から節税効果を実感できるでしょう。支払う金額は自分で調整できるため、生活の負担になりにくいという特徴もあります。将来の備えとして活用できるはずです。
もともと「小規模企業の退職金」という目的で使われている制度ですから、たとえ死亡しなかったとしても、支払ったお金が無駄になる恐れはありません。退職時に共済金を一括で受け取る場合は退職所得として、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得として扱われます。税制上の扱いが違ってくるため、受け取り方法は慎重に検討してみてください。
一方で小規模企業共済にもデメリットはあります。加入期間が短ければ、共済金の受け取りで損をするリスクがあるでしょう。具体的には、契約期間が12カ月未満の場合、準共済金や解約手当金が支払われず、掛け捨て扱いになってしまう恐れがあります。加入期間が20年未満の場合、受け取る共済金が過去に支払った掛け金の総額を下回る、いわゆる「元本割れ」になってしまうでしょう。
さらに契約者が死亡した場合も注意が必要です。受取人の順位が定められている小規模企業共済制度ですが、順位に当てはまる人がいなければ、受給権者不在と判断されます。共済金は受け取れません。また受取人を事前に指定できない点も、デメリットと言えます。
小規模企業共済の特徴を知った上で検討を

小規模企業共済には、「契約者が亡くなった場合でも、家族のために財産を残せる」というメリットがあります。たとえ相続放棄の手続きをとっても、共済金は受け取れますから、家族の生活の安定にも役立つでしょう。一方で共済金制度にはデメリットもあります。両者を知った上で賢く活用してみてください。