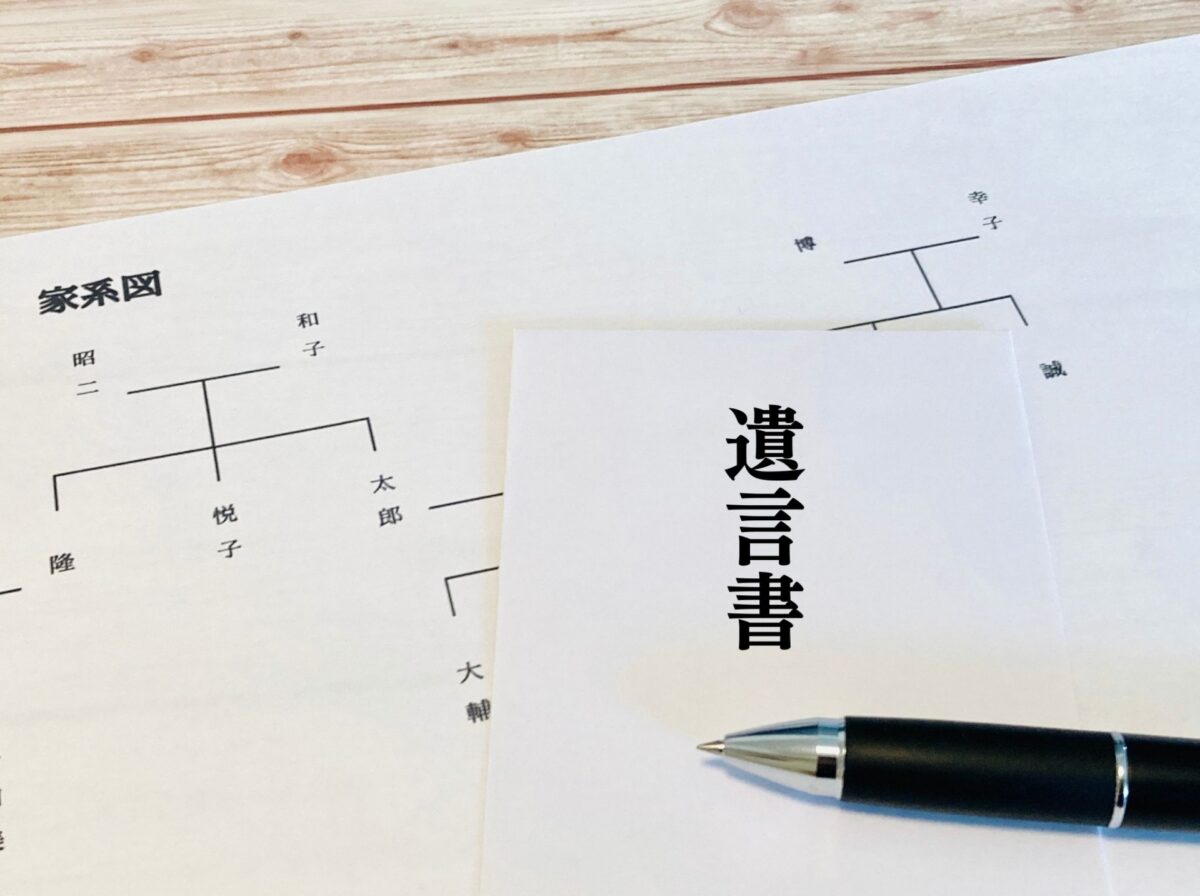終活の一環として、考えておきたいのが「相続」についてです。「どうせ大した財産はないから…」と油断していると、思わぬ親族間トラブルに発展する可能性も。特に「被相続人の兄弟姉妹」について、相続とどう関連するのか知っておきましょう。
相続に関する兄弟姉妹の基礎知識と、遺言書の内容や作成するメリットについてまとめます。
相続に兄弟姉妹が関わるケースとは?
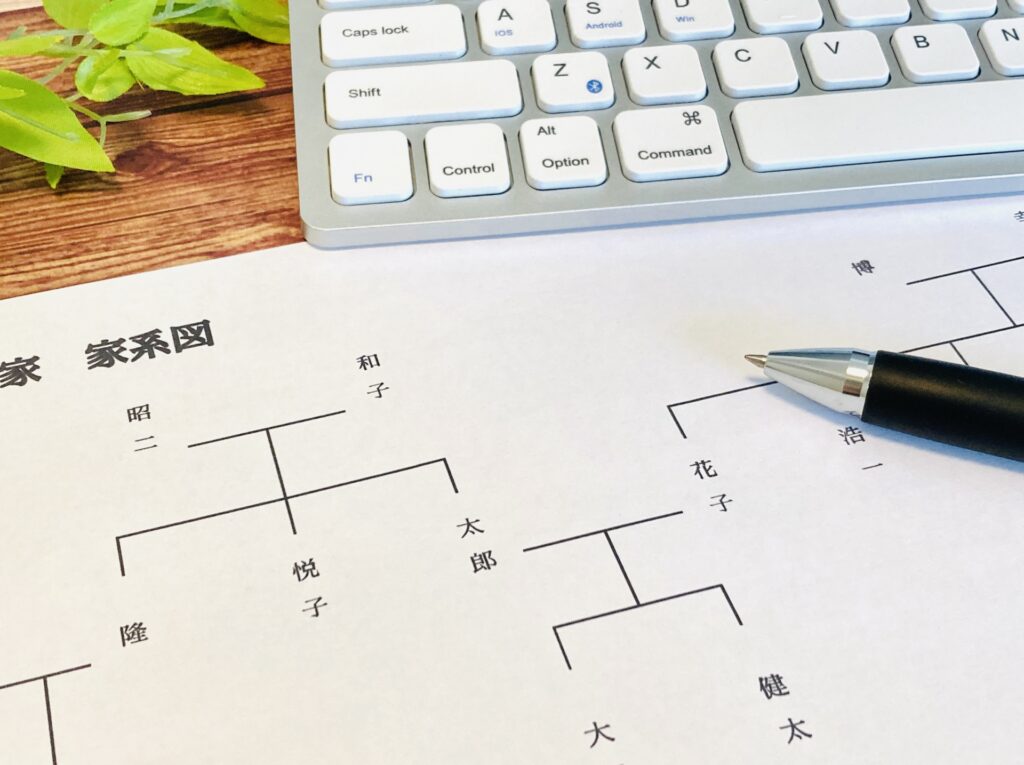
相続トラブルを回避するため、まず頭に入れておきたいのが法定相続人の範囲についてです。法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を受け継ぐ権利を持っている人」のこと。一定範囲内の血族のうち、優先順位の高い人から法定相続人になれる仕組みです。
「自分が亡くなったあと財産を受け継ぐ人」と言えば、自身の配偶者や子どもをイメージする方も多いのではないでしょうか?しかし法定相続人になる可能性がある人は、それだけではありません。状況によっては、自身の兄弟姉妹、そしてその子どもたちが法定相続人になる可能性もあるのです。
相続が発生した際に、必ず相続人になるのが「被相続人の配偶者」です。一方で、それ以外の血族は、以下の順位に基づいて相続人になるかどうかが判断されます。
第1順位 被相続人の子ども(もしくは代襲相続人)
第2順位 被相続人の親など(直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(もしくは代襲相続人)
第1順位から第3順位までは、「もっとも順位が高い人のみ」が相続人になれます。つまり、兄弟姉妹が相続人になるのは以下のようなケースです。
・両親や祖父母がすでに亡くなっていて、被相続人に子どもがいない
・被相続人の両親・祖父母・子どもがすでに亡くなっていて、孫もいない
・第1順位と第2順位に当てはまる人がいても、その全員が相続放棄をした
被相続人の両親・祖父母・子どもがすでに亡くなっている場合でも、孫がいれば、子どもの代襲相続人として相続権を持ちます。このため、兄弟姉妹が相続人になることはありません。同順位の相続人のすべてが相続放棄を選択した場合、相続権は次の順位へと回されます。この場合、子どもや親が生存していても、兄弟姉妹が相続人になる可能性があるでしょう。
このように、兄弟姉妹と相続は、決して無関係ではありません。特に昨今は、子どもを持たない選択をする夫婦も増えてきています。相続順位が兄弟姉妹にまで回る可能性がある点を踏まえて、さまざまな準備を整えていくことが大切です。
兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点とは?
終活の一環として相続について考える場合、「すでに両親や祖父母が亡くなっている」というケースも多いでしょう。この場合、自身に子どもや孫がいなければ、兄弟姉妹が相続人になる可能性は高いと考えられます。兄弟姉妹が相続人になると想定される場合、以下の点に注意しましょう。
★1.配偶者に全財産を残せない
子どもがいない夫婦の場合、「自分が亡くなったあとは配偶者に全財産を譲りたい」と考える方も多いはずです。しかし先ほどもお伝えしたとおり、子どもや親がいなければ、兄弟姉妹が法定相続人に。自分の兄弟姉妹が遺産の分割を希望した場合、配偶者はそれを受け入れざるを得ないのです。
ちなみに、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が遺産の4分の1を受け取る権利を持ちます。「遺産のほとんどが不動産」という場合、兄弟姉妹に遺産を分割するため、売却せざるを得ない可能性も。たとえそれが、夫婦にとっての終の棲家であっても状況は変わりません。配偶者が、住む場所を失うリスクもあるでしょう。
★2.戸籍収集が大変になる
兄弟姉妹への遺産分割に問題がない場合でも、手続きのために必要な戸籍収集は、決して簡単ではありません。子どもや親が相続人になるケースと比較して、難易度はアップします。
兄弟姉妹が相続人になる場合、第1順位や第2順位に当てはまる人が存在しないことを証明するための書類が必要です。具体的には、被相続人の戸籍のすべてや、両親の戸籍謄本の一式を準備する必要があるでしょう。兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいる場合、その人の分の戸籍謄本一式も必要になります。
★3.相続税が高い
兄弟姉妹が相続人となって財産を受け継ぐ場合、相続税は20%割り増しになります。遺産分割に納得していても、相続税が原因でトラブルになる可能性もあるので注意しましょう。
遺言書を残すメリットとは?
兄弟姉妹が相続人になる場合、遺言書を残すメリットは以下のとおりです。
・配偶者に全財産を相続させるよう指定できる
・兄弟姉妹の相続税負担に配慮した遺産分割を指定できる
兄弟姉妹が相続人になる場合の大きな特徴は、「遺留分を請求する権利を持たない」という点です。遺留分とは、遺産のうち最低限相続できると定められている取り分のこと。たとえ遺留分が侵害されても、それを請求する権利は、兄弟姉妹に認められていないのです。つまり、法的に有効な遺言書にて「自身の配偶者に全財産を譲る」という文言を残しておけば、兄弟姉妹に財産を受け継ぐ権利は発生しません。自身が亡くなったあとの配偶者の生活を守れるでしょう。
ある程度年齢を重ねていると、兄弟姉妹としての関係性が希薄になっているケースは多いものです。配偶者と兄弟姉妹の間の話し合いが、スムーズに進むとは限らないでしょう。遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要はなく、親族間トラブルが発生する恐れもありません。
また遺言書であれば、相続税負担に配慮する形で、誰に何を残すのか指定できます。兄弟姉妹への配慮とともに、大切に思う気持ちも伝えやすくなります。自分自身が気持ちよく旅立つためにも、できる準備は整えておくのがおすすめです。
兄弟姉妹と相続への関わりを知り具体的な準備を整えよう

自身が亡くなったあと、誰が財産を相続するのか、事前に考えておきましょう。兄弟姉妹が相続人になる場合、「関係が薄い兄弟姉妹よりも、生活をともにしてきた配偶者に全財産を残したい」と思うのは当然のこと。この場合、遺言書を残しておくのがおすすめです。シンプルな内容でも、十分に効果を発揮してくれます。自身が亡くなったあとの配偶者の生活を守りやすくなりますし、余計なトラブルでストレスを抱えるような恐れもありません。
実際の遺言書の内容については、弁護士や司法書士といった専門家に相談しつつ、決定するのがおすすめです。実際に誰が相続人になる可能性が高いのか、またどういった点に配慮して遺言書を残すべきなのか、的確にアドバイスしてもらえるでしょう。専門家の協力のもとで、自身の希望を叶える遺言書を用意してみてください。