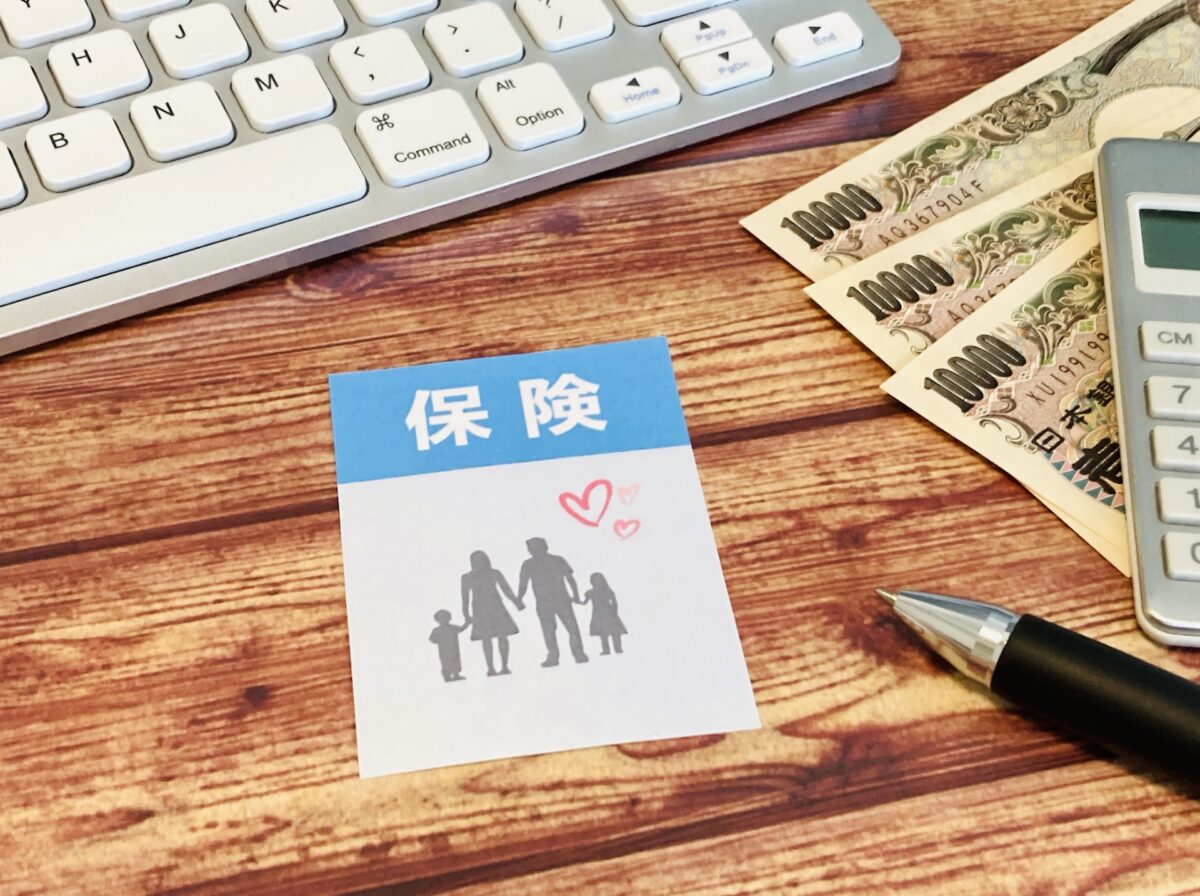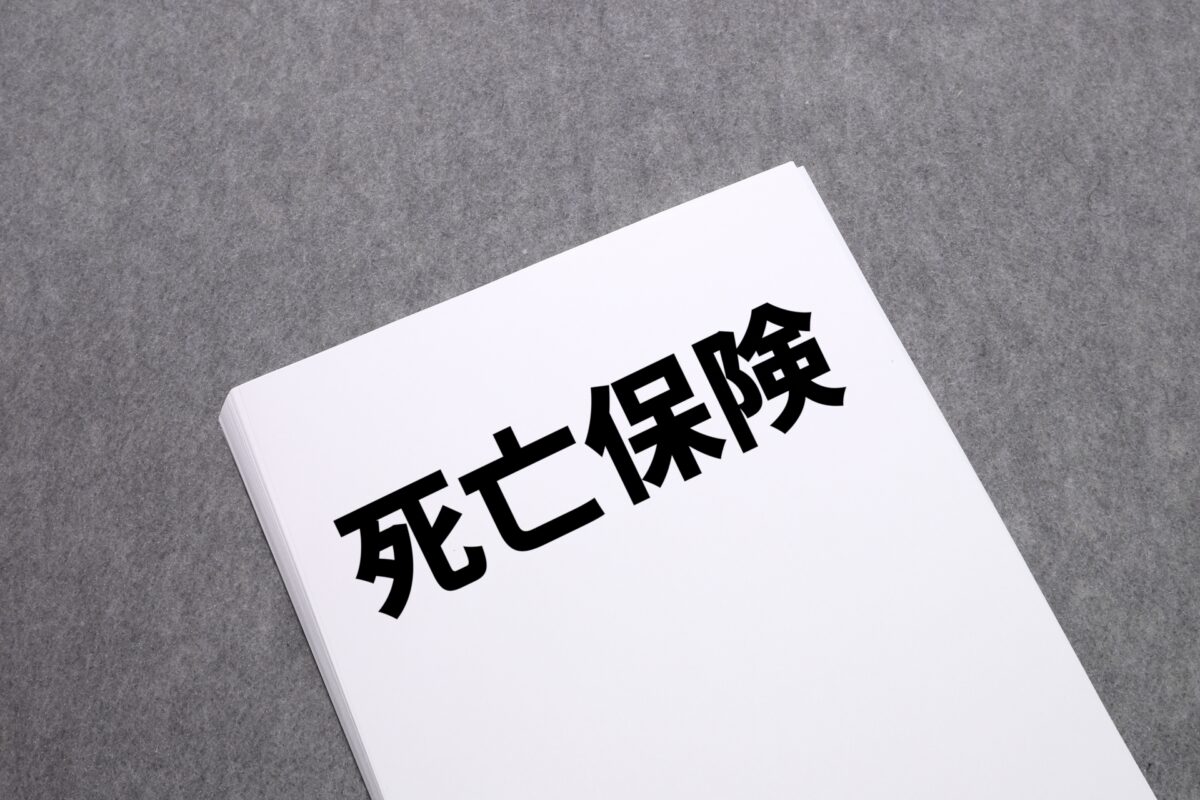一家の働き手であった家族が亡くなったとき、残された人々の生活は非常に厳しくなってしまうでしょう。子供がいる世帯にとっては、その将来にまで影響を及ぼしかねません。こうした人々を支えるため、用意されているのが遺族年金の制度です。子供の年齢に応じて受取額が変わるため、事前に知識を身につけておきましょう。
遺族年金とは?
まずは遺族年金の基本について学んでおきましょう。遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた家族が受け取れる年金のこと。年金加入者が亡くなった際に、その家族が路頭に迷う恐れがないよう、整備されている制度です。
国民年金に加入していた場合に、対象となる可能性があるのは遺族基礎年金です。厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金の対象となります。どちらを受給する場合も、指定されている条件を満たしている必要があります。
遺族基礎年金を受け取れるかどうかは、「子供の年齢」によって違ってくるでしょう。子供がいない場合、残念ながら対象外です。一方、遺族厚生年金はより幅広い家族が受給できます。子供の有無や子供の年齢にかかわらず受給できる可能性があるため、ぜひチェックしてみてください。遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給資格を満たしている場合、両方の年金を受け取れます。生活を安定させるため、役立てましょう。
遺族年金と子供の年齢に関係性は?

遺族年金の受給には、子供の年齢が深く関わっています。遺族基礎年金と遺族厚生年金、それぞれの関わり方は以下を参考にしてみてください。
★遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金の受給資格を持つのは、「子供を持つ配偶者」もしくは「子供」のいずれかです。この「子供」には、「18歳になった年度の3月31日までにあたる」という条件があります。一般的には「高校卒業のタイミングまで」と言えるでしょう。
子供が障害年金の障害等級1級または2級に認定されている場合、年齢条件は「20歳」へと変更されます。通常の場合と比較して、2年間長く遺族基礎年金を受給可能です。
遺族基礎年金は、子供が年齢条件を満たさなくなった場合に支給が打ち切られます。このため、受給開始時点で子供が何歳であったのかによって、支給総額が変わってくるでしょう。0歳のときに受給対象になれば、その分受給できる期間が長くなります。これは、遺族基礎年金の目的が「18歳未満の子供の養育を支えるため」である点に関連しています。
ちなみに、令和4年4月からの遺族基礎年金の支給額は以下のとおりです。
【子供を持つ配偶者が受取人になる場合】
777,800円+子共の加算額/年
【子供が受取人になる場合】
777,800円+2人目以降の子の加算額/年
1人目および2人目の子供には、1人あたり年223,800円が加算されます。3人目以降の子供は、1人あたり年74,600円です。子供が受取人になる場合、上の計算式で求められた金額を子供の数で割った額が、1人あたりの受給金額になります。
★遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持されていた方の中で、以下の人々に受給資格が認められています。
第1順位 妻
第2順位 子供
第3順位 55歳以上の夫
第4順位 55歳以上の父母
第5順位 孫
第6順位 55歳以上の祖父母
受給資格が認められる人のうち、もっとも順位の高い人に支給される仕組みです。
妻に次いで高い順位となる子供ですが、ここにも年齢制限があります。具体的には、遺族基礎年金と同じ「18歳になった年度の3月31日までにあたる」人。障害等級1級または2級の状態にある場合、20歳未満まで認められています。この年齢条件を満たさない場合、順位は次へと移ります。ちなみに、第5順位にあたる孫にも、同じ年齢条件が適用されるため、条件を満たすかどうか慎重に判断してみてください。
もっとも高い順位にある妻ですが、年齢条件を満たす子供がおらず、自身が30歳未満の場合は受給期間が5年間と制限されます。こちらも併せてチェックしてみてください。
遺族厚生年金で受給できる金額は、被保険者が生前に支払った保険料によって異なります。平均標準報酬月額と被保険者期間から求められるため、「毎月の給与が多く、年金加入期間が長い人ほど多くの年金を受け取れる」という仕組みです。
子供が年齢条件を満たさなくなった場合の手続き方法は?
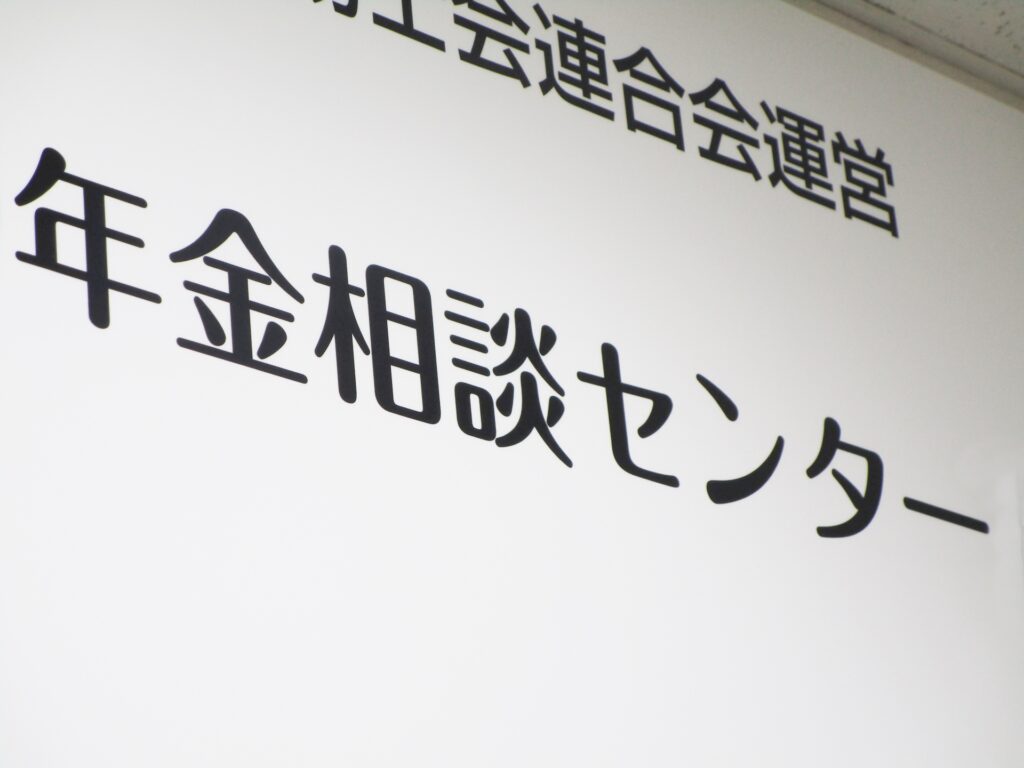
遺族基礎年金も遺族厚生年金も、子供の年齢によって支給状況が違ってきます。子供が18歳を迎えたのち、年度が切り替わったタイミングで遺族年金の支給はストップされるでしょう。
通常、遺族年金の受給権を失ったときには「遺族年金失権届」を提出する必要があります。ただし子供の年齢条件によって受給権を失った場合、この手続きは必要ありません。年金事務所や年金センターで特別な手続きをしなくても、自動で支給はストップするので安心してください。
子供が複数人いる場合、年齢条件を満たさなくなった人は自動的に受給対象から外されます。年齢条件を満たす子供分のみで計算され支給される仕組みです。受給対象の子供がすべていなくなった時点で、遺族年金は受給できなくなります。
子供の年齢が18歳未満でも遺族年金を打ち切られる場合とは?
子供の年齢が18歳未満でも、以下の条件に当てはまる場合、遺族年金の受給資格を失います。年金を打ち切られてしまうので注意してください。
・亡くなった場合
・結婚した場合
・直系血族または直系姻族以外の方の養子になった場合
受給権を持つ人が亡くなれば、受給資格は失います。その資格を、別の人が受け継ぐことはできません。18歳未満の子供がいることで遺族基礎年金の受給資格を満たしていた配偶者も、子供が亡くなれば年金は受給できなくなってしまいます。
子供自身が結婚した場合や、養子に出た場合も、遺族年金は打ち切られます。結婚すれば一人前と扱われますし、親の遺族年金で生活を支える必要はなくなります。直系血族または直系姻族以外と養子縁組をした場合も、新たに生活の場が整うため、受給資格を失うでしょう。
遺族年金と子供の年齢の関係性を理解して手続きを
幼い子供を残して一家の大黒柱が亡くなれば、「今後の生活をどうするべきか…」と悩む方も多いでしょう。こんなときには、遺族基礎年金や遺族厚生年金が残された家族の生活を支えてくれます。実際に遺族年金を受給できるかどうかは、子供の年齢によって違ってきます。18歳未満かどうかが鍵となりますから、ぜひチェックしてみてください。子供の年齢条件も理解した上で、手続きや事前準備を進めてみてください。