「将来のために遺言を残したい」と思ったら、まずは遺言書に関連する基礎知識を身につけましょう。今回は遺言書情報証明書について解説します。具体的な内容や、活用方法・取得方法を紹介。後々のトラブルリスクを避けるためにも、ぜひチェックしてみてください。
自筆証書遺言書保管制度とは?

遺言書情報証明書は、「自筆証書遺言書保管制度」に関連する証明書です。令和2年7月よりスタートした新しい制度で、自筆証書遺言書に関するトラブルを予防する目的で設立されました。
遺言形式には、以下の3つが存在しています。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
この中で、もっとも手軽に残せるのが自筆証書遺言です。いくつかの条件を満たす必要があるものの、自筆証書遺言は「自分だけの力でいつでも好きな場所で作成できる遺言書形式」です。終活ブームの今、指南書をもとに自力で自筆証書遺言を残そうとする方も多いのではないでしょうか。
しかし自筆証書遺言には、自力作成できるからこそのデメリットも。具体的には、以下のようなポイントが挙げられるでしょう。
・自宅で保管している最中に紛失してしまう
・自宅で保管中に内容を改ざんされてしまう
・自身が亡くなったあとに、遺言書を発見してもらえない
・最初から最後まで専門家の目に触れないことで、法的な要件を満たせていない
どれも遺言書の役割を果たさない、非常に重大なトラブルだと言えます。
自筆証書遺言書保管制度は、自力で作成した遺言書を法務局で保管。これらのトラブルを予防できます。自宅ではない場所で保管すれば、改ざん・紛失リスクはありません。遺言内容に不満を持つ親族の手で、勝手に処分されてしまうような恐れもないでしょう。
また保管時には、専門家による外形的なチェックを受けられます。遺言内容に関するアドバイスは受けられないものの、作成した自筆証書遺言書が法的に有効な形で整えられているかどうか、確認してもらえます。自筆証書遺言を残すのであれば、ぜひ積極的に利用したい制度と言えるでしょう。
遺言書情報証明書とは?
遺言書情報証明書とは、自筆証書遺言書保管制度によって保管された遺言書の情報を、証明するための書類です。遺言を残した人が亡くなったあと、相続人がその内容を確認するために請求します。
遺言書情報証明書に記されるのは、以下のような情報です。
・遺言者の氏名
・出生年月日
・住所よび本籍
・遺言書の作成年月日
・保管開始日
・遺言書が保管されている保管所の名称
・遺言書の保管番号
・遺言書の画像情報
遺言書情報証明書には、法務局で保管されている遺言書の内容を画像データとして記載されています。証明書を取得すれば、亡くなった人がどのような内容の遺言を残していたのか確認できるでしょう。
遺言書情報証明書は、各種相続手続きを進めるために使います。遺言書と言えば「原本を持って手続きを進める」と思いがちですが、自筆証書遺言書保管制度を活用した場合は異なります。保管制度を利用した場合、遺言書の原本が相続人の手元に返却されることはありません。よって、その後のすべての手続きを遺言書情報証明書で進めていくのです。その効力は遺言書原本と変わりないため、安心してください。
保管制度を活用した場合、自筆証書遺言書であっても、裁判所による検認手続きは必要ありません。相続スタート後に遺言書情報証明書を取得すれば、そのままスムーズに相続手続きを進めていけます。
遺言書情報証明書の取得方法は?
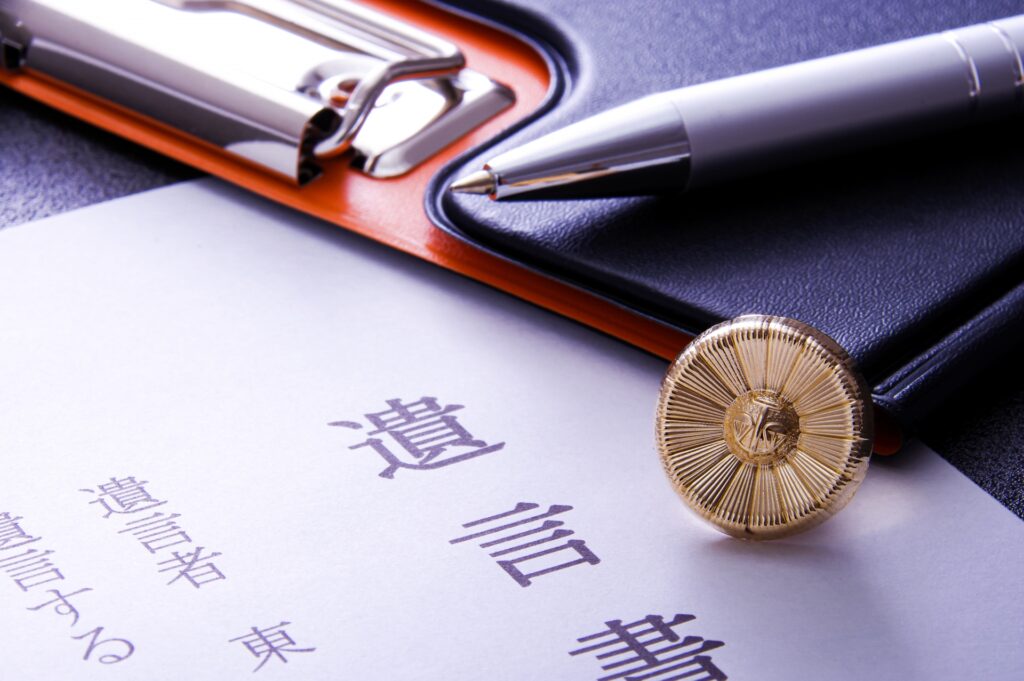
遺言書情報証明書は、取得したい人からの申し出によって交付されます。取得を希望できるのは、以下の条件に当てはまる方々です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
・相続人や受遺者の親権者や成年後見等の法定代理人
遺言者情報証明書は、誰にでも自由に公開されるわけではありません。あくまでも、遺言書の内容に関わる人のみに取得が認められています。取得までの具体的な流れは、以下を参考にしてみてください。
1.交付請求場所を選択する
2.遺言書情報証明書の交付請求書を作成する
3.必要書類を揃える
4.交付請求場所にて予約をとり、交付請求を行う
5.証明書を受け取る
遺言書情報証明書は、遺言書そのものではなく画像データとして交付されます。このため、実際に遺言書が保管されている保管所以外からでも請求が可能。日本全国どこからでも、自分の都合の良い場所から該当データを取得できます。
交付請求書は、最寄りの法務局窓口のほか、ウェブサイトからのダウンロードも可能です。必要事項を記入し、書類を作成してください。交付請求書とともに必要になるのは、以下のような書類です。
・遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
・相続人の戸籍謄本(全員分)
・相続人の3ヶ月以内に発行された住民票(全員分)
このほか、受遺者や遺言執行者が証明書の請求手続きをする場合には、請求する人の住民票が必要です。併せて準備しておきましょう。
遺言書情報証明書の請求手続きは、郵送もしくは直接出向いて行います。遺言書保管所にて手続きする場合、事前予約が必須です。予約がないまま訪れても対応してもらえないため、注意してください。手続きそのものは即日処理されますが、ある程度の時間がかかるもの。できるだけ待ち時間が発生しないよう、事前予約制度が導入されています。予約は専用ホームページもしくは電話、窓口にて行えます。
予約は、請求手続きを行う本人の手で行わなくてはいけません。また予約できる期間は30日先までです。当日予約はできないため、注意してください。
遺言書情報証明書は、相続人それぞれが必要とするケースも多いでしょう。たとえば、共に相続人となっている兄弟姉妹がそれぞれで遺言書情報証明書を必要とする場合、予約はそれぞれでとる必要があります。請求者1人につき1件の予約をするようにしてください。
手続きする際には、請求者の本人確認のため、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書が必要です。発行手数料は、証明書1通につき1,400円。こちらも忘れずに準備しておきましょう。
郵送で手続きする場合、必要書類と返信用封筒をセットにして、遺言書保管所に送付すればOKです。発行手数料は収入印紙で納付してください。
遺言書情報証明書を知り将来のために活用を
遺言書情報証明書は、自筆証書遺言書保管制度と深く関わる書類です。その意味や取得方法をあらかじめ知っておくことで、将来の終活や相続手続きにも役立つでしょう。
自筆証書遺言書保管制度は、遺言書をより確実に残すために有効な制度です。遺言書に関連する知識を深め、ぜひ活用してみてください。









