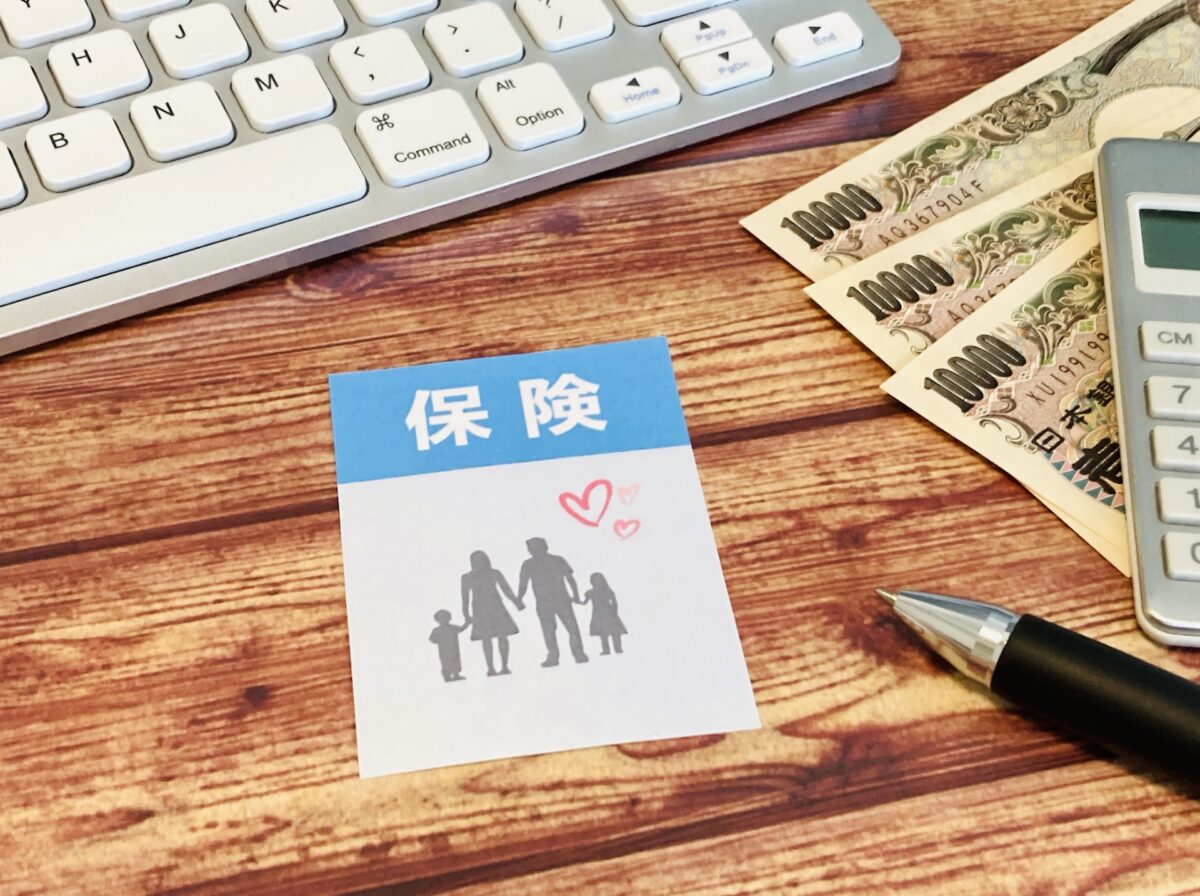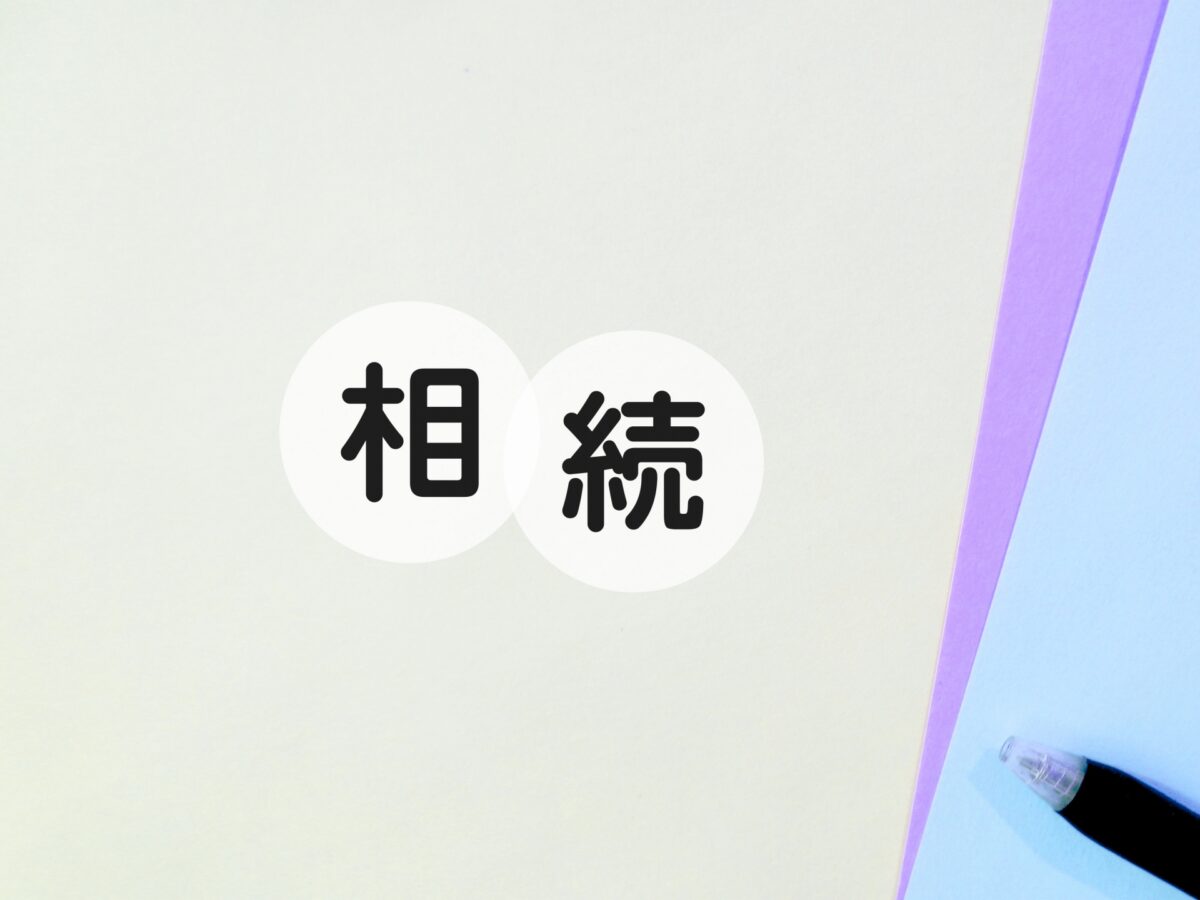いざというときのために加入する生命保険。受取人に指定された人は、被保険者が亡くなった際に保険金を受け取れます。相続対策としても人気の生命保険ですが、さまざまな事情から「受取人がいない」という事態になってしまうケースもあるでしょう。このような場合の対処法や注意点を解説します。
生命保険は受取人を指定しなくても加入できる
生命保険に加入する際には、受取人を指定するケースが一般的です。受取人に指定できるのは、以下のような立場の親族です。
・配偶者
・子ども
・両親
・祖父母
・孫
・兄弟姉妹
このほかにも、内縁関係にあると認められるパートナーや同性パートナーでも、受取人に指定できる可能性があります。具体的な加入条件については、保険会社に問い合わせてみましょう。
とはいえ、生命保険の受取人は「絶対に指定しなければならない」というわけではありません。トラブル予防のために受取人を指定しておくケースが多いものの、受取人を指定しないまま生命保険に加入する方もいます。
この場合、保険会社の規約によって、誰が保険金を受け取るのか決定されます。一般的には、法定相続人に対して保険金を支払うケースが多いようです。
受取人が死亡している場合はどうなる?
生命保険の受取人がいないパターンとして、もう一つ考えられるのが「被保険者よりも受取人の方が先に亡くなってしまった場合」です。受取人が死亡した場合、契約者や被保険者は、事前に受取人の変更手続きをする必要があります。「受取人に指定していたのを忘れていた」「バタバタしていてそんな余裕がなかった」といった事情で変更しないまま放置すると、いざ生命保険金が支払われる際に、「受取人がいない」といった事態に陥ってしまうでしょう。
この場合、保険金を受け取るのは、「受取人の法定相続人」です。生命保険金を受け取る権利は、あくまでも「受取人」のもので、受取人がすでに死亡していた場合でもその権利は相続人へと受け継がれていきます。これは保険法で定められたルールです。法定相続人は、「全員」が対象になります。
たとえば、夫を被保険者とする生命保険で妻が受取人に指定していた場合を考えてみましょう。夫より先に妻が亡くなり、そのまま受取人変更手続きを取らなかった場合、夫の生命保険金を受け取るのは、妻の法定相続人です。夫婦の間に子どもがいれば、子ども全員が受取人に。自分と血縁関係がなくても、妻の子どもであれば生命保険金を受け取る権利を有するのです。
夫婦の間に子どもがいなかった場合、さらに話は複雑になります。子どもの次に法定相続人になるのは、妻の両親です。両親もすでに亡くなっている場合、妻の兄弟姉妹が夫の生命保険金の受取人です。
被保険者である夫の立場としては、「妻が亡くなっているのであれば、自分の親や兄弟姉妹にお金を残したい」と考えるケースもあるでしょう。このような場合でも、自身の希望を叶えるのは難しくなってしまいます。仮に夫の親族が生命保険金を受け取る権利を主張したとしても、認められません。
ただし、受取人が先に死亡している場合の受取人規定には、例外もあります。「保険金は受取人の法定相続人へ」というルールは、保険法で定められたもの。任意規定であるため、生命保険契約によっては別のルールが適用されている可能性も。実際に誰が受取人になるのか、保険会社に確認しつつ手続きを進めていくのがおすすめです。
法定相続人がいない場合の生命保険金は?

続いては、「被保険者が亡くなった際に、すでに受取人が死亡していて法定相続人もいない」というケースについて考えてみましょう。子どもがいない高齢者で、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合などが当てはまります。この場合、生命保険金は誰が受け取るのでしょうか。
生命保険金はその他の財産とあわせて、裁判所から選定された相続財産管理人が管理します。すべての財産を整理した上で、国庫に帰属。つまり「個人のお金ではなく、国のお金として扱われる」ということになります。
トラブルを避けるための方法は?
生命保険において、受取人に関するトラブルは決して少なくありません。回避するためには、どういったポイントに注意すれば良いのでしょうか。3つの項目を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
★1.生命保険加入時に「約款」を確認する
生命保険金の受取人が誰になるのかは、「約款」を見ればわかります。受取人がいない場合の規定についても、あらかじめ確認しておきましょう。
被保険者よりも受取人の方が先に亡くなっている場合、保険法の規定が適用されるのかどうかは、保険によって異なります。事前に確認した上で契約を結べば、「いざというときに、自分の思いとは異なるところにお金が渡ってしまった…」といった事態も防げるのではないでしょうか。
分厚い約款をすべて確認するのは大変…と思いがちですが、目次に沿って目当ての情報を見つけられます。最近ではウェブ上で約款の内容を確認できる保険会社も増えていますから、しっかりと確認し内容を把握した上で、契約を結ぶようにしてください。
★2.生命保険加入時に「受取人」について真剣に考える
生命保険は、相続を考える上でもメリットがあります。受取人を事前に指定しておけば、確実にお金を残してあげられるでしょう。相続税の計算においても、非課税枠が用意されています。
こうしたメリットを最大限に活用するためには、保険契約時から受取人についてしっかりと考えておく必要があります。
・誰を受取人にするのか?
・受取人が先に死亡してしまった場合に誰が受け取るのか?
これらの点について、考えた上で保険契約を結ぶのがおすすめです。
さまざまな事情から、「保険契約時に受取人を指定できない」というケースもあるでしょう。この場合でも、どういったデメリットが考えられるのか把握しておくだけでも、トラブルが発生する可能性を低くできます。
★3.受取人が死亡した際に変更手続きを忘れない
生命保険契約を結んだあとは、受取人に関する情報を、適宜確認するのがおすすめです。身近な人が亡くなった際には、その人を受取人に指定している保険契約がないかどうか、確認してみてください。必要に応じて、変更手続きをしておきましょう。
受取人が死亡したとき以外でも、状況が変わるケースはあるでしょう。そのほかの相続財産とともに、定期的にチェックするのがおすすめです。
生命保険の受取人について知識を身につけて対応を

少子高齢化の今、さまざまな事情から「生命保険の受取人がいない!」といったトラブルに巻き込まれる方も少なくありません。事前に受取人を指定し、定期的にチェックするだけで、トラブルを回避できる可能性が高まるでしょう。保険契約について不安がある方、またこれから契約する上で受取人を誰にするのか悩んでいる方は、ファイナンシャルプランナーや相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。