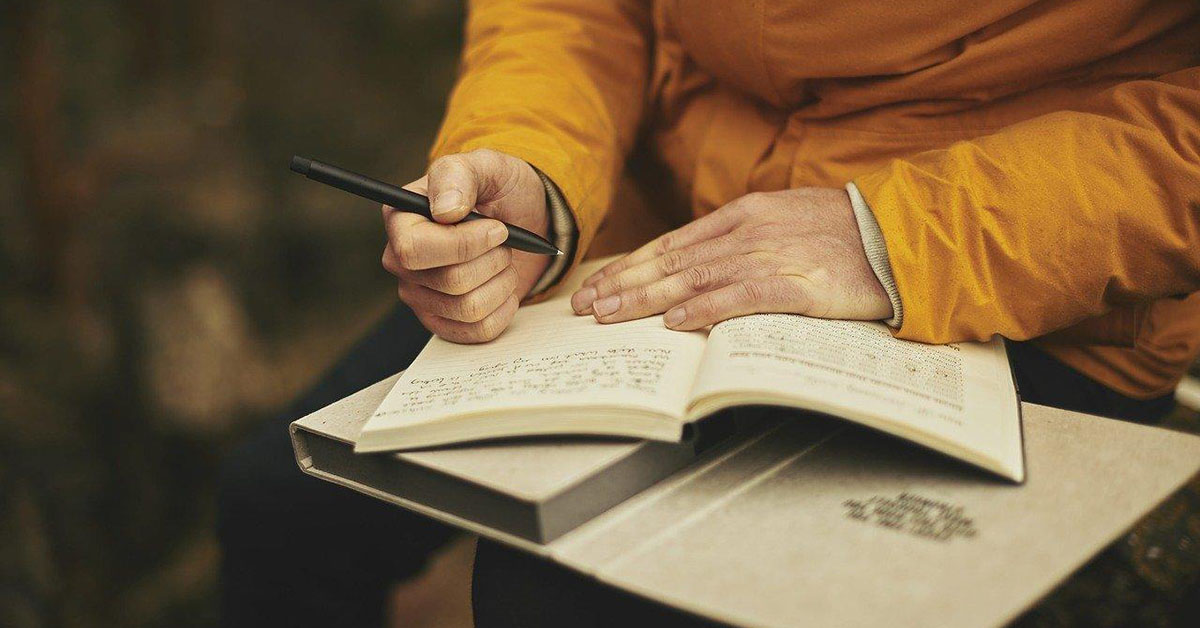終活と言えば、「遺言」をイメージする方も多いのではないでしょうか?遺言書があれば、自分が亡くなったあと、最期の意思を示せるでしょう。相続に関するトラブルを減らす効果も期待できるかもしれません。
とはいえ実際には、ほんの少しのミスが原因で、遺言そのものが無効になってしまうケースも多く見られます。せっかくの遺言書を無効にしないための、基本ルールを解説します。
そもそも「遺言」とは?
遺言とは、被相続人による意思の表明です。相続とは、被相続人が亡くなった瞬間からスタートするもの。その性質上、自身の財産の相続について、被相続人が直接口を出せる機会はありません。だからこそ重要視されているのが、亡くなる前に自身の意思を明らかにしておくための「遺言」なのです。
遺言を残しておけば、被相続人の意思を相続に反映させられます。また、被相続人の思いが明らかになることで、相続に関連した親族間トラブルを避けられる可能性もあるでしょう。遺言を残しておくメリットは、非常に大きいと考えられます。
遺言には、以下の3つの形式が用意されています。終活準備として「遺言を残したい」と思ったら、まずは自分にとって、どの形式を選ぶのがベストなのか検討してみましょう。
★自筆証書遺言
被相続人が自分自身の手で内容を記し、署名・押印の上、個人で管理する遺言を、自筆証書遺言と言います。以前は遺言書のすべてを自身の手で記載する必要がありましたが、平成30年に民法が改正。財産目録はパソコンでの作成が可能になり、また法務局で遺言書を保管できる制度もスタートしています。
自筆証書遺言の場合、いつでも好きなときに遺言書を作成できます。基本的には自分の手元で保管することになるため、書き換えも容易です。終活準備に人気のスタイルと言えるでしょう。ただし、遺言書作成の手順をすべて自分でこなすため、ミスも多くなりがちです。
★公正証書遺言
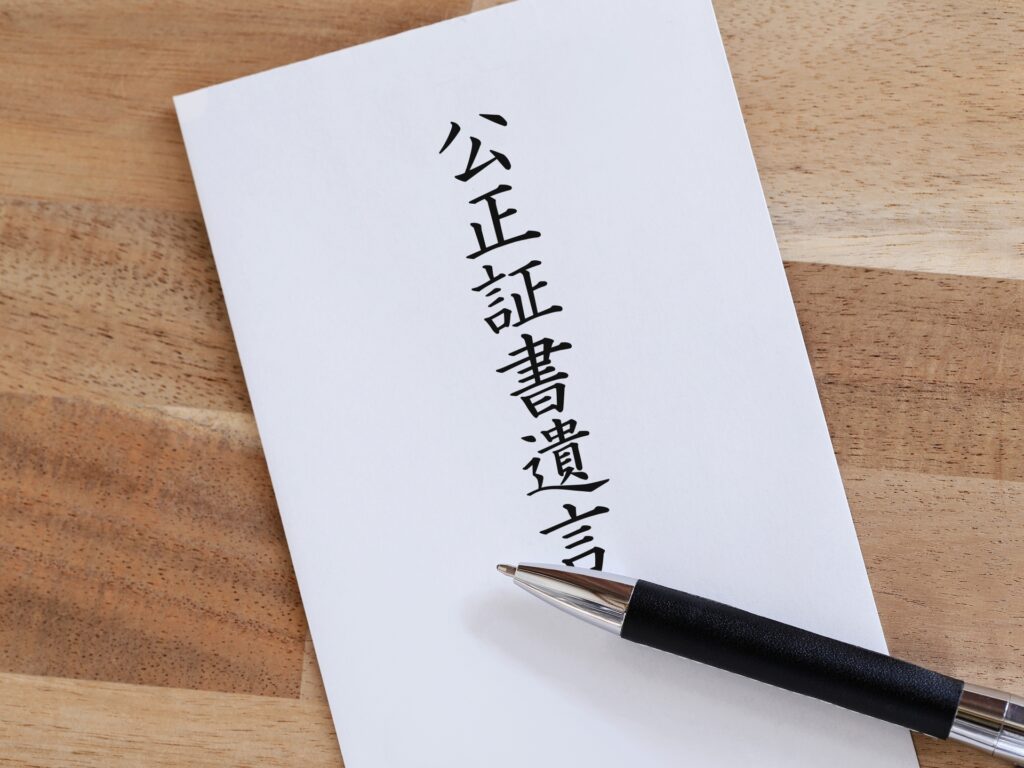
公正証書遺言は、被相続人の言葉をもとに、公証人が作成する遺言スタイルを指します。公証役場にて、2名以上の証人が立ち会い、遺言書を作成。手間も手数料もかかりますが、公証人が遺言書を作成するため、ミスが発生しにくいという特徴があります。
★秘密証書遺言
遺言内容を自分自身で記し、内容を秘密にしたまま、公証人役場でその存在を証明してもらうスタイルを、秘密証書遺言と言います。こちらの方法なら、遺言の本文はパソコン等で作成可能。また、公証人に内容を知られることなく、遺言書の存在を明らかにできます。
秘密証書遺言の場合も、遺言書の作成は自分自身で行うことに。ミスをしないよう、入念にチェックする必要があるでしょう。
自筆証書遺言の基本ルール
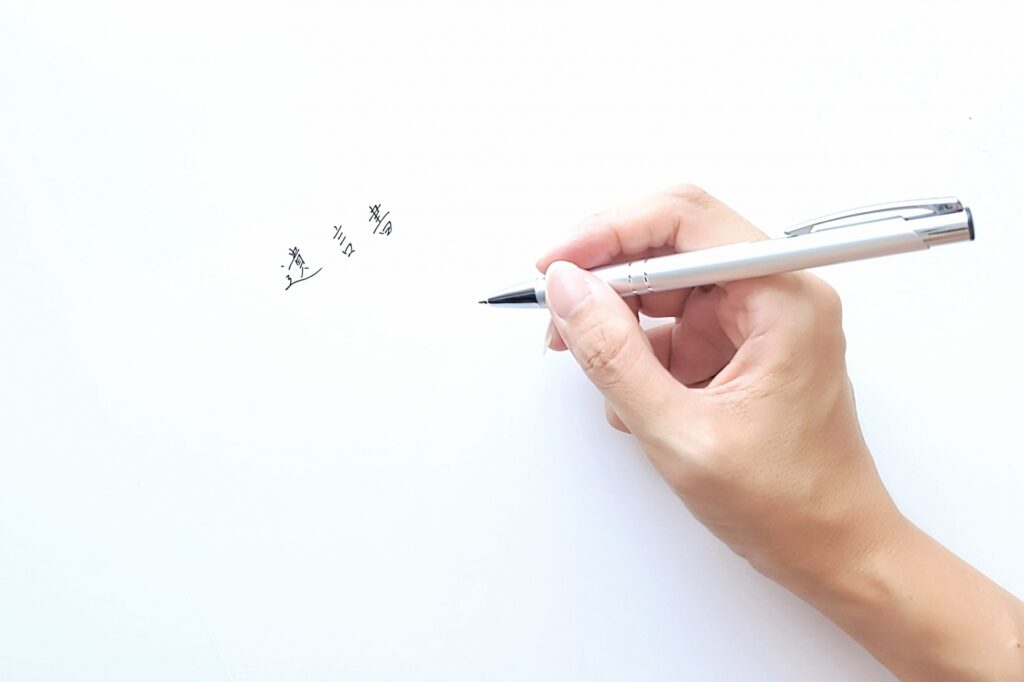
ここからは、終活ブームと共に人気が高まっている、自筆証書遺言について紹介していきます。まずは、遺言を残すための基本ルールを確認していきましょう。
★フォーマットに厳密な規定はなし
自筆証書遺言を作成する際に、「まずどう書けば良いのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。自筆証書遺言に、決まったフォーマットは存在しません。必要事項が漏れなく含まれていれば、様式やペンの種類、大きさなどは好みで選んで大丈夫です。
決まったフォーマットは存在しませんが、自筆証書遺言に記すべき内容には、一定のルールがあります。
・誰に何を、どのくらい相続させるのか?
・誰に相続させたくないのか?
・遺言執行人は誰にするのか?
・内縁関係にあるパートナーや隠し子について
遺言の本文には、これらの項目をわかりやすく記しておきましょう。
★自筆による作成が基本
自筆証書遺言は、署名や日付から本文に至るまで、すべてを自筆で記す必要があります。自筆による作成が不可能な場合は、その他の遺言スタイルに注目してみてください。誰かに代筆してもらったり、パソコンで作成したりした遺言は無効です。
★日付・署名・押印を忘れずに
遺言本文を記載したあとには、遺言を残した日付と自筆署名、そして押印を忘れないでください。一つでも欠けていると、遺言が無効になってしまいます。自筆でのサインは、本名以外に芸名やペンネームも認められています。「本人とわかること」がもっとも重要なポイントです。
★財産目録は漏れなく準備を
遺言書とセットで作成しなければならないのが、自身が所有する財産を一覧で示した財産目録です。自筆証書遺言の場合でも、財産目録だけはパソコンでの作成が可能。ただしその場合、すべてのページに自筆署名と押印が必要です。
★加除訂正はルールを守って
いつでも好きなタイミングで、遺言の内容を変えられるのが自筆証書遺言のメリットです。ただし、遺言書に加筆や訂正をする場合、ルールを守って正しく行う必要があります。加除訂正のルールの例は以下のとおりです。
・間違った部分を二重線で消す
・正しい言葉は「吹き出し」を使って加筆する
・余白部分に削除した文字数、加入した文字数を明らかにし、署名押印する
ルールを守らずに加除訂正された遺言書は、その部分のみならず、全面が無効と判断されてしまいます。十分に注意してください。
より確実に遺言を残したいなら
手軽さで人気の自筆証書遺言ですが、実際には非常に細かいルールが設定されています。法律上有効な遺言書を残すことは、決して簡単ではありません。だからこそ、より確実に遺言を残したいなら、公正証書遺言を検討するのがおすすめです。
遺言を残す際に手間は発生するものの、法律のプロが作成する遺言なら安心です。ささいなミスがきっかけで無効になってしまったり、勘違いから望まない内容の遺言を残してしまったりするような、遺言リスクを避けられるでしょう。
弁護士事務所の中には、遺言書作成をサポートしてくれるところも少なくありません。遺言書を作成する前の段階から相談することで、
・そもそも自分にはどの遺言タイプが合っているのか?
・どのような内容にすれば、自分の理想を実現できるのか?
これらの点についても、専門家目線で具体的なアドバイスをもらえるでしょう。より確実に、自身の意思を反映した遺言を残すためにも、ぜひ活用してみてください。
自筆証書遺言なら保管制度も活用を
自筆証書遺言にこだわりたい場合、法務局が提供する保管制度も活用してみてください。これは、自宅で記した遺言書を、法務局内で適正に保管・管理してもらえる制度です。
遺言書を預ける際には、法律的な要件を満たしているかどうかのチェックが受けられます。遺言内容に関するアドバイスではありませんが、細かなミスが原因で、遺言書そのものが法的に無効と判断されるようなリスクは避けられるでしょう。
こちらの制度を使えば、遺言書の紛失や改ざんといったトラブルは回避できます。また相続開始後の検認が不要で、相続手続きを素早く行えるというメリットもあります。
遺言の準備は基本ルールを学ぶところからスタートしよう
正しい形で遺言を残すためには、まず遺言そのものについて、知識を深めなければいけません。終活準備の一つとして、ぜひ遺言ルールについても積極的に学んでみてください。
終活ブックなどでは、気軽に残せる自筆証書遺言をおすすめされるケースも多いもの。基本のルールを身につけ、ときには専門家のアドバイスも活用しましょう。時間をかけて何度もメンテナンスしていくことで、より自分の理想の遺言に近づけていけるのではないでしょうか?