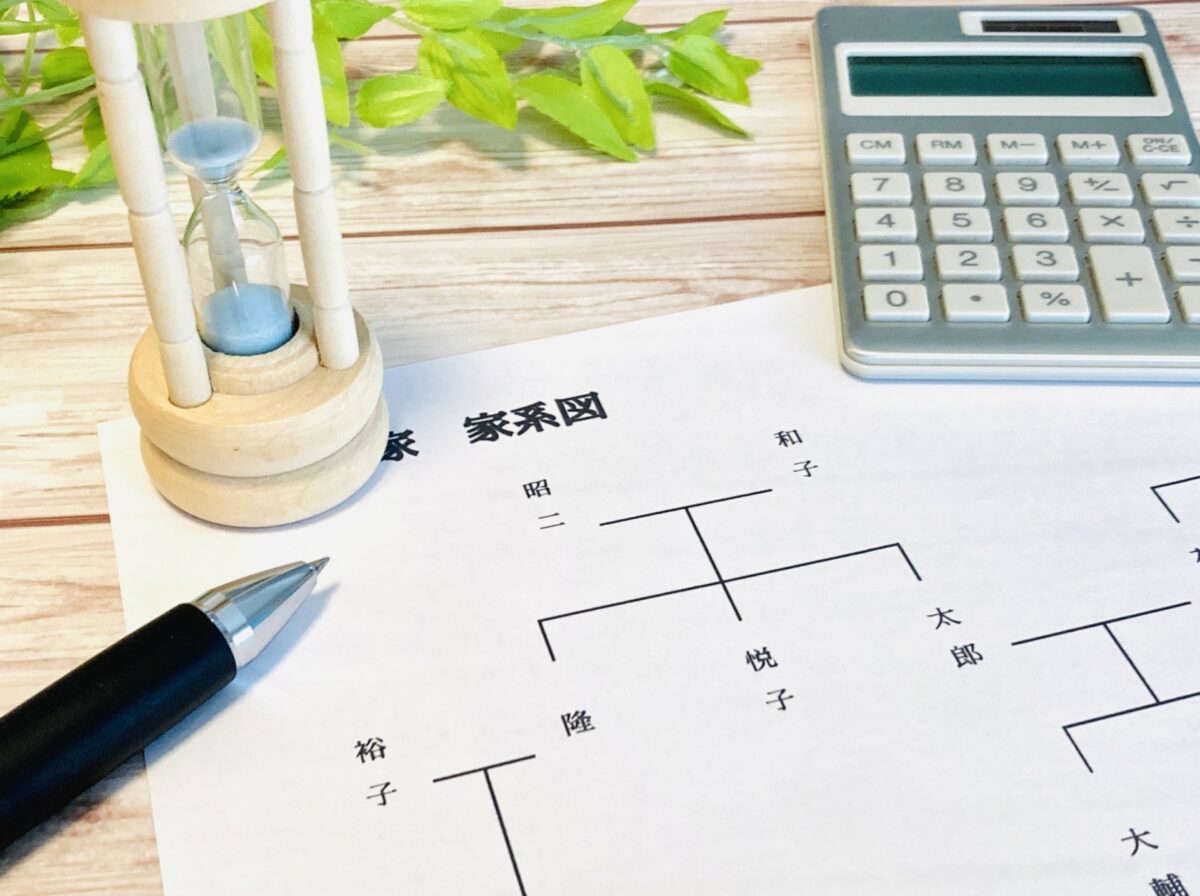身近な人が亡くなった際には、さまざまな手続きが必要になります。相続について考えるとともに、厚生年金手続きも忘れないようにしましょう。具体的にどのような手続きが必要になるのか、わかりやすく解説します。慌てず確実に、一つ一つの手続きを終えてください。
年金受給者が亡くなった場合の手続きとは?
厚生年金を始めとする年金受給者が亡くなった場合、年金を受給する権利はなくなります。年金を受け取る権利は亡くなった人個人のもの。「配偶者だから」「子どもだから」という理由で、その権利が相続されることはありません。年金事務所に対して「受給権者死亡届」を提出して、現在受給している年金をストップしましょう。
何かとバタバタしている時期ですが、手続きを忘れたまま放置すると、年金の受給は続いてしまいます。自分ではそんなつもりはなくても、不正受給と判断される可能性もあるのです。
受給権者死亡届の提出期限は、以下のように定められています。
・国民年金 14日以内
・厚生年金 10日以内
あまり時間的な余裕はありませんから、忘れずに手続きするようにしてください。
ちなみに、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合、わざわざ受給権者死亡届を提出する必要はありません。手続きの負担を一つでも減らすため、事前に登録しておくのもおすすめです。
未支給年金とは?受給方法も解説
受給者死亡により年金をストップする際に、忘れてはいけないのが未支給年金です。
毎月支給される年金ですが、支給日は2ヶ月に1回、偶数月と定められています。たとえば2月に亡くなった方は、2月分までの年金を受け取る権利を有しています。しかし年金は後払いであり、その2月分が支給されるのは4月になってからなのです。この「受給者が生きている間に支給されたものの、まだ受け取っていない年金」のことを、未支給年金と言います。
未支給年金は、遺族が請求することで初めて支給されます。厚生年金や国民年金をストップさせるための手続きとともに、未支給年金の請求手続きについても忘れないようにしましょう。
未支給年金を請求できるのは、以下のような立場の方々です。
・生活をともにしていた配偶者
・生活をともにしていた子ども
・生活をともにしていた父母
・生活をともにしていた孫
・生活をともにしていた祖父母
・生活をともにしていた兄弟姉妹
・生活をともにしていた、その他の三親等内の親族
未支給年金は、誰でも自由に請求できるわけではありません。上から順位が定められており、もっとも高い人が請求できる仕組みです。配偶者がいれば配偶者がもっとも優先されますし、配偶者がいなければ子ども、子どももいなければ父母…というように、該当者がいない場合に下順位へと繰り下がっていきます。ただし立場としては「配偶者」でも、生計をともにしていなければ、未支給年金は請求できません。
未支給年金を請求するための書類は、死亡届とセットになっています。死亡届を提出する場合、忘れることはないでしょう。亡くなった人の年金証書や住民票除票、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど、必要書類とセットで提出してください。
未支給年金の請求は、5年以内に行わないと時効を迎えてしまいます。できるだけ早く、手続きを済ませておきましょう。
遺族厚生年金や遺族基礎年金を受け取れる可能性も
生活をともにしていた人が亡くなってしまった場合、収入面で不安定になってしまうこともあるでしょう。こうした人々の生活を支えるために、用意されているのが遺族厚生年金や遺族基礎年金といった制度です。こちらは、「生前に本人が受け取るお金」ではなく、「保険者が亡くなったあとに遺族が受け取るお金」です。
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人が亡くなった場合に受け取れる可能性のある遺族年金です。亡くなった人によって生活を支えられていた人の中で、もっとも優先順位の高い人が受給できます。具体的な順位は、以下のとおりです。
第1位 配偶者もしくは子ども
第2位 両親
第3位 孫
第4位 祖父母
年金事務所に必要書類を提出すれば、亡くなった人の老齢厚生年金額の4分の3を受給できるでしょう。
遺族基礎年金は、生前に国民年金に加入していた方向けの遺族年金制度です。年金を受け取れる可能性があるのは、子どもを持つ配偶者もしくは子どもです。ここで言う「子ども」とは、「18歳に到達する年度の末日(3月31日)を経過していない、もしくは障害年金の障害等級が1級か2級の20歳未満の人」のこと。遺族厚生年金よりも、受給できる人の範囲が狭い点に注意しましょう。
このほかにも、被保険者が亡くなった場合には、寡婦年金や死亡一時金といったお金を受け取れる可能性があります。「被保険者が亡くなった=年金制度の恩恵を受けられない」と決まったわけではありません。どのような制度を利用できる可能性があるのか、年金事務所に問い合わせ、必要な手続きを進めてみてください。
相続放棄した場合の遺族厚生年金はどうなる?
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に、検討したいのが相続放棄の手続きです。相続放棄すれば、相続権を失うため、すべての財産を受け継ぐことができなくなります。この際の、「遺族厚生年金も受け取れなくなってしまうのでは…」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
たとえ相続放棄の手続きをとっても、遺族厚生年金を受給する権利は失いません。これは、遺族厚生年金の受給権は、民法上で言う相続財産に当てはまらないからです。ちなみに、未支給年金も相続財産には当たらないため、相続放棄しても受け取れます。
被相続人が負債を多く残して亡くなったとしても、相続放棄すればその負担が回ってくることはありません。遺族厚生年金の受給権があれば、負債を手放した上で、安定した収入を得られるのではないでしょうか。
相続放棄については専門家に相談しつつ、確実に手続きを進めていくのがおすすめです。
相続発生後も慌てずに厚生年金手続きを
相続発生後に、厚生年金関連でやるべき手続きは、決して少なくありません。不正受給にならないため、また自分に権利のある年金をしっかりと受け取るためにも、手続きを忘れないようにしましょう。
厚生年金や国民年金の手続きで悩んだ際には、年金事務所に行くとアドバイスしてもらえます。必要書類を用意してもらえるほか、今後どのように手続きを進めていくべきか、アドバイスしてもらえるでしょう。手続き漏れで損をするリスクもなくなるはずです。専門家のサポートも上手に取り入れつつ、必要な手続きを進めてみてください。