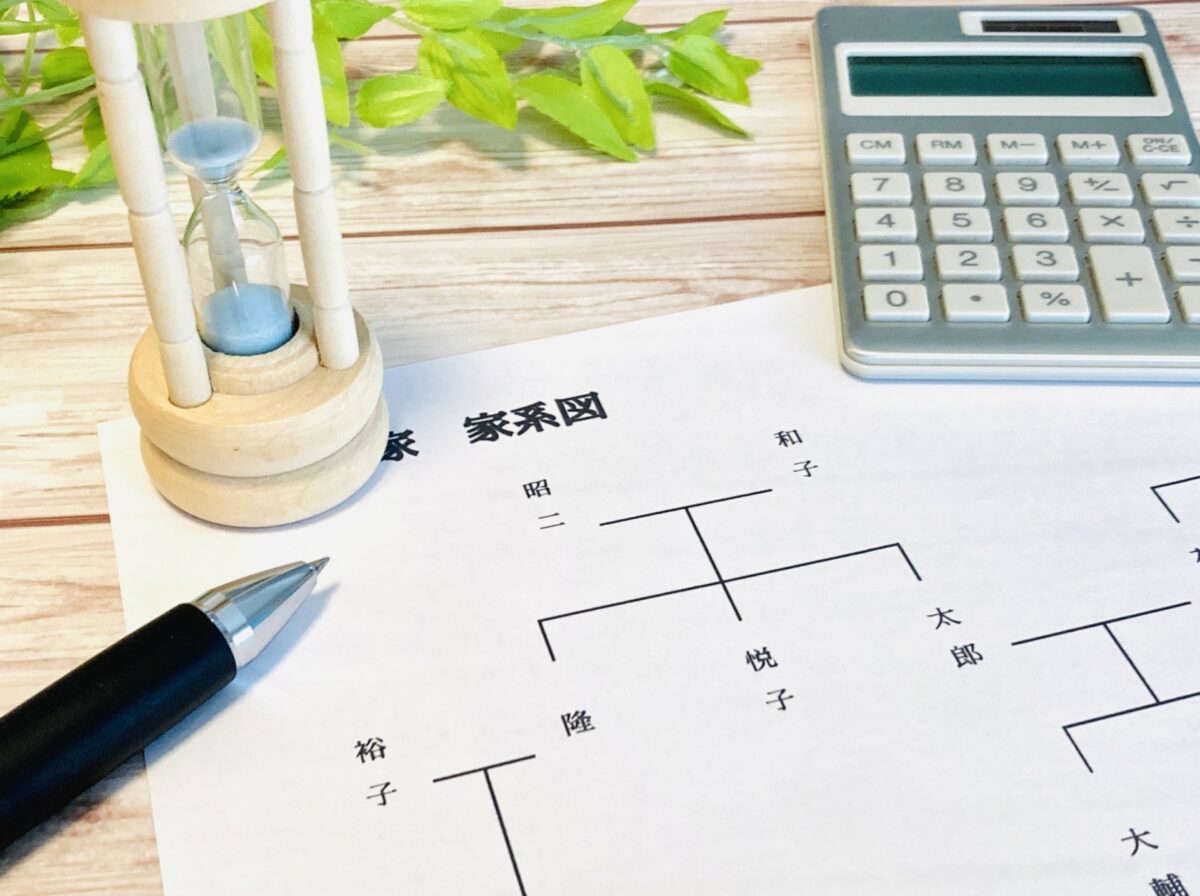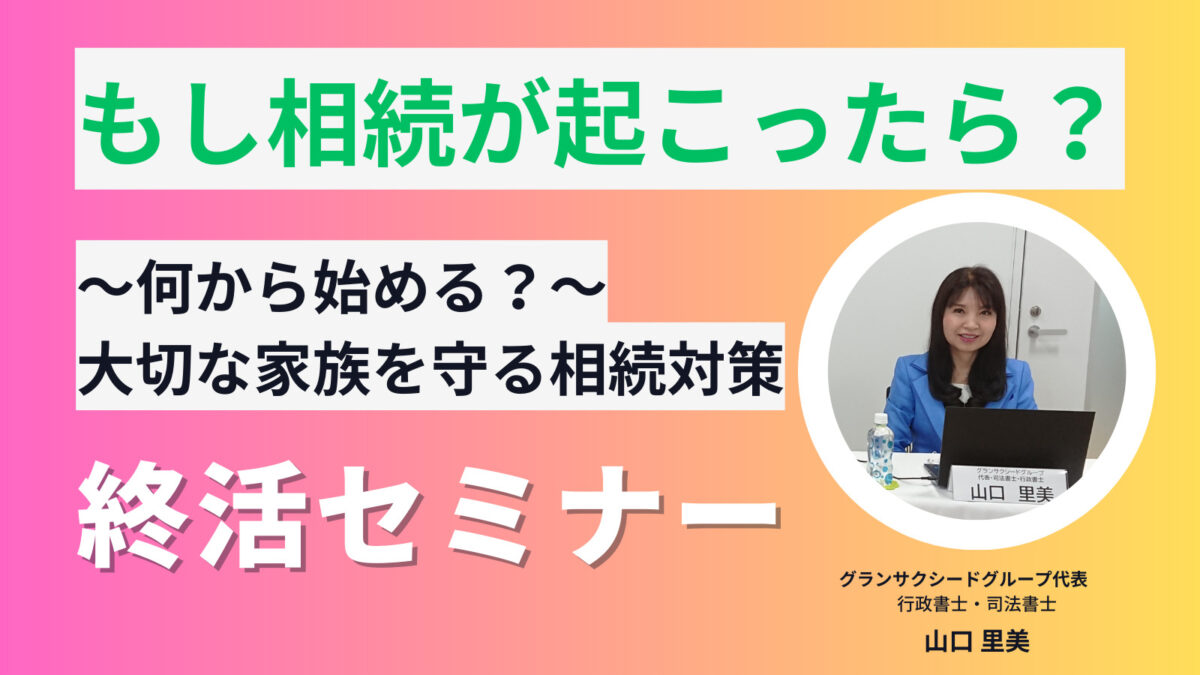配偶者が亡くなったとき、深い悲しみに沈んでしまう方も多いことでしょう。とはいえ、相続手続きは待ってはくれません。愛する配偶者が残してくれた財産と今後の自分の生活を守るためにも、「配偶者の立場での相続」について、基本的な知識を身につけておきましょう。
法定相続のポイントや相続税の配偶者控除、各種注意点について順番に解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
配偶者は法律上、無条件で法定相続人に!
相続とは、被相続人から相続人へと、財産が受け継がれることを意味しています。ここで大きな問題になるのが、「ではいったい誰が法定相続人になるのか?」という点。亡くなった人に「法律上の婚姻関係がある配偶者」がいれば、その配偶者は必ず法定相続人になります。
ここで重要なのは、「法律上の婚姻関係がある」という部分です。長年連れ添ったパートナーであっても、事実婚や内縁関係の場合、配偶者としての相続権が無条件で認められるわけではありません。まずはこのあたりを、しっかりと確認しておきましょう。
またもう一点注意しなければならないのが、「配偶者以外の法定相続人」についてです。配偶者以外にも法定相続人がいれば、当然遺産を分け合うことに。配偶者の立場であっても、被相続人の財産をすべて受け継ぐことはできないのです。
配偶者以外の法定相続人は、
・第1順位 → 被相続人の実の子ども
・第2順位 → 被相続人の父母
・第3順位 → 被相続人の兄弟姉妹
と定められており、順位に沿って決定されます。亡くなった方に子どもがいれば、配偶者と子どもが法定相続人です。子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの子や孫へと相続権が受け継がれていきます。
注意しなければならないのは、亡くなった方に子どもがいないケースです。第1順位不在の場合、第2順位の両親、第3順位の兄弟姉妹と法定相続人の範囲は広くなっていきます。
もし第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になり、さらにその本人がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹の子ども、つまり被相続人にとっての甥や姪が財産を受け継ぐ可能性も。配偶者の立場では、こちらも頭に入れた上で、事前にしっかりと対策を取っておくことをおすすめします。
相続税における配偶者控除とは?
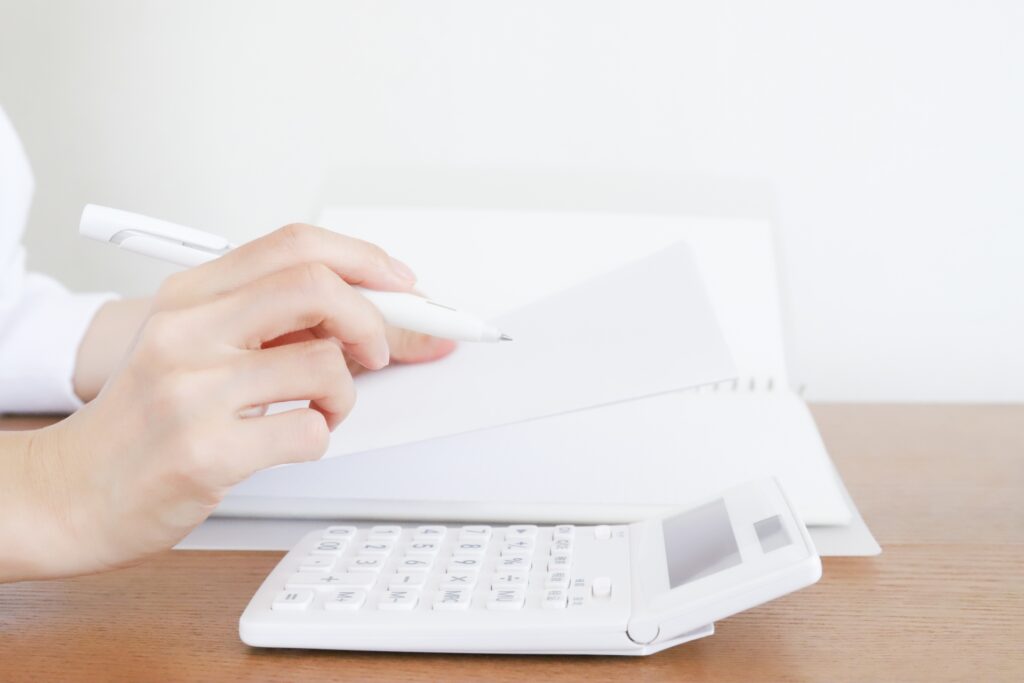
配偶者は、「亡くなった人と協力して財産を築き上げた人」であるため、他の法定相続人よりも多くの財産を受け取れるように設定されています。とはいえ、受け継ぐ財産が増えれば増えるほど、気になるのが相続税について。こうした不安を解消するために、相続税においては配偶者のみが利用できる控除制度が用意されています。
相続税における配偶者控除は、
・相続する財産が1億6,000万円までであれば非課税
・相続する財産が配偶者の法定相続範囲内であれば非課税
という2つのルールが定められています。遺産分割協議の結果、配偶者の立場で受け取る財産が1億6,000万円までであれば、配偶者の相続分に対して相続税が課せられることはありません。またたとえ1億6,000万円以上であったとしても、以下の法定相続範囲内に収まっていれば、やはり相続税を納める必要はないのです。
・配偶者と子どもが法定相続人になる場合 → 配偶者の法定相続分は遺産の2分の1
・配偶者と被相続人の親が法定相続人になる場合 → 配偶者の法定相続分は遺産の3分の2
・配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる場合 → 配偶者の法定相続分は遺産の4分の3
10億円の財産を配偶者と子どもが受け継ぐ場合でも、配偶者の取り分が5億円までであれば、配偶者分の相続税は発生しません。また、もし法定相続人が配偶者のみの場合、遺産のすべてが配偶者の法定相続分となります。たとえ遺産が100億円あり、そのすべてを受け継いだとしても、配偶者に相続税は課せられないのです。
ただし、先ほどの「10億円の財産を配偶者と子どもが受け継ぐ」ケースで、相続税が控除されるのは配偶者のみです。子どもが受け継ぐ分については、基礎控除額を除き、相続税が課せられるため注意してください。
配偶者の相続で知っておくべき3つの注意点
配偶者の立場で財産を相続する際には、以下の3つの点に注意しましょう。
★1.相続税の申告を忘れない
配偶者の立場で多額の財産を受け継ぐ場合、よほどのケースでなければ、相続税は0円で済む方がほとんどでしょう。ここで注意が必要なのは、「相続税が0円とわかっていても、相続税の申告はしなければならない」という点です。
相続税の配偶者控除は、自動で適用されるわけではありません。「相続の状況を正直に申告した結果、配偶者控除が認められるため0円になる」という仕組みです。申告は、被相続人が居住していた地域を管轄している税務署にて行います。申告書や遺産分割協議書など、必要書類をそろえた上で手続きしましょう。
★2.手続きの期限を守る
相続税の申告には、「相続の発生を知った日の翌日から10か月以内」という期限が設定されています。この間に遺産分割協議を完了させ、必要書類をそろえた上で手続きする必要があるのです。
配偶者が亡くなってすぐのタイミングで、遺産相続について考えるのは難しいかもしれません。しかし後回しにしていると、手続き期限を過ぎ、配偶者控除を受けられなくなってしまうリスクもあります。残念ながら、遺産分割協議が常にスムーズに進むとは限らないでしょう。早め早めを意識して行動することをおすすめします。
★3.二次相続のリスクも考慮しよう
配偶者の立場で財産を相続する際に、便利に使える配偶者控除。配偶者の立場としては非常に心強い制度ですが、二次相続のリスクについても、あらかじめ知っておきましょう。
二次相続とは、財産を受け継いだ配偶者が亡くなった際に発生する相続のこと。一次相続で多額の財産を受け継いだ配偶者が亡くなった場合、またその財産は、次の相続人へと受け継がれていきます。一時相続で「配偶者と子ども」が相続人になった場合、二次相続でも「子ども」が相続人になる可能性は高いでしょう。二次相続では、当然配偶者控除は適用されません。一次相続で配偶者が受け継いだ財産の額が大きければ大きいほど、二次相続における子どもの負担は上昇してしまうでしょう。
二次相続に関するリスクは非常に複雑で、一次相続の段階からしっかりと準備を整える必要があります。相続や税金のプロにサポートしてもらうのがおすすめです。
不安な点は専門家に相談するのがベスト
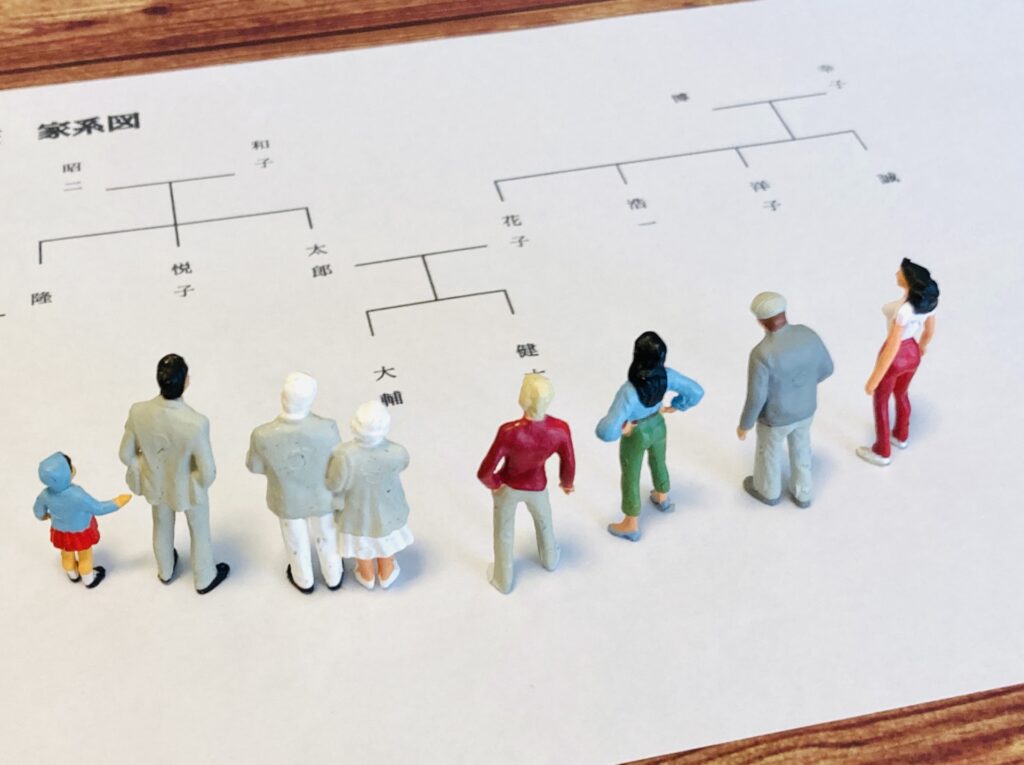
配偶者の立場で、相続に関する不安を抱えている方は決して少なくありません。できるだけ早く専門家に相談し、アドバイスをもらうのがおすすめです。また「配偶者にすべての財産を残したい」といった希望がある場合、相続が発生する前の段階から準備を進める必要があるでしょう。ぜひ終活の一つとして、将来発生するであろう「相続」にも、目を向けてみてくださいね。