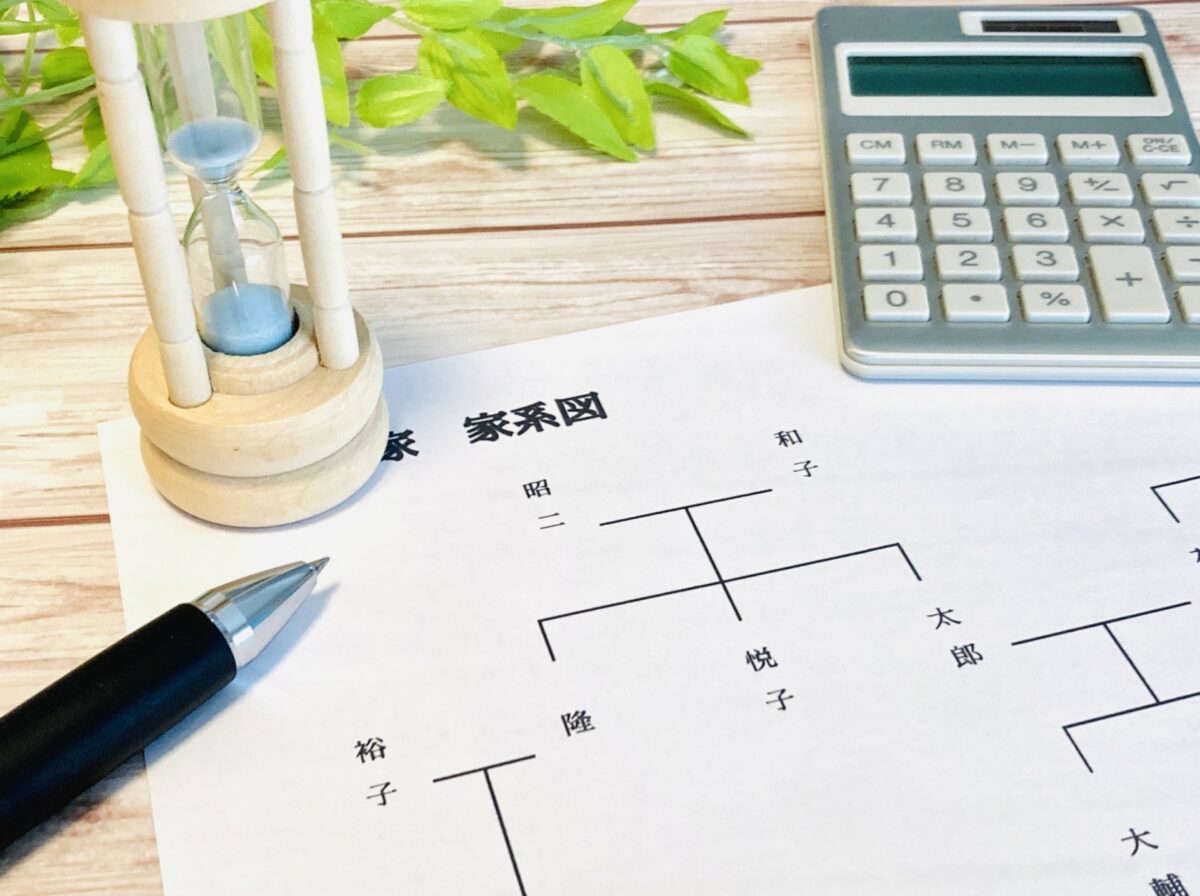身近な人が亡くなった際に、トラブルになりやすいのが「被相続人名義の預貯金の引き出し」についてです。預貯金や遺産として扱われるため、取り扱いには注意しましょう。「遺産として残された預貯金は引き出せない」と言われていますが、実際のところはどうなのでしょうか。対処法や必要な手続きについて詳しく解説します。
預貯金が引き出せなくなるのは口座が凍結されるから
亡くなった人の口座からお金が引き出せなくなるのは、該当の口座が凍結されるからです。これは、銀行側が相続トラブルを避けるために行っている措置。特定の相続人だけが遺産を独り占めしないよう、「銀行側が死亡を確認した時点で口座を凍結する」と定められています。
銀行側が口座名義人の死亡を知るきっかけはさまざまです。
・家族からの連絡
・新聞に掲載されるお悔やみ欄
・担当する行員からの連絡
「死亡届を提出すると自動的に銀行に連絡がいく」というのは誤解です。また、名義人死亡に伴う口座の凍結について、銀行側が相続人に対して通知することはありません。「気づいたときにはすでに凍結されていた…」という事態も、決して少なくないでしょう。いつ口座が凍結されてしまうかわからないからこそ、亡くなる瞬間が近づいてきたら、ある程度の準備を整えておく必要があります。
凍結されない場合も預金の取り扱いには注意が必要
相続人が口座名義人の死亡を知らせず、銀行側もその情報を得ていない場合、口座は凍結されません。ATMとキャッシュカード、暗証番号さえあれば、生前と同じように預金を引き出せるでしょう。
葬儀代やその他の出費に対応するため、亡くなった人の口座からお金を引き出すケースは決して少なくありません。それ自体が、何らかの罪に問われるわけではないでしょう。
ただし、安易な出金が、後々の相続トラブルに発展しやすいのも事実です。亡くなった人の預貯金は遺産の一部。特定の相続人が、よくわからない目的で多額の現金を引き出していたら、「預金を独り占めしようとしている」と思われても仕方がないでしょう。トラブルを避けるためには、細心の注意を払って行動する必要があります。
病院代の清算や葬儀で必要なお金を捻出する目的であれば、何にいくら必要だったのか、わかるようにして管理してください。請求書や領収書、必要なメモ書きとともに保管すれば、その他の相続人も納得しやすくなるでしょう。その他の目的で預貯金を引き出したい場合、相続分に留まる範囲で行動しましょう。「自身の取り分から先払いで受け取った」と説明し、相続手続きを進めていけば、問題が起きる可能性は低くなります。
自分一人で隠しておくのではなく、その他の相続人に対して、「どのような目的でいくら出金するのか」を明らかにしておくのもおすすめです。お金の流れをできるだけ明らかにしておくことで、生前の口座管理やその他の出金について、余計な誤解を防ぐ効果が期待できます。
口座が凍結された場合の対処法は?
銀行側が名義人死亡の事実を把握し、口座が凍結された場合、各金融機関にて相続手続きを進めていく必要があります。必要な手順さえ踏めば、凍結は解除され、口座解約とともに預貯金が引き出されます。金融機関から必要な書類の説明を受け、準備したのちに郵送しましょう。
被相続人が遺言書を残していれば、その内容をもとに相続手続きを進めていきます。遺言書の原本や謄本が必要になるので準備してください。残された遺言が自筆証書遺言であった場合、家庭裁判所の検認済証明書も必要に。手続き完了までには少し時間がかかるため、できるだけ早く動き出すのがおすすめです。
遺言書がなかった場合、相続人同士の話し合いで遺産分割協議書を作成するケースもあるでしょう。この場合は、遺産分割協議書を金融機関に提出します。
このほかにも、被相続人や相続人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、所定の届出書など、必要書類は決して少なくありません。相続人それぞれの思いを確認した上で、速やかに準備を進めていきましょう。
凍結された口座からお金を引き出す方法はある?
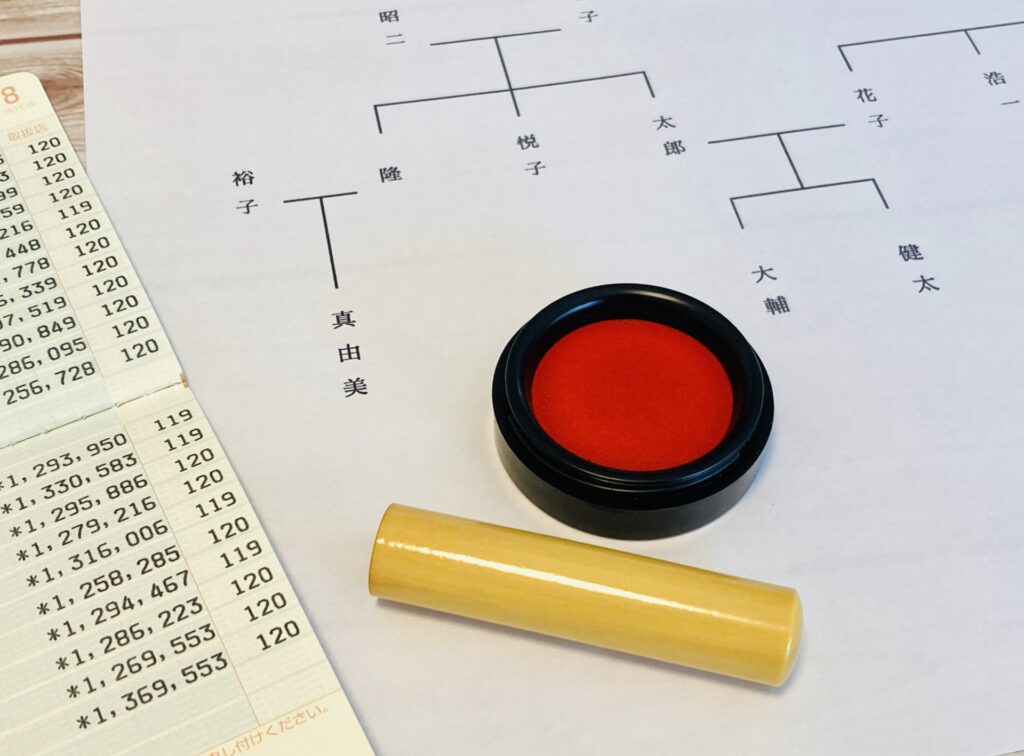
預金口座の凍結から、必要な手続きを経て解除されるまでには、一定の時間が必要になるでしょう。「このままでは葬儀代の支払いができない」「遺産分割協議が進まず、お金が足りない」といったトラブルに発展する可能性もあります。このような場合には、「相続預金の仮払い制度」を活用しましょう。
仮払い制度は、凍結された口座からでも、預金の一部を引き出せる制度です。出金できる金額は「1金融機関あたり150万円を上限とし、預金額の3分の1×仮払いを受ける相続人の法定相続割合まで」と定められていますが、必要書類さえ揃えれば、現金の引き出しが可能です。
仮払い制度を利用するためには、
・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人の戸籍謄本(全員分)
・印鑑証明書(手続きする人)
これらの書類が必要です。金融機関によっては、その他の書類の提出を求められるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
また家庭裁判所を通じて手続きを行った場合、引き出せる金額に上限はありません。少し手間はかかりますが、必要なお金が多いときには活用してみてください。必要性が認められれば、全額引き出しも可能です。
銀行口座はできるだけシンプルにしておくのがおすすめ
被相続人の死後、凍結された銀行口座からお金を引き出すのは、決して簡単ではありません。相続発生後の手間をできるだけ少なくするためには、生前から保有する銀行口座の数を絞っておくのがおすすめです。引き落とし用の口座や普段のお金を出し入れする口座をまとめておけば、相続手続きも楽になるでしょう。
使わない銀行口座を解約しておくことも、立派な終活の一つです。親が終活をスタートしたら、ぜひアドバイスしてみてください。またもちろん、自分自身の終活に活かすのもおすすめ。残された人に負担をかけないよう、しっかりと準備を整えておきましょう。
被相続人名義の預貯金は遺産の一部!慎重な取り扱いを

身近な人が亡くなった時点で、その人名義の預貯金は「遺産」として取り扱われます。たとえ家族であっても、その財産は家族だけのものではありません。相続人全員に受け取る権利があるお金なのです。慎重な取り扱いを心掛けてください。
口座が凍結されれば引き出せなくなりますし、たとえ凍結されなくても、勝手に引き出せばトラブルの原因になってしまうでしょう。どうしてもお金が必要なときには、相続人同士の意思疎通が重要です。しっかりと話し合った上で、仮払い制度の利用を検討しましょう。