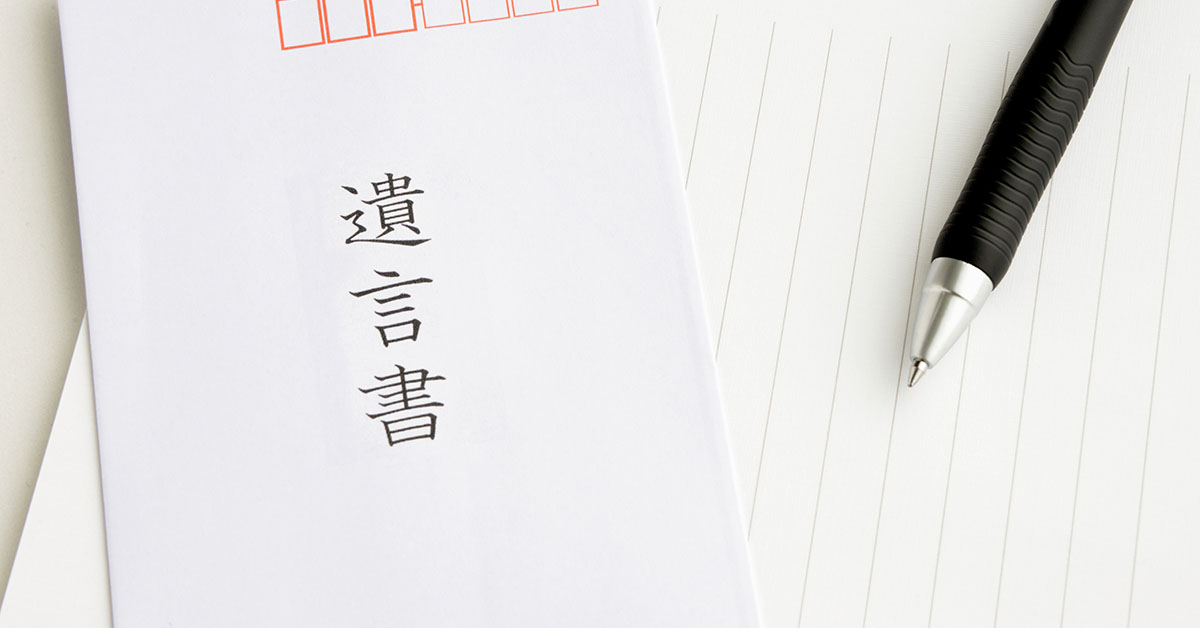デジタル化が進む今、インターネット上のさまざまなサービスを利用している方も多いのではないでしょうか?そうした状況の中で、問題になりやすいのがデジタル遺産についてです。家族に残す資産を考える上で欠かせないデジタル情報について、詳しく解説します。デジタル遺産とは何か、その整理方法や残し方はどうすれば良いのか、家族を困らせないために学んでみてください。
デジタル遺産とは?

まずは「デジタル遺産」とは何かという点について、正しい知識を身につけておきましょう。デジタル化が進む今、自身に関連する各種デジタル情報は、立派な遺産です。家族に残す資産の一つとして、しっかりと情報をまとめておく必要があります。
具体的には、デジタル遺産には以下のような情報が含まれます。
・オンライン上で管理されている資産のIDやパスワード情報
・スマートフォンやパソコンのロックパスワード
・各種ポイント情報
・電子マネー情報
・有料会員サービス
ネット銀行やネット証券が一般的になっている今、実際に利用している方は少なくありません。身近な銀行と比較して、「インターネット上でいつでも取引できる」というメリットがある一方で、「通帳」のような目に見える証拠が残りにくいという特徴があります。これらの情報を家族が把握しないまま相続手続きがスタートすれば、一生みつからない可能性も。仮に存在だけは知っていても、取引用の各種情報がなければ、ログインさえ難しくなってしまうでしょう。
また忘れてしまいがちですが、オンラインサービスにつながるための「手段」にも注目してみてください。スマホやパソコンのロックを解除するための情報も、デジタル遺産に当たります。利用しているポイントや電子マネーがあれば、そちらも対象です。
各種サブスクリプションサービスなど、有料会員サービスは、解約しない限りサービス提供(料金支払い)が続いてしまいます。どのようなサービスを利用していて、自身の死後どのように扱えば良いのか、事前に指示しておきましょう。
デジタル遺産の捉え方は人によって異なる
一般的にデジタル遺産とは、デジタル形式で保管されていた資産に関する情報を指すもの。しかし人によっては、もう少し広い意味で捉えるケースもあります。以下のような情報も、デジタル遺産に含めるケースもあるでしょう。
・SNSのアカウント情報
・過去のメールのやりとり履歴
・パソコンに保存されている画像やデータ
どこまでを「自身にとって重要なデジタル遺産」と捉えるのかは、個々の判断によって異なります。だからこそ、残された家族にとっては「どう扱えば良いのかわからない」といった事態に陥りやすいでしょう。
近年は終活の一環として、身の回りの持ち物の、生前整理を進める方も増えてきています。自分にとって身近な各種デジタル情報も、その一つであると心得て、いざというときにどうしてほしいのか情報をまとめておくことが大切です。
デジタル遺産の整理はどうすれば良い?
家族に残す資産の中でも、デジタル遺産については「どう整理すれば良いのかわからない…」と悩む方も少なくありません。自身の資産に関連する重要情報を、そう簡単に漏らすわけにはいかないと考えるのも、当然のことだと言えるでしょう。
こんなときには、以下の方法を実践してみてください。
1.必要なデジタル情報を、A4用紙1枚にまとめる
2.預金通帳などと一緒にまとめておく
デジタル遺産の中でも、特に重要なのはネット銀行やネット証券に関連する情報です。ログインのために必要なID・パスワードを一覧表にまとめたら、預金通帳や実印とともに厳重に保管しておきましょう。その他のポイントや電子マネー、有料サブスクリプションサービスについては、エンディングノートに記載しておくのもおすすめです。
デジタル情報を整理する際に注意しなければならないのが、「記載した情報は定期的に更新する」という点です。
不正利用を警戒し、ネット銀行やネット証券では一定期間ごとのパスワード変更を求めてきます。ある時点での情報を残していても、実際に相続がスタートした段階では「ログインできない」といった事態にもなりかねないでしょう。この場合でも「生前にどこに口座を有していたのか?」は把握できるわけですから、何も情報がない場合と比較すれば、はるかに良い状況です。とはいえ、ログインIDやパスワードを探したり、本人確認手続きを取ったりと、余計な手間が発生することには変わりありません。
保管したデジタル情報は、1年に一度を目安に更新するのがおすすめです。自分にとってキリの良いタイミングで、記載している情報に変更がないかどうか確認してみてください。
デジタル情報を整理しなかった場合のリスクとは?
最後に紹介するのは、生前にデジタル情報を整理しておかなかった場合のリスクについてです。残された家族にとっては、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
★遺産分割協議をやり直さなくてはならない
デジタル遺産の特徴は、「情報を事前に知らされなかった場合、見逃す可能性が非常に高い」という点です。オンライン上でどのようなサービスを利用していたのか、本人以外は把握できません。遺産分割協議に必要な遺産調査でも見逃され、デジタル遺産以外について分割協議がまとめられてしまう可能性が高いでしょう。
遺産分割協議がまとまったあとにデジタル遺産が発見されれば、協議そのものがやり直しになってしまいます。相続税が発生する場合は、期限後申告や修正申告が必要になる可能性もあるでしょう。最悪の場合、税務署から申告漏れを指摘され、重加算税が課せられるケースもあります。
★相続人が損をする
FXやネット証券で保有する株式、仮想通貨といったデジタル遺産の評価額は、相続発生時の時価によって計算されます。相続税の金額も、こちらをもとに決定されるでしょう。デジタル遺産情報を把握できず、放置されてしまった場合でも、相続が発生した段階でその評価額はすでに決まっているというわけです。
一方で、相続人が実際に受け取るお金は、取引完了時の価額です。相続開始時よりも相場が下がっていれば、「相続人が受け取るお金は少ないにもかかわらず、多額の税金を取られてしまう」といった事態にもなりかねません。
デジタル情報は事前に整理を

各種デジタルサービスが身近になっている今、自分がどのようなサービスを利用し、どういった資産を保有しているのか、他者にわかるように整理しておくことが大切です。デジタル情報の重要性を把握した上で、できるだけ早く情報を整理しておきましょう。
情報を整理する方法は極めてシンプルです。「家族に残す資産の一つ」として必要な情報をまとめ、確実に見つけてもらえるよう準備を整えておいてください。