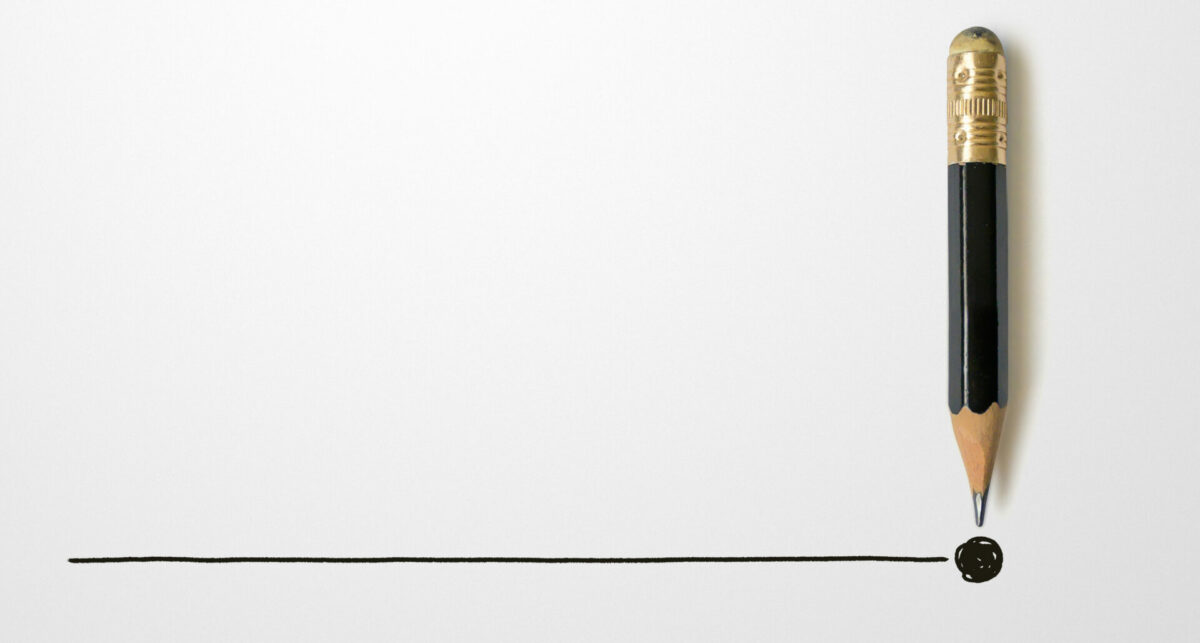子どもたちが独立してほっとしたのもつかの間、そろそろ老後のことと一緒に亡くなった後のことも考えなければならないかもしれません。特に最近は親世帯のみ、子世帯のみで生活しているご家庭が増えてきています。
本記事では、遺産にかかる税金について、計算方法と併せて解説します。自分たちが亡くなった後に困らないように財産の整理と一緒に相続にかかる税金についても考えてみませんか?
遺産にかかる税金「相続税」の手続きについて

貯金や不動産などの財産を遺産として受け継いだ場合には税金として相続税がかかります。相続税は、借金や葬式費用などを除外したあとの残額が、基礎控除額よりも上回る場合にかかります。
財務省のホームページによると、令和元年時点での相続税がかかった方の割合は、亡くなられた方の8%程度です。
参照:『親が亡くなりました。遺産を相続する場合にどのような税金がかかるのですか?』
基礎控除額を超える部分の遺産は相続税の課税対象になります。
相続税の申告期限は被相続人がなくなった日の翌日から10ヵ月以内におこないます。相続税の納税も申告期限内におこなわなければなりません。
相続税の計算に誤りがあると、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課せられる場合もあります。
葬儀費用や相続する財産にまつわる確認などには、書類の取り寄せや手続きするのに時間がかかるものもあります。できるだけ生前のうちから財産を把握しておき、遺言書を準備しておくのが理想です。
遺産相続から税務署へ相続税申告までの税金支払い流れについて
遺言書があれば、原則その内容に沿って相続することになります。
遺言書がなければ、相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い、決めなければなりません(遺産分割協議)。
話し合いによって決められた分割遺産の内容で相続税を計算したあと、税務署へ申告します。
遺産の税金対象となる金額について
相続した財産の内、課税対象になるのは、現金・預貯金、株式や債券等の有価証券、土地・建物等の不動産、貴金属、書画骨董等亡くなった人が所有していた財産です。これに加えて、亡くなったことによって入ってくる死亡保険金や死亡退職金等の「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。これらの合計が課税対象となる課税相続財産総額です。
相続税の対象となる金額は、課税相続財産総額から債務・葬儀費用・非課税財産を差し引いた正味の遺産額で計算します。
非課税財産に該当する遺産については下記の通りです。
- お墓や仏壇、祭具など
- 寄付した財産
- 生命保険金のうち500万円×法定相続人の人数
- 死亡退職金のうち500万円×法定相続人の人数
上記のものは非課税財産として差し引かれます。
遺産にかかる相続税の基礎控除とは
遺産のうち一定の金額までは税金がかからない制度です。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
相続人が死亡・廃除・欠格のどれかに該当すると法定相続人に含めません。
- 廃除:民法第892条に基づいて相続人の資格を失ったもの
- 欠格:民法第891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度
遺産の法定相続人の優先順位は配偶者から
遺産の相続には優先順位があり、相続人が誰になるかで相続割合や法定相続分は違います。
遺産の法定相続人の優先順位は配偶者から順に、以下のように民法で定められています。また内縁の妻は相続人に該当しません。
- 第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫)養子・認知した子ども・前の配偶者との間の子ども
- 第2順位:両親(亡くなっている場合は祖父母)・養父母
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)
遺産の相続割合について
法定相続分は、相続人が配偶者と子ども2人の場合には配偶者1/2、残りの1/2を子どもたち2人で均等に分けるため、子ども1人につき1/4となります。
配偶者に子どもがなく父母が存命の場合は、配偶者2/3・父母1/3です。
また配偶者に子どもがなく父母もいない場合には、兄弟姉妹と分け合う形になり、配偶者3/4・兄弟姉妹1/3となります。
遺産を相続放棄すると基礎控除はどうなるのか?
相続放棄はなかったとして計算します。仮に法定相続人が子3人のみの時、子3人のうち1人が相続放棄をしたとしても、基礎控除額は4,800万円のままです。
相続税の配偶者控除は1億6,000万円まで
配偶者にはさまざまな相続税の優遇措置があります。配偶者に対する相続税額の軽減という税を減額する規定があり、被相続人と長い間生活を共にしてきたため、一緒に財産を作り上げた貢献があるとみなされるのです。
配偶者への相続は同一世代間の財産の移転とされ、遠くない将来に相続が再び発生するため、相続税の負担を軽減する目的も含まれているのです。
また被相続人が亡くなったあとの、配偶者の生活を保障するために優遇されています。
配偶者控除では相続財産が1億6,000万円までは税金がかかりません。
「配偶者控除」または「法定相続分の基礎控除」のどちらかを選択して相続税の計算を行います。
二次相続の問題とは
相続税の問題は、両親のどちらかが亡くなるとおこります。例えば最初に父が亡くなると、一回目の相続「一次相続」が発生します。次に母がなくなると、二回目の相続「二次相続」の問題がおこるのです。
「二次相続」税金での問題点について
一次相続での通常の相続人の構成は、おおむね「配偶者と子」です。二次相続の場合では「子」となるため、遺産の分け方や相続税の計算方法に違いが生じます。
最も大きいのが相続税の特例の部分で、一次相続で受けられた配偶者控除などの優遇がなくなるため、税金の負担が大きくなるのです。
以上のように二次相続では相続税の負担が大きくなるため、一次相続から将来を見据えた税金対策をとる必要があります。
遺産にかかる税金「相続税」の計算方法について

相続税の計算方法はまず基礎控除を算出し、各人の相続財産を一度合算したあと、法定相続分で按分して仮の相続税を計算します。
仮の相続税の合計が相続税の総額です。
相続税の総額を各人の実際の相続割合に合わせて案分します。
課税の対象となる遺産の総額を計算する
課税の対象となる遺産とは以下のような財産です。
- 預貯金や不動産などプラスの相続財産
- 死亡保険金、死亡退職金などのみなし相続財産
- 相続開始前3年以内に贈与された財産
- 相続時精算課税制度の生前贈与財産全部
これに、「借金などのマイナスの財産・葬式費用を差し引いたもの」が正味の遺産額となります。
正味の遺産額が基礎控除額より少なければ相続税はかからない
以下のようなときは「正味の遺産総額>基礎控除額」でも納税額が0円になります。
- 小規模宅地等の特例の適用後、正味の遺産総額が基礎控除額以下になるとき
- 配偶者の税額軽減や相次相続控除などの税額軽減制度で納税額が0かマイナスになるとき
「正味の遺産総額≦基礎控除額」のときだけ申告不要になります。
課税の有無や課税額を知るには「正味の遺産総額」「基礎控除額」を正確に計算しなくてはなりません。
遺産の相続税計算について注意する点
相続税は課税遺産総額に対して課税となりますが、土地の評価額に直接税率をかけて算出するわけではない点に注意が必要です。
宅地の場合の評価方法は2つあります。
- 路線価方式
- 倍率方式
相続した土地の評価方法がどちらになるかは、毎年の国税庁ホームページに掲載される路線価図・倍率表でわかります。
参照:『財産評価基準書 路線価図・評価倍率表』
また賃貸している場合、評価計算が異なることに注意が必要です。被相続人が土地や建物を他人に貸していると、自由に売却できません。このため土地や建物の評価が低くなり、不動産の評価減を行う必要が出てきます。
遺産に関わる税金の相談は誰にすればいいか

相続に関する税金の相談方法には以下のような3つの方法があります。
➀電話で相談する
- 国税局電話相談センター
- 税務署の窓口
相続に関する税金の相談や質問には、国税局相談センターがよいでしょう。電話の対応専門の職員が常駐しているためスムーズに答えてもらえます。
税務署の窓口では電話対応以外の業務も兼任しているため、すぐに回答ができないこともあります。税務署から届いた書面や税金の支払いに関する相談が必要な場合に限定しておきましょう。
➁税務署を訪ねて相談する
直接訪問する場合には、事前予約を行います。相談する税務署は被相続人の住所を管轄する税務署を選びましょう。相談する内容や必要な書類は、まとめて準備しておくようにします。
税理士に相談する
税理士に相談するのも一つの手です。税理士の場合、相続税に関する申告業務や遺産分割協議をはじめとする手続きに関するさまざまなアドバイスをしてくれます。
税理士の多くは無料相談を30分ほど行ってくれるので、預金通帳や確定申告書などの必要書類を用意したうえで相談を検討してください。
まとめ:遺産にかかる税金「相続税」を知って不安をなくそう

遺産にかかる税金、相続税の基本的な情報についてご紹介しました。
相続税がかからないのは基礎控除まで、もしくは配偶者控除の1億6,000万円までとなります。相続税で注意する必要があるのは一次相続よりも二次相続の場合です。
また相続に関する相談は、国税局電話相談センターを利用します。相続税に関する知識を深めて、税金対策に備えていきましょう。