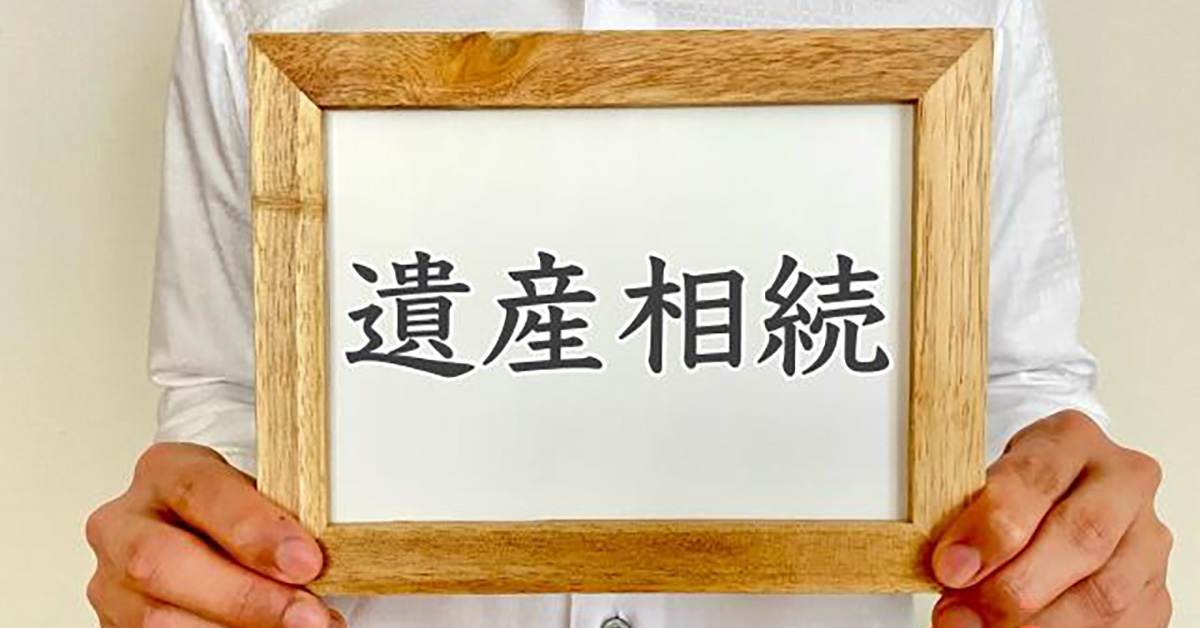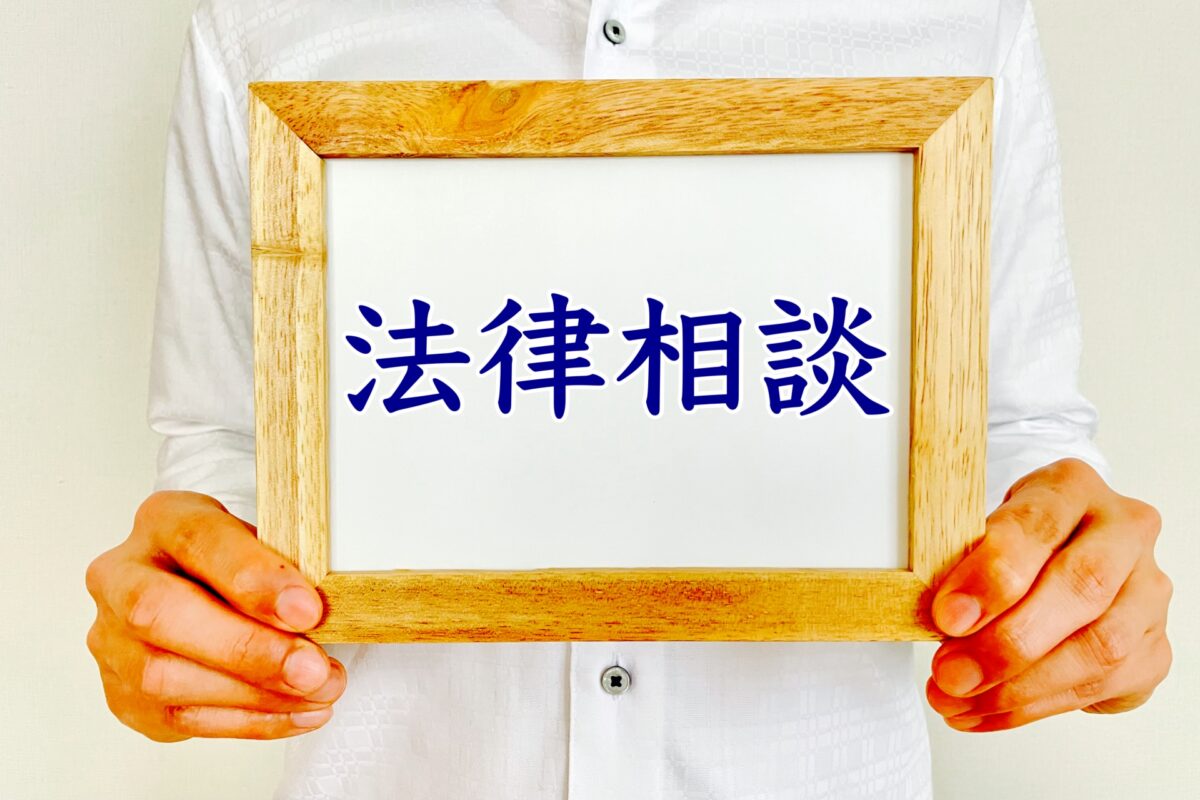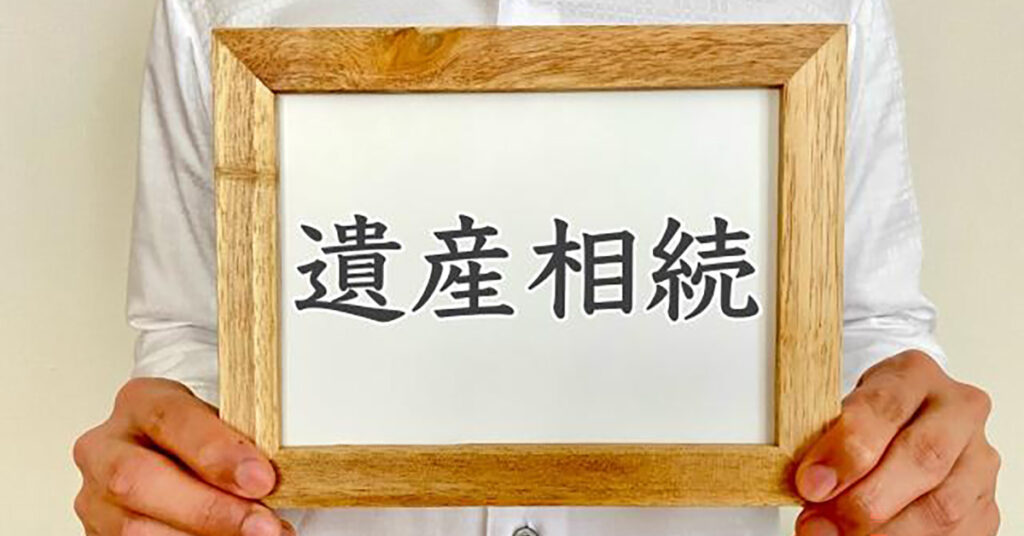
自分は家族に残せる遺産が少ないから、残した遺産で家族が揉めるような事態にはならないと安心していませんか?また、どんな遺産を家族に残せるのかしっかりと把握していますか? 今回は、残す遺産で家族が揉めないためにやっておくべきことをご紹介します。自分たちは関係ないのではなく、少しずつ家族に残す遺産について考えていきましょう。
家族に残す遺産とは

家族に残す遺産といえば、お金や土地を思い浮かべる方が多いです。しかし、実際には多くの方が思い浮かべるお金や土地といった正の遺産にも相続税がかかるものと、かからないものがあります。
また、注意すべきは負の遺産といわれるものです。どういったものが該当するのか、くわしく見てきましょう。
相続税のかかる正の遺産
まずは多くの方が家族に残す遺産として意識している、相続税のかかる正の遺産です。国税庁は相続税のかかるものとして、以下のように決められています。
「死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。」
引用:『No.4105 相続税がかかる財産』
この決まりに該当し、主に相続税がかかるものは以下の9つです。
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 宝石や貴金属
- 土地
- 家屋
- 貸付金
- 特許権
- 著作権
これらの金銭に見積もれる経済的価値のあるものすべてに相続税がかかります。
意外と知られていないのが、特許権や著作権でしょう。もし、特許権や著作権を持っているのであれば、必ずその旨やいくら位の収入があるかを家族にわかるようにしておくとわかりやすいです。
相続税がかからない遺産
亡くなった方から引き継ぐもので経済的価値のあるものはすべて相続税かかるといいましたが、一部例外もあります。
| 相続税がかからない遺産 | 例外 |
| 墓地・墓石・仏具・神棚など | 骨董品として所持していた金の仏像など |
| 弔慰金・花輪代など | 業務上の死亡(普通給与の3年分を超える場合) 業務上の死亡ではない(普通給与の半年分を超える場合) |
| 生命保険金・退職手当金 | 500万円×法定相続人の数以上の金額 |
| 損害賠償金 | 財産的損害(付添看護費や医療費などに対する賠償金を請求権)、逸失利益 |
| 寄附した財産 | – |
上記の5つは一定条件をクリアすれば相続税がかかりません。しかし、例外として記載した条件を外れた場合は相続税がかかります。
生命保険は場合によって相続税がかかる
先程、生命保険に関しては500万円×法定相続人の数以下の金額は相続税がかからないとお伝えしましたが、それを超える場合には相続税がかかります。
また、生命保険の中でも以下のようなものについては、被相続人自体が受取人の場合には相続税の課税財産となります。
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- ガン診断一時金
- 特定疾病保険金
- 先進医療給付金
- 就業不能給付金
さらに、死亡保険や満期保険金は契約者や被保険者に誰が該当しているかによって、税金の種類が変わることにも注意が必要です。
- 契約者=被保険者(相続税)
500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。 - 契約者=保険金受取人(所得税)
支払った保険料を差し引いた分から所得税を支払います。 - 契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ違う(贈与税)
所得税や贈与税は金額に応じた分を支払う必要があります。
できれば家族に残したくない負の遺産
遺産は何も先程紹介した正の遺産だけではありません。問題はできれば家族に残したくない負の遺産です。
- 借入金やローン
- 未払金
- 保証金や預り金
- 保証責務や連帯責務
- 公租公課
これらはあなたが亡くなった場合、残された家族に相続されます。
借入金やローンは負の遺産としてわかりやすいですが、意外と家族に伝えずにあとからトラブルになるのは連帯保証人です。連帯保証人になっている場合は誰の、どんな保証人になっており、いくらの借入金額なのかしっかりと家族に残しておきましょう。
相続放棄や限定承認といった選択
負の遺産があった場合や正の遺産であっても何らかの事情で遺産を相続したくない場合、残された家族には2つの選択肢があります。
1つ目は、正の遺産と負の遺産の両方の相続権を完全に放棄する相続放棄。2つ目は、正の遺産の金額が負の遺産を上回っている場合、正の遺産で負の遺産を支払い残った正の遺産分を相続する限定承認です。
どちらも申述期間は相続開始(亡くなった事実を知って)から3ヵ月以内です。相続人が複数いる場合に相続放棄や限定承認を行う場合は注意してください。
相続放棄に関しては複数人いる相続人のうち1人だけ相続放棄して、ほかの方は相続できます。しかし、限定承認は相続人全員が同意しなければ限定承認は行なえません。
残した遺産で揉める家族の特徴

ここでは、遺産で揉める家族の特徴を紹介します。
家族に残せる遺産は少ないから遺産で揉めたりしないだろうと安心していませんか?遺産で揉めた割合と相続金額は1,000万円以下で約33%、5,000万円以下で約42%です。遺産で揉める理由に相続金額はさほど関係ありません。
それではどんな特徴がある家族が遺産で揉めるのでしょうか?
➀相続人が仲が悪いか疎遠
相続人同士が仲が悪かったり、疎遠だったりすると遺産分割の際に行われる話し合いがスムーズに進まず、揉める場合が多いです。仲が悪い場合は、遺産をより多くもらいたい者同士で譲り合えず、揉める可能性があります。疎遠だった場合、そもそも遺産分割の話し合いに参加できない可能性があります。
また、遺産分割をする際には相続人全員の参加が必要です。委託したり、異議申し立てをしない約束で不参加で行う場合もありますが、連絡が取れる前提です。疎遠の場合、そもそも遺産分割を行う連絡すらできない場合があります。
➁1人が高額の贈与を受けていた
相続人のうちの1人が高額の生前贈与を受けていた場合も、揉める原因になります。生前贈与がなければ、遺産がもっと残っていたかもしれない、生前贈与をもらっているのに遺産を平等に分けなければいけないのかといった問題が発生します。
特に、有効な遺言書がない場合は相続人同士の話し合いで決まりますが、かなり揉めるケースが多いです。
➂金融資産以外の資産が多い
お金など割れるものであればよいのですが家や土地などの不動産が多い場合、どう分けるのか選択肢が増えるため揉める原因になります。不動産の場合主に4つの選択肢があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有
相続人が現在住んでいる場合は特に揉めやすいです。
➃相続人に何らかの支障がある
相続人がもし認知症だった場合、きちんとした判断ができるか分からず相続の内容を一切理解していない可能性があります。そのような正常な判断ができないとされた場合は、成年後見人を選任します。
行方不明で連絡が取れない場合も、失踪宣言や不在者財産管理人を選任しなければいけません。これらの手続きは家庭裁判所で行うため、手間と時間がかかります。
⑤想定外の相続人がいた
亡くなった方の前妻や前夫に子どもが居た場合、家族が知らない子どもが居た場合、血縁者であるため相続権があります。しかし、想定外の相続人と公平な相続を行いたくない相続人がいれば揉める原因になります。
⑥介護負担が相続人で異なる
亡くなった方の介護を子どものうちの誰か一人だけが行っていた場合、介護分をほかの相続人よりも多く貰おうと思うため揉めやすくなります。一応、民法では介護を行っていた相続人に対してほかの相続人よりも多く相続できる制度があります。
しかし、それが認められるか、どの程度多く相続できるかは相続人同士で決めるため、揉める割合がかなり高いです。
⑦遺産が使い込まれていた
亡くなった方の財産管理を相続人が1人で行って使い込んでいた、使い込みが疑われる状況の場合、遺産が少なくなるため揉める原因になります。また、相続についての話し合いの際に遺産の一部しか開示せず、揉める場合もあるので財産管理は複数で行うか、書面等ではっきりと残しておくとよいでしょう。
残した遺産で家族が揉めないためにやっておくべきこと

家族が遺産で揉めないため、生前にやっておくべきことはあります。自分が残した遺産で家族が揉める状況を望む方は居ないでしょう。それでは、家族が揉めないためにやっておくべきことを2つ紹介します。
遺言書を作る
相続で起こる揉めごとへの対策として有効なのが遺言書です。
ただし、便箋などに相続の割合を書くような簡易的なものではなく、弁護士や司法書士に依頼して、法的に有効な遺言書を作ってもらいましょう。「長男にすべて相続させて長女は0」など、よほど無茶苦茶ではない限り、法的に有効な遺言書が遺産相続の場では最も有効です。
エンディングノート
最近は早くに終活を始める方も多く、エンディングノートを書く方も増えています。エンディングノートは、財産や介護など意思疎通が難しい場合や死後にまつわるさまざまな希望を書き残すためのものです。
しかし、あくまで希望であり、遺産分割方法について記載はできますが遺言書のような法的効力はありません。エンディングノートに書いてある財産分与を採用するかは、相続人任せになりますので、あくまでも家族同士が揉めないように作っておくとよいでしょう。
家族信託の活用
家族信託とは、判断能力が低下する老後に備えて、持っている不動産や預貯金等の遺産を信用できる家族に管理や処分を任せる方法です。遺言書よりも幅広い遺産の承継ができます。
家族が遺産で揉めないために生前からの準備を

いかがでしたか?今回は、残す遺産で家族が揉めないためにやっておくべき2つをご紹介しました。家族が揉めないための対策をやって無駄になることはありません。 家族には揉めずに仲良くして欲しいと思うのは当然ですよね。自分の所は大丈夫と決めつけるのではなく、できる限り家族が遺産で揉めないために生前から準備をしておきましょう。