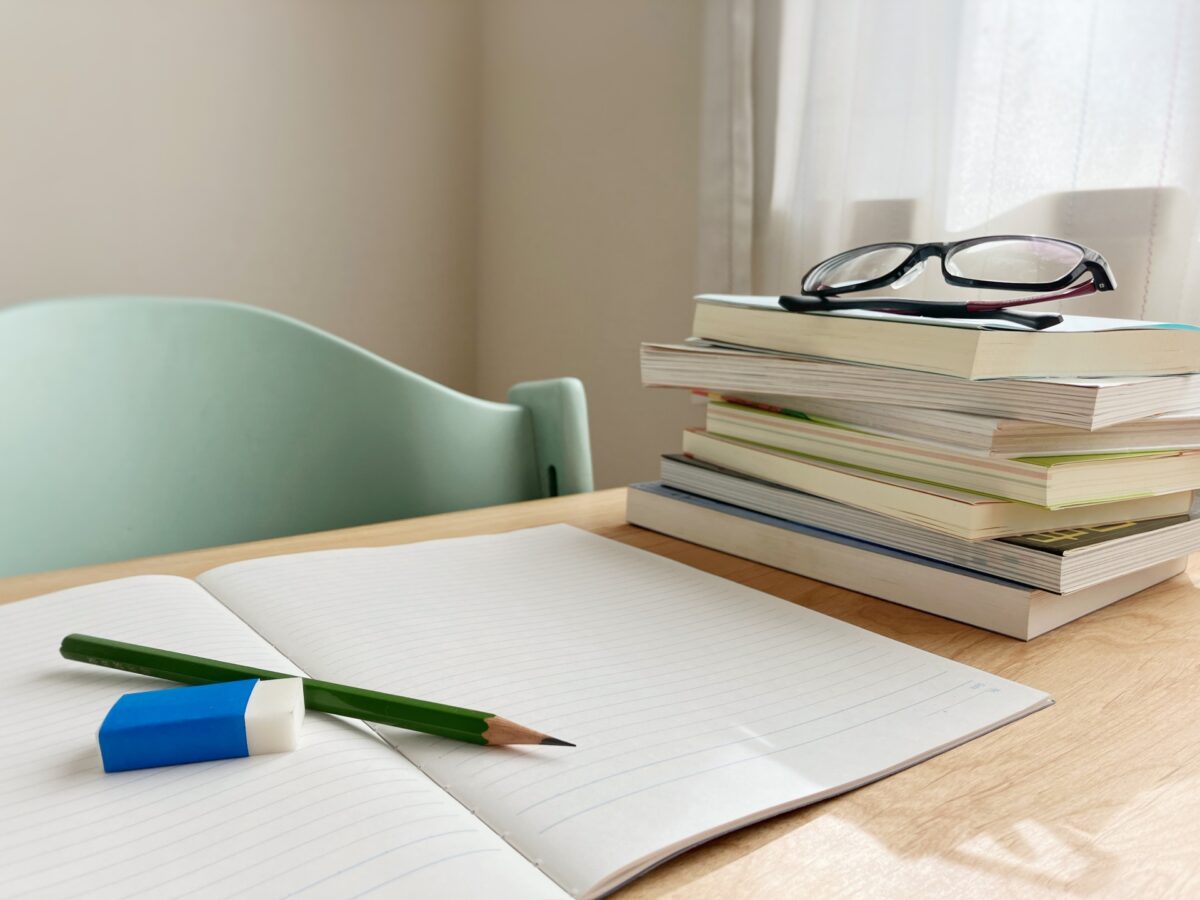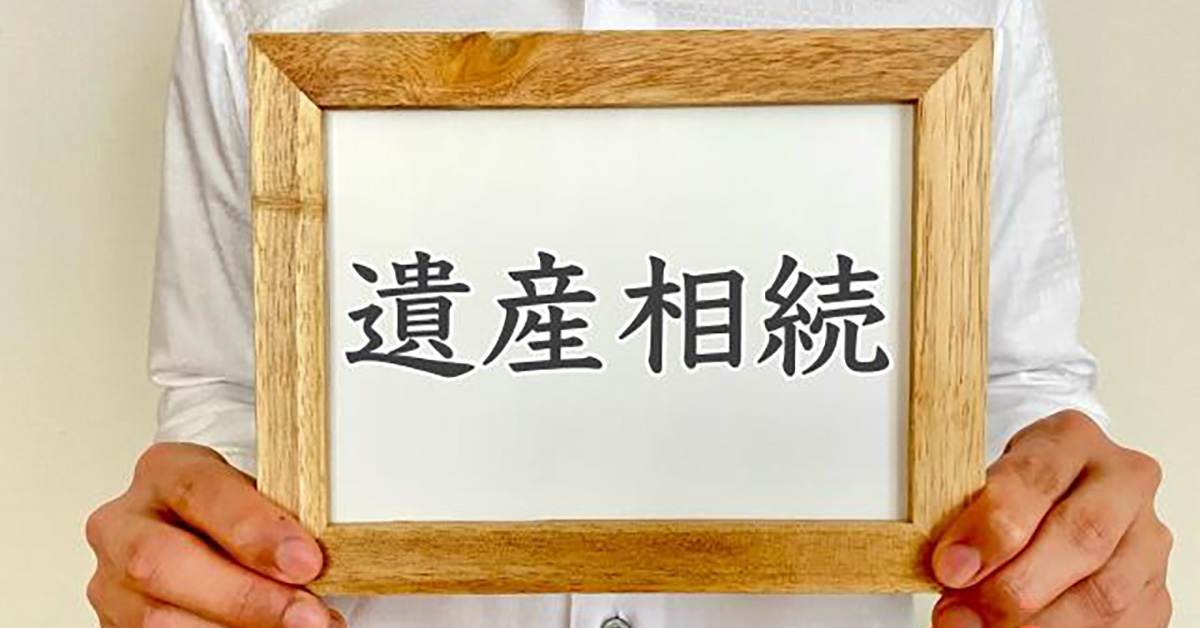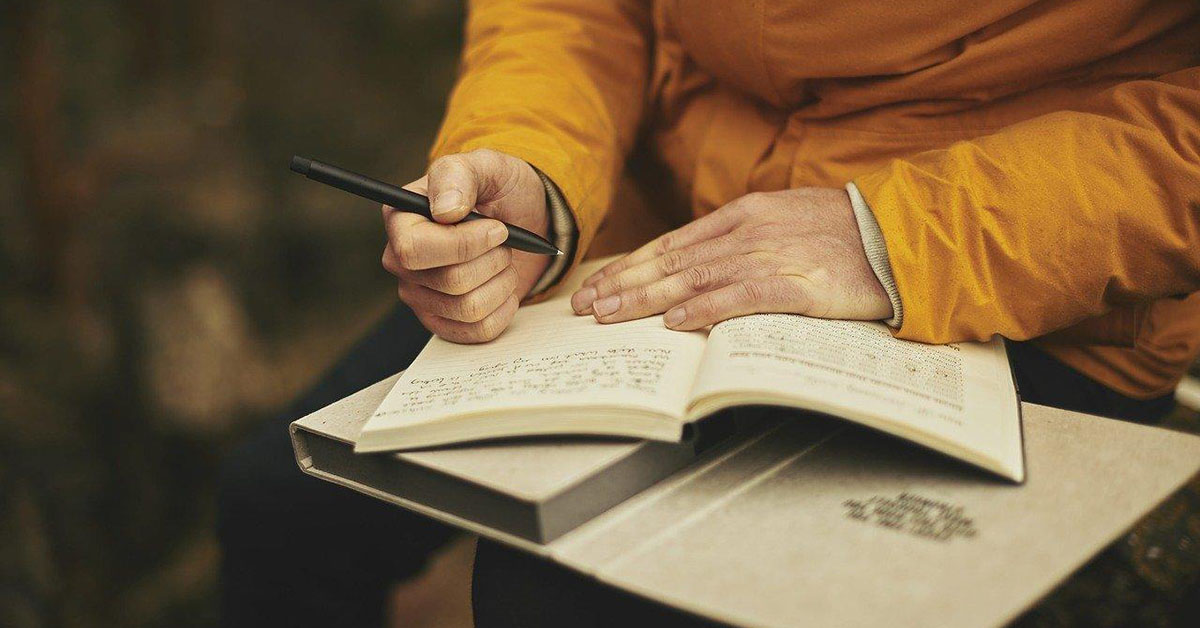老後の生活を支えてくれる厚生年金。自身の将来を考える上で、非常に重要な年金だからこそ、実際に年金を受け取る前から正しい知識を身につけておくことが大切です。
今回は、夫婦が離婚した場合の厚生年金の扱い方について解説します。「離婚したら厚生年金も財産分与の対象になると聞いたけれど…本当なのか?」といった疑問を、すっきり解消していきましょう。
厚生年金そのものは財産分与の対象にならない!
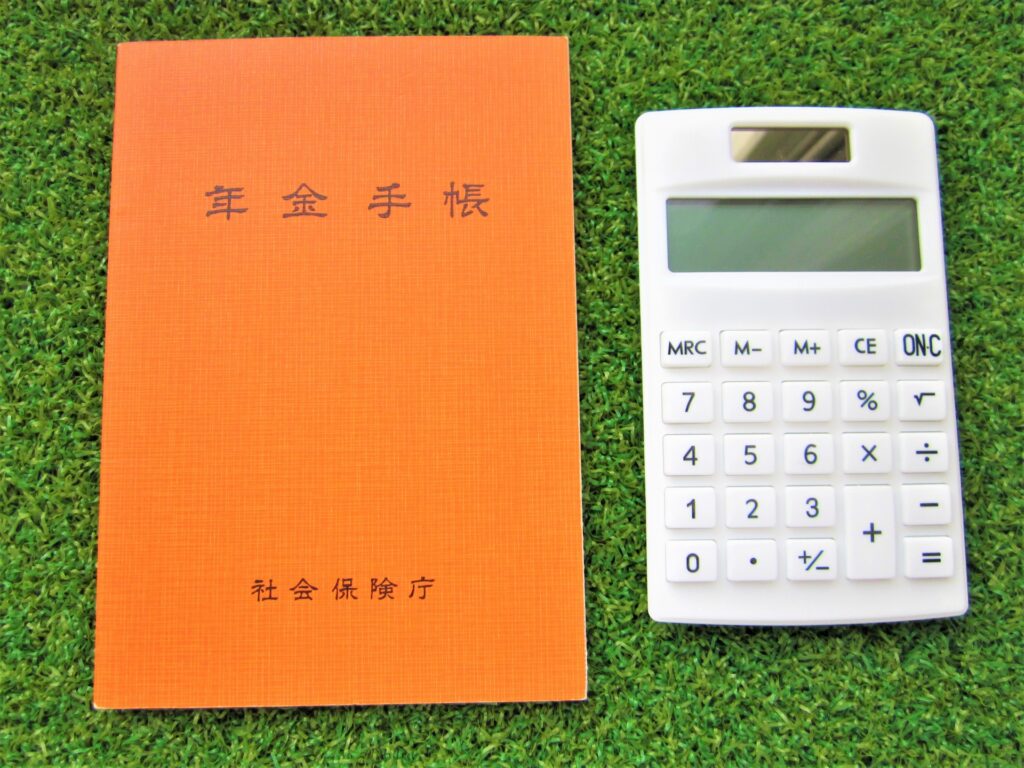
長年連れ添った夫婦が離婚する際に、トラブルの原因になりやすいのが財産分与です。婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産は、離婚するにあたって、夫と妻の間で公平に分配されます。「名義がどちらにあるのか」ではなく、「実質的に二人が協力して築き上げてきた財産かどうか?」が重視されます。
たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻という家族構成であった場合、「家や土地は夫名義である」というご家庭も多いのではないでしょうか。しかし婚姻中に得た不動産は、夫のみの努力で購入できたわけではありません。夫の財布の裏には、妻の支えがあったと考えられるでしょう。たとえ夫名義であっても、夫だけが家や不動産を100%手に入れるわけではありません。
財産分与では、夫婦が公平に財産を分配できるようになっています。もちろん財産分与の対象は、婚姻中に使用していた家具や家財はもちろん、預貯金や自動車、有価証券に保険解約返戻金と多岐にわたります。お互いの退職金さえも、財産分与の対象になり得るのです。
ここで気になるのが、老後に受け取る厚生年金についてです。サラリーマンの夫と専業主婦の妻という家族構成の場合、当然妻は、厚生年金に加入していません。しかしその加入実績は「夫婦が協力して築き上げた財産」とも捉えられます。妻側が、「だとしたら財産分与の対象になるのでは?」と考えるのは、ある意味で当然のことと言えるのかもしれません。
厚生年金は、現役期間の加入実績をもとに、将来受け取る金額が変動する仕組みです。残念ながら、この「将来受け取れる厚生年金そのもの」が財産分与の対象になるわけではありません。離婚する夫婦で分け合えるのは、「婚姻期間中に納めた年金保険料の納付記録」です。この制度を、年金分割と言います。
婚姻期間中に収めた年金保険料を夫婦間で分割すれば、専業主婦の妻であっても「厚生年金に保険料を納めている」と判断されます。年金分割をしなければ基礎年金のみが支給されるところを、納付保険料に応じた厚生年金を受給できるのです。
「夫に支給される厚生年金そのものの2分の1が受け取れる」というわけではありませんが、年金分割を利用すれば、結果として年金を分け合う形を実現できるでしょう。
年金分割の注意点は?
離婚時に年金分割をする場合、以下の3点に注意してください。
★請求期限は離婚してから2年以内
夫婦が離婚した際の、厚生年金の年金分割請求には、請求期限が設けられています。基本的には、離婚した日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると請求できなくなってしまうので、注意してください。
ちなみに年金分割請求は、事実婚状態にあった人でも可能。たとえ事実婚であっても、一方の厚生年金加入歴は、もう一方の協力あってこそのものだと判断できるためです。ただしこの場合、「具体的にいつからいつまでが婚姻期間であったのか?」が不明確になってしまいがちです。事実婚をしている間に「国民年金の第3号被保険者資格」を取得していた場合、その喪失日を「事実婚を解消した日」と証明できます。その翌日から2年以内に請求手続きをしてください。
★分割制度は2種類
年金分割で問題になりやすいのが、分割割合についてです。どちらにどのくらいの厚生年金記録が割り当てられるのかは、以下の2つの方法によって決定されます。
・合意分割
・3号分割
合意分割とは、当事者間の合意によって分割割合を決定できる制度のこと。一方が希望しても他方が同意しなければ、分割は認められません。この場合、裁判手続きを経て妥当と思われる分割割合が決定されます。分け与えられる側の割合の上限は2分の1です。
3号分割制度は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に、第3号被保険者期間がある方向けの分割制度です。第3号被保険者であった期間に、相手方の厚生年金の保険料納付記録があれば、2分の1ずつ強制的に分割されます。この場合、相手の合意は必要ありません。
離婚による年金分割を検討する場合、自分がどちらに該当するのかしっかりと確認しておきましょう。「自分ではよくわからない…」という場合には、請求期間内に年金事務所等で相談するのがおすすめです。
★分割の対象になるのは厚生年金のみ
年金にはさまざまな種類がありますが、年金分割できるのは、厚生年金および共済年金のみという決まりがあります。国民年金はもちろん、企業年金や個人年金の保険料納付記録を分け合うことはできません。
また年金分割は、離婚する夫婦間の格差を是正するための制度です。「夫から妻に無条件に年金加入期間を分け与える制度」というわけではないので注意しましょう。
たとえば、夫よりも妻の方が厚生年金を多く納めている場合、年金分割によって妻の保険料納付記録が夫の方へと分け与えられます。手続きによって、将来受け取る年金額が少なくなってしまう可能性についても、事前に考慮してみてください。
年金分割の申請方法とは

離婚時に年金分割を希望する場合、自分自身で手続きする必要があります。「何もしなくても離婚と同時に分割される」というわけではないため、注意してください。請求先は厚生労働大臣で、年金事務所を経由して手続きします。
年金分割をするためには、まずは双方の厚生年金加入状況をはっきりさせる必要があります。標準報酬総額や按分割合の範囲など、分割のために必要な情報を開示してもらえるよう、「年金分割のための情報提供請求書」を使って請求しましょう。交付された「年金分割のための情報通知書」をもとに、按分割合を決定し合意します。合意内容は、合意書や公正証書といった正式な書面に残しておきましょう。
その正式な書面と標準報酬改定請求書、年金手帳や戸籍謄本などを年金事務所に提出すれば、年金分割が実行されます。
厚生年金と財産分与について正しい知識を身につけよう
離婚を考える際に、「将来の生活が不安…」と感じる方は少なくありません。将来受け取る厚生年金そのものが財産分与の対象になるわけではありませんが、きちんと手続きすれば年金分割は可能。将来受け取る年金額をアップできる可能性もあります。
一方で、手続きしたことによって、自分が将来受け取る年金額が減少してしまう恐れもあります。厚生年金と財産分与、そして年金分割について、正しい知識を身につけた上で、より良い道を選択しましょう。