
「終活っていつから始めればいいだろう…」「終活は具体的に何をするの?」「まわりの人はどんなタイミングで終活を始めているんだろう?」終活に関する悩みは多いのではないでしょうか?
今回は、終活の種類と終活を始めるタイミングを紹介していきます。終活をよく知ることで、余裕を持った行動ができるようになります、この記事を読んで、後悔のない終活をしていきましょう。
終活の種類を知ろう
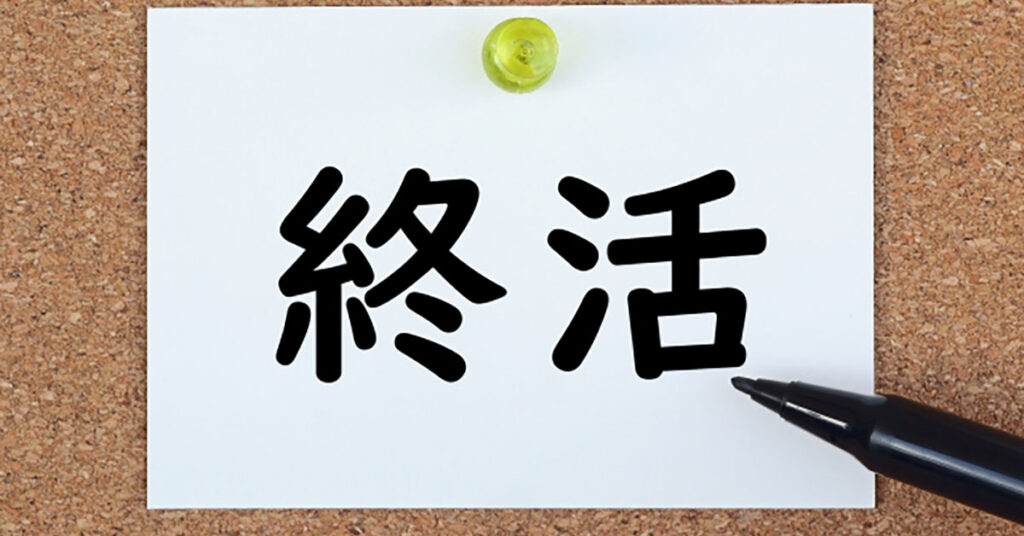
終活と一言で言っても、実際にやっていく内容はさまざまなものがあります。今回解説する終活の種類と内容は以下のとおりです。
- 自分史(エンディングノート)
- 介護・看病
- 葬儀・お墓
- 財産
- 身辺整理
それぞれみていきましょう。
自分史(エンディングノート)
自分史とはエンディングノートとも言われ、家族に向けて「死後こうしてほしい!」という意思を伝える物となっています。葬儀やお墓など、「こうしたい」という意思を残しておくことで家族がそれに沿ってすすめることができスムーズに故人を送ることができます。
また、親しい友達などの人間関係も書いておくことで、自分が亡くなったことを知らせるべき相手も遺族は知ることができるのです。遺言書との違いは遺産相続などの内容を書くか書かないかの違いですが、最近はエンディングノートにまとめて記しておく人も増えているようです。
寝たきりになってからではエンディングノートを書くことができなくなってしまいますので、元気なうちに予め書いておくことが重要になります。後悔のないように時間をかけてゆっくり書いていきましょう。
介護・看病
認知症などが進行してしまった場合、「誰が介護するのか」「どこの病院に行くのか」などはっきりとしておいたほうがいいでしょう。もし本人の意思がわからないままだと、最終的に決めるのが家族になってしまいます。
延命治療ができる場合などは、するかしないかも家族の判断になってしまいますので家族が大きな悩みを抱えることがないように事前に意思を伝えておくべきですね。持病がある場合は、終活を始めるタイミングに伝えておくと家族も心の準備ができますから、きちんと伝えておきましょう。
家族に伝えづらいことではありますが「私はまだ大丈夫だから」と先延ばしにせず、家族のことも考えて余裕を持って伝えておくようにしましょう。
葬儀・お墓
最近では「家族葬」が増えてきていることもあり、故人がどんな葬式を希望しているかを遺族が知ることはとても重要なことの一つです。お葬式にも少なからず費用がかかりますので、家族に迷惑がかからないようにするためも葬儀屋さんや葬儀の形態は早めに決めておくべきでしょう。
また、お墓は生前に建てる場合も増えてきており、本人が「こんなお墓に入りたい」と希望すれば家族も快く応えてくれることでしょう。家族と一緒に終活を進めていくことも、後悔のない終活をするうえで一つのポイントになります。
財産
終活において、財産に関することはとても重要なことです。どれだけの財産が残されているか、誰にどれくらい分配するか、どんな資産を持っているか、すべてはっきり残しておかないと後々整理がつかなくなってしまうことも。
月々の支払いやローン、借金などがある場合は早めに伝えておかないと亡くなったあと督促状が来てしまいますよね。遺産分割に関してはきちんとした遺言書を書くと法的に認められた文書となり、故人が希望したとおりに分配されます。
たった一人の財産かもしれませんが、整理をしておかなければかえって家族に負担をかけてしまうこともありますのでしっかり確認しておくようにしましょう。
身辺整理
終活を始めようとしているあなたは身辺整理のことを考えていますでしょうか?生前に自分のものをしっかり整理しておくことで、先程解説した財産の整理もしやすくなります。
財産になるような高額のものも予め売っておけばその分まとめて遺産にできますよね。土地や不動産を所有している場合はそれも整理しておきましょう。
また、物が多いと亡くなったあとに家族が遺品整理などでとても大変になってしまいますので、元気なうちに片付けられるものは片付けておくとよいですね
終活を始めるタイミング
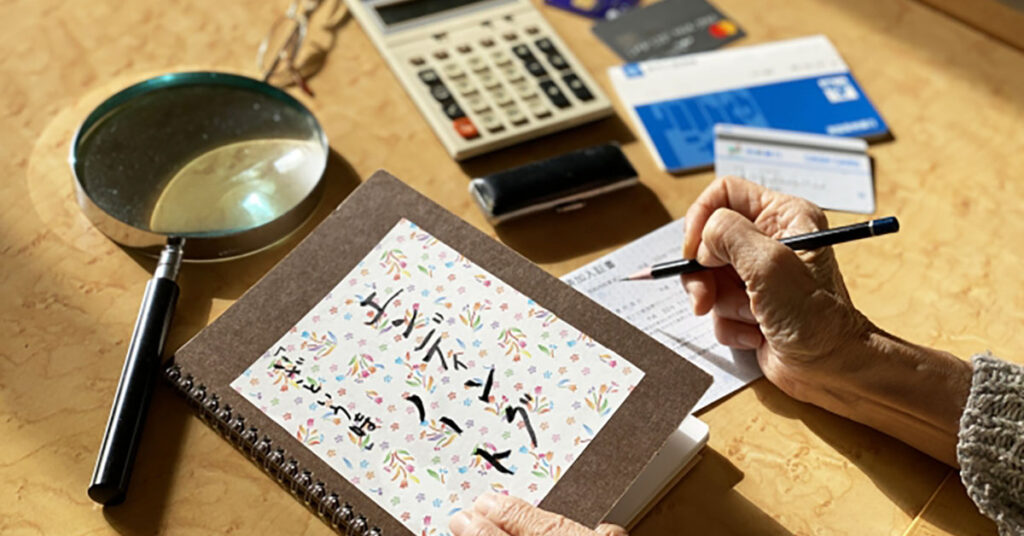
ここからは、終活を始めるタイミングについて紹介していきます。今回紹介する内容は以下のとおりです。
- 定年退職後
- 環境や体調の変化が出たとき
- 子どもができたとき
- 身近な人が亡くなったとき
一つずつ見ていきましょう。
定年退職後
終活を始めるタイミングは、定年退職後がいいという方が一番多いのではないでしょうか?毎日の仕事がなくなった分、余裕をもった終活をすすめるのに一番適しているかもしれません。
終活を始める方は60〜70代が一番多いというデータもありますので、まわりの人と相談しながらすすめることもできますね。
また、定年まで働けたということは体も元気である証拠ですので、体が衰えて終活が進まなくなる前に進めておくとよいですね。
環境や体調の変化が出たとき
定年退職も一つの例ですが、まわりの環境や自身の体調の変化が出たときに終活を始めるのもいいタイミングになります。終活は余裕をもって進めていくことが大事ですが、なかなか進まないという方でも病気や体調の変化で「そろそろ終活を始めたほうがいいかな」と感じてきますよね。
体の衰えていくスピードや急な環境の変化は自分でもわからないので、思い立ったときに始めていきましょう。
子どもができたとき
「子どもができたときは流石に早過ぎるでしょう!」と感じる方もいると思いますが、人はいつ亡くなるかわかりません。子どもができたあとすぐ亡くなってしまった場合、残された家族は途方に暮れてしまいます。
そうならないためにも、最低限のことをやっておくのが良いでしょう。終活は、親としての責任をまっとうするうえでも大切です。
身近な人が亡くなったとき
身近な人が亡くなったときも、終活を始めるにあたっていいタイミングになります。人の死を目の当たりにすることで、誰にでも来るものだと意識するきっかけになるんです。
自分の人生の終わりを自分の思ったとおりに進めてもらえるよう、身辺整理やエンディングノートなどを書き始めてもいいかもしれませんね。
まとめ:終活は早めに始めるのがおすすめです

ここまで、「終活の種類」と「終活を始めるタイミング」について解説してきました。
「思っていたより色んなことをやらなければいけないんだ!」と感じた方は、自分が想定していたより早めに進めることができると思います。終活はとても時間がかかるものですので、後悔のないように余裕をもって早めに始めるのがおすすめです。
早めに終活を終わらせておくと、充実したセカンドライフを送ることにも繋がります。久しぶりに夫婦で旅行に行ったり、ゆっくり親族を迎えたりするためにも心と時間の余裕は大事ですよね。
終活だけに限らず、将来や今後に関わることは早めに済ませておくようにしましょう。
「子どもができたとき」の章で解説したように、人はいつ死ぬかわかりません。事故に遭うかもしれないし、自分が気づかなかった急病で余命が短いとわかる場合も。
「もしも」の場合に備えておくことは終活の場合でも大切なことです。どれだけ早くても終活をしておくことに無駄はありませんので、家族や親しい人たちのことも考えて終活をすすめるようにしましょう。









