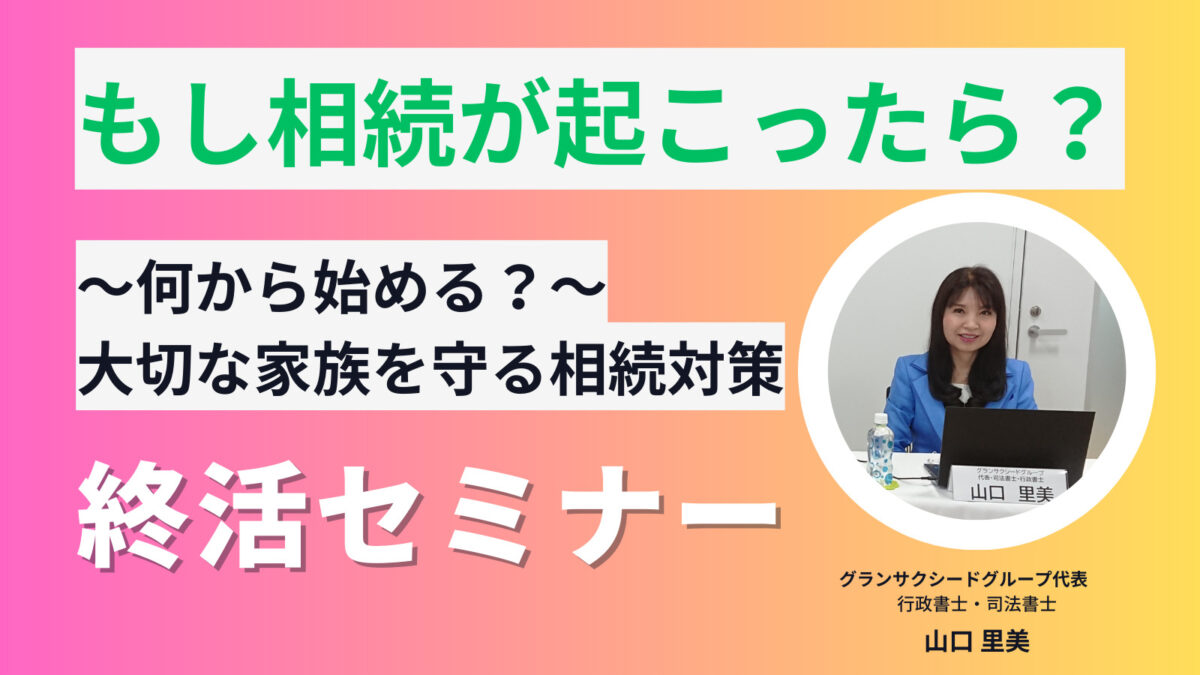誰にも必ず訪れる、人生最後の日。穏やかにその日を迎えるため、最近では多くの方が「終活」を行うようになりました。しかし、終活で取り組んでおきたい事柄は多岐に渡り、一朝一夕でできるものばかりではありません。 そこでこの記事では、終活を始めるのにメリットのある年齢や、終活でしておくべきことについてご説明します。残されたご家族のためにも、知識を付けて実践していきましょう。
終活を始めるのに適した年齢とは?

終活というと、年齢を重ね60~70代を迎えた方のものであるというイメージが強いですが、終活を始めるのに適した年齢の定義はありません。いつ始めてもよいものです。なぜなら、人生の終わりはいつ訪れるかわからないからです。
そのため、年齢にこだわるのではなく、「終活をしたい」と感じた時に始める方がメリットは大きいでしょう。一般的には、次のような節目が、終活を考えるタイミングとなることが多いようです。
- 終活は定年を迎える年齢から
- 終活は親が亡くなった時から
- 終活は病気などで終活や死について考えた時から
順番に解説します。
定年を迎える年齢
一定の年齢を迎え、力を注いできた職場から去る定年のタイミングは、終活のきっかけにふさわしいものです。心血を注ぎ、人生を捧げてきた職場から去ると、突然時間に余裕ができ、ぽっかりと穴が開いたような戸惑いが生まれます。
この余裕の時間が手に入ることで、これまでは考えたことのない「これからの人生」について、考えられるようになるのです。
退職したばかりの頃は、まだ気力にも体力にも恵まれ、考えたことを行動に移すだけのバイタリティがあり、終活するにあたってはメリットとなります。元気があるうちに終活を始めれば、やり残したことにも十分にチャレンジできるでしょう。
親が亡くなった時
身近な人が亡くなった時も、終活を始めるきっかけです。急に「死」が身近な存在に感じられて、自分の死についても考えるようになるため、自分自身の最期を意識する方が多いのです。
終活をすることは、残りの人生でやり残していることを整理し、セカンドライフを楽しむきっかけにもなります。終活を前向きにとらえて行動に移すことは、自分亡きあとの家族・子どもへの思いやりとして遺す意味でも、大切なことなのです。
病気などで終活や死について考えた時
病気で入院し、自分の体が思うように行かない体験をした時も、終活を始めるよいタイミングです。どんな方でも年齢を重ねると、体にも徐々に不具合が現れ、若い頃のように元気に生活できる日ばかりではなくなっていきます。
病気を患い、自分について考えることを余儀なくされれば、これからの人生での健康管理や、余生の過ごし方について考えざるを得ません。死とは何か、どんな風に受け入れるかを意識し始め、それを終活に活かしていくことができるよい機会となるでしょう。
また、自分自身の健康についての意識を高められるメリットもあります。
終活ですべきこと
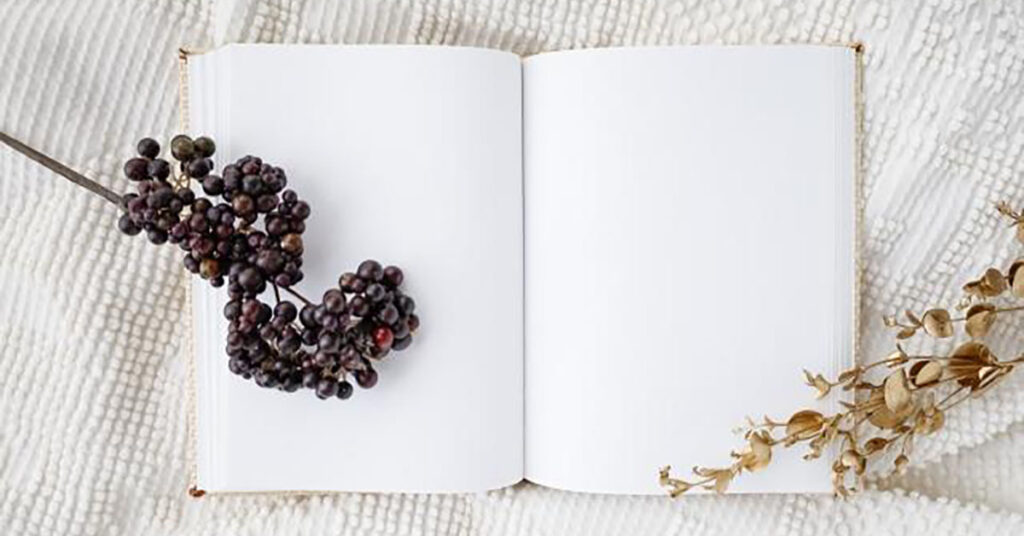
では、実際に「終活」とは、どのようなことをするのでしょうか。「自分や残された家族が、いざと言う時に困らないように……」と言うだけでは、具体的な取り組み方はわかりません。
そこでここでは、実際に終活ではどのようなことに取り組んでおくとよいのかを、具体的にご説明します。
- 医療の方針の相談
- 葬儀・お墓について相談する
- 遺言書の作成
- 終活に向けての生前整理
- エンディングノートの作成
一つずつ見ていきましょう。
医療の方針の相談
終活では、介護や医療の方針について意思を示しておきましょう。高齢になって病気にかかり、終末期を迎え自分の意志が示せなくなった時には、代わりにご家族が介護や医療方針を医師に伝える必要があります。
そのときにどこまで医療提供を受けるのかや、どこで最期を迎えたいかなどをあらかじめ共有しておくと、ご家族が戸惑うことがありません。
葬儀・お墓について相談
自分が旅立ったあと、どのようにして葬儀を行ってほしいのかも、あらかじめご家族と相談していくようにします。家族葬にするのか、お別れの会を開いてほしいのかなど、葬儀の方針を話しておきましょう。
そのほかにも、埋葬するお墓はどうするのかも重要です。ご家族のお墓に入るのか、お墓がなければ買っておくのか、それとも墓じまいをするのかなども相談します。
遺言書の作成
財産の分割方法などについて書き残しておく「遺言書」の作成は、終活の中でも大切な作業です。法的効力を持つ書類であるため、相続争いを防ぐ意味でも、必要なことを書き残しておきましょう。
書き方がわからない、何を書くべきか困った場合は、専門家に相談しましょう。
エンディングノートの作成
エンディングノートとは、死ぬまでにやっておくべきことや、死んだあとに家族にしてほしいことを書き残しておくノートです。死の準備のためではなく、自分自身が残りの人生を目いっぱい楽しむための、前向きなものと考えましょう。
エンディングノートには、下記の内容を自分亡きあとに遺族が困らないように記しておきます。
- 自分の生年月日、住所などの基本情報
- 親しい友人の連絡先
- 財産、年金、保険
- クレジットカード情報
- 終末医療・葬儀・お墓の希望
- 自分史
自分史には、これまでの人生を見つめなおし、セカンドライフを充実させるためにも、死ぬまでにやっておきたいことをリストアップしておくとよいでしょう。併せて、模様替えや季節の変わり目などのタイミングごとに、自分の身もまわりの整理も始めておきます。
終活をするときに気をつけること

終活でするべきことについて触れてきましたが、実際に終活を行うとなったときは、どんなことに気を付けて進めていくのがよいのでしょうか。この項目では、終活にあたっての注意点を挙げています。
終活は家族と相談しながら行う
終活は、ひとりで進めるのではなく、家族と相談しながら進めていきましょう。
特に、終末医療や葬儀については、就活している本人と家族の希望が合わない場合もあるからです。家族と遺志の共有ができていれば、自分が動けなくなった時にも、気持ちを汲んでサポートしてくれるかもしれません。
遺言書=エンディングノートではない
残された方に遺志を伝えるためのエンディングノートですが、法的な効力は持っていません。
特に、財産分与に関しては自分がこの世を去ったあとにもめごとになることも多いですが、エンディングノートに遺言を書き残しても、法的には認められないのです。家族が困らないように、守ってほしいことは法的効力を持つ遺言書に遺しておきましょう。
終活を前向きなものと考える
そして、終活を考えるときに大切な点は、「終活は前向きなものである」ということです。死は万人に対し平等であり、必ず訪れるものですから、「終活」の先に「死」を予感させるイメージがついて回るのは仕方のないでしょう。
しかし、いずれ迎える死に怯えるあまり目を背けてしまうことや、やりたいことをする気力まで失っては、残りの人生が輝きを失ってしまいます。
終活は、自分と愛する人たちの信頼関係を示すものです。家族と話し合い、自分の遺志を示すことは、最後に遺せる愛情ともいえるでしょう。
まとめ:終活は何歳からでも始めたい活動

終活とは、自分の人生を見つめなおし、最期を穏やかに迎えるための準備です。 60代を過ぎてからの終活が一般的ですが、早く取り組めばその分未来を見通して人生の計画を立てることもできます。早いからと言って、デメリットはありませんので、体力のある早いうちから準備するのがよいでしょう。